再び童話を題材に読書感想文を書いていきたいなと。
今回はイソップ童話を題材に10作品くらい読んでみて感想を書いてみますね。
イソップ童話1回目は『ウサギとカメ』の簡単なあらすじと感想文を書いていきます。
有名な話ですし、そのままの解釈をしてもつまらないので、いつも通り斜に構えて書いていく予定です。
『ウサギとカメ』の簡単なあらすじを確認してみよう
まずはご存知の方も多いと思いますが、あらすじを簡単に確認していきましょう。
分かりやすい良く出来たお話ですよね。
イソップ童話はいわゆる寓話(比喩によって人に教訓を伝える物語)なので、読んでいて面白いですし、『人の振り見て我が振り直せ』のように「自分も反省しないとな…」と気を引き締める意識も与えてくれます。
軽く『ウサギとカメ』の教訓について一緒に学んでおきましょうか^^
『ウサギとカメ』の教訓は『油断大敵』
『ウサギとカメ』の教訓として一番しっくりくるのは『油断大敵』でしょう。
普通にやればウサギの圧勝だったのに、過信して思いあがって油断したがためにカメに負けてしまう。
ライオンはウサギを狩る時でも全力を尽くすというに、相手がどうあれ、簡単なことでも決して手を抜かないことが大切なのですね。
一方で、カメ目線で考えると能力で劣っていても着実に進むことで大きな成果を得られることもあるということも言えるかもしれません。
だから、どんな事に対しても一生懸命に取り組むことが大事と習うこともできるでしょう。
この2つの教訓を理解した上で、別の見方ができたら面白いかなと思ったので、そういった視点の読書感想文を書いてみました。
では、私の『ウサギとカメ』の読書感想文をご覧くださいm(_ _)m
『ウサギとカメ』の読書感想文
私にはカメの考えが理解できない。
なぜ足の速いウサギに対して『かけっこ』での勝負を選んだのだろうか。
歩みがのろいことをからかわれて腹が立ったことは理解できるが、だからと言って相手の得意分野に飛び込んでまで勝負する必要はあったのかは甚だ疑問である。
ところが、ふたを開けてみればカメの大勝利。
ウサギは自分の力を過信してしまい、途中で居眠りをしてしまう。その間に着実に歩みを進めたカメの努力が実を結び世紀の番狂わせを演じてみせた。
『油断大敵』という教訓がとてもよくわかる物語だろう。
しかし、この勝負に勝ったのはカメだけれど、果たしてそれを喜んでいいのだろうか。
物語はココで終わるが、物語を終えた後も一生は続く。偶然の勝利に一喜一憂していいのだろうか。
おそらく、両者が再び相まみえることがあった時、もうカメはウサギに勝つことはできないだろう。
両者には圧倒的な能力差があるし、今後ウサギが油断することはない。そして、カメがどれだけ努力してもウサギより足が速くなることはないからだ。
勝てる可能性があったのは最初の一回だけであろう。本来ならそのためにあらゆる準備をする必要があるはずだ。
けれども、カメはただ一生懸命走っただけだった
だからこそ、無策で勝負に挑んだカメが私は信じられないのである。
弱者は考えなければならない。
どうすれば能力差を埋められるか戦略を練って、万全を期して勝負しなければ、相手が油断する事でしか求める結果は得られない。
例えば、カメは川を通るルートを提示する必要があった。泳ぎならウサギよりもカメの方が得意なはずだから。
あるいはもっと距離を長くしても良い。瞬発力に自信がなければ持久力で勝負するのも一つの戦略だ。
自分より優れた相手に勝ちたいのなら、どうしたら自分の有利な条件で戦えるかをちゃんと考える必要があるだろう。
勝負は時の運である。だから、一発勝負なら偶然で弱者が強者に勝つ事もあるだろう。
けれども、競争は続く。そして、その多くで結果を出すのは能力の高い強者のはずだ。
だからこそ、弱者がその中で結果を求めるのなら、一つ一つの勝負を大事にし、戦略を持って戦うことが必要なのではないだろうか。
たとえどんな相手だろうと、自分にできることを把握し、戦略を考える。そして最大限のパフォーマンスを出せる人を目指したいと思った。
(962文字)
『弱者』に注目して物語を考察
『ウサギとカメ』を『強者と弱者』と考えて感想文を書いてみました。
それで言うと私はカメタイプだと思うので、「どうやったらカメでもウサギに勝てるのかな?」と考えてみたのですね。
それで「泳いだらいいんじゃないか?」「距離伸ばしたらどう?」などを必死に考えたのに、この物語のカメはあろうことか無策で、感情的に勝負に挑むというね。笑
「それは無いだろう!Σ(゚Д゚)」と思って、あんな感想文になりました。
周りを見渡せばハイスペックな人ばかりですからね。とても自分の能力で真っ向勝負して勝てる気はしません。
だからといって「じゃあ勝てないか」と言われたらそんなこともないと思っています。
自分の能力を理解して戦略を考えれば弱者だって勝てると思うし、思わぬ力を発揮できるとも考えられます。
バトル漫画で言う『能力は使いよう』みたいなところですか?
ただ、2勝8敗や3勝7敗でも、利益が出ればトータルで言えば勝ち。
目の前の勝敗にこだわりすぎるのも良くないかもしれない。
将来勝つために今は負ける。それだって立派は戦略だと私は思っています^^

『ウサギとカメ』の物語には続きがあった?
そういえば、『ウサギとカメ』の物語に続きがあるって知ってましたか?
調べてみたらウサギとカメのそれぞれの『その後の物語』があるようです。ちょっと面白そうなので、軽く確認しておきましょうか。
ウサギ編は『負けウサギ』というタイトル。
【かけっこでカメに負けたウサギは、仲間に馬鹿にされ村を追い出される。しかし、オオカミに村が狙われていることを知り、そのオオカミをやっつける。英雄となったウサギは仲間に温かく迎え入れられる】
というお話だそうです。一方のカメ編(タイトル不明)のお話はこんな感じ。
【ウサギに勝ったカメは「なんでもできるんだ!」という気持ちになり、あらゆることに挑戦した。ある日、ワシに頼んで空高く飛んでくれとお願いする。ワシは言われた通り空高く飛び、そこからカメを落とした。カメは飛べるはずもなく地面に激突してしまい砕け散ってしまった】
というお話。何だか悲しい結末ですね。
どちらものお話も『ウサギとカメ』の結果とは反対の結末を迎えることになっていますが、やはり一時的に成功しても意味がないし、一度の失敗で悔やんでも仕方がないという事は伝わります。
物語は切り取った話ですが、人生は続くことを考えると勝敗以外の部分に目を向ける大切さみたいなのは言えるのかもしれません。
★イソップ物語の読書感想文まとめ

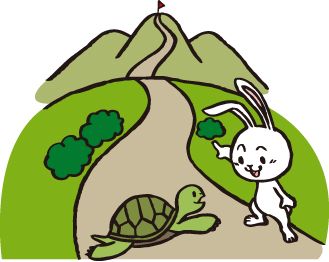

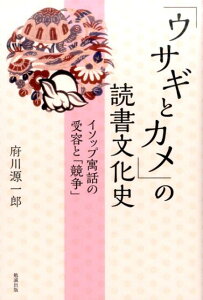


コメント
>物語はココで終わるが、物語を終えた後も一生は続く。偶然の勝利に一喜一憂していいのだろうか。
物語の不確定な要素をきちんと見つめ「どう受け取れば人の生き方にプラスになるだろう」という考え方にとても共感しました。
そして「弱者がその中で結果を求めるのなら、一つ一つの勝負を大事にし、戦略を持って戦うことが必要」は人生の真理だと思います。
だからこそ「相手の得意分野に飛び込んでまで勝負する必要はあったのかは甚だ疑問」(しかも無策で)という、感想は合理的に受け取れます。
じつは私、同じような着目点から考察を重ねて、カメの行動に合理的な理由を見出しております。
もし興味を持っていただけたら光栄と思い、コメント欄にその前半部分を投稿いたします。
興味を持っていただければ後半も投稿致します。つまらなければスルーしても削除しても結構です。
長文ですが、楽しんでいただければ幸いです。
突然ですが、童話(おとぎ話)ってどんな話でしょうか。
ハッピーエンドからブラックエンドまで多種多様な話がありますが、基本的には「子供に人生の教訓や生きるための知恵を伝える話」と考えてよいでしょう。
そして古くから語り継がれてきた話は「多くの人に共感された」からこそ時代を超えて語り継がれてきたともいえ、そこに伝わる教訓は人間の本質を捉えていると思います。
子供に向けて語られる話の奥に「大人でもためになる教訓」があるのなら軽く見るのはもったいないです。
一例として「ウサギとカメ」で深堀ってみたいと思います。
①大人向けとはリアル
それでは「大人向けに考える」とはどういうことでしょう。
一言でいえば「リアルに考えること」といえます。
重要なポイントは「部分的にリアルに取りあげる」のではなく「考察そのものをリアルにする」ことです。
「部分的にリアル」の代表例は、実際のウサギとカメの走行速度をツッコむことです。
ノウサギの走行速度は時速60㎞以上、カメは時速0.5㎞といわれています。
時速60㎞というのは60分で60㎞進みます。なので5分なら5㎞進みます。
その5㎞をカメが進むには10時間かかります。
この競争ではウサギは抜かれたうえに追いつけません。
となると必要な時間はもはや居眠りのレベルではなく「話が成立しない=だから実際にはあり得ないファンタジー」という論法が立ちます。
これは確かに走行速度に関してはとてもリアルな考察です。
でもよく考えると「会話している」という「もっとファンタジーな要素」が見落されています。
ウサギとカメを隣り合わせたら「キミ足遅いね」「じゃあ競走しましょう」なんて会話を始めるでしょうか。
そんなことカメが走りで勝つよりあり得ません。
「部分的にリアルに考える」では結局考察が行き詰まるのです。
「考察そのものをリアルにする」というのは物語のすべてを因果関係も含めて説明できるようにすることです。
「会話」に関していえば答えは一つです。
それは「会話する時点でこの話は人間の話だ」と解釈することです。
「ウサギのような人」と「カメのような人」の話、と考えるのです。
ではなぜ「擬人化した動物のキャラクター」を使うのか、というと「子供に分かりやすく伝えるため」です。
これがもし大企業の経営者と町工場の社長の話だったら、小さな子供には理解不能です。
おとぎ話に登場する「小人」「魔法使い」「モンスター」などのキャラクターは、大人社会の出来事を子供でも分かる話に変換する役割を担っているのです。
物語がじつは人間の話であることを踏まえつつ、話の全体像を考えてみます。
この話はざっくり言えば「足の速い者がサボったために、足の遅い者に負ける話」です。
対照的な登場者のみで語られる展開は「対比」という形でメッセージを伝える構造です。
伝えるテーマは「物事の取り組み方の善し悪し」となります。
ここから本格的な考察に入ります。
やり方としてはストーリーを大事なポイントのみに要約します。
この話においては下記の4つです。
4項目の因果関係を明確にすることで、この文脈で伝達可能なメッセージを全て炙り出し、本質的な教訓を見出します。
ストーリーの要約(4項目)
①ウサギがカメを馬鹿にする。
②カメが競争を提案し、ウサギが受ける
③ウサギが大量リードに油断して居眠りをする。
④カメが勝つ
これが物語の構造を最も簡潔にした状態です。
ここから4項目の「そうなった理由」を結果側から考えていきます。
出来る限り当たり前な「確かにそうだね」という理由が望ましいです。
④の考察 カメが勝った理由は何か
『ウサギがサボったから。カメがサボらなかったから』
********
という考察を積み上げていくものです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
>コメントありがとうございます!
こんな趣味で書いた感想文を真剣に読んでいただけて…とても申し訳ない気持ちでいっぱいです(;゚Д゚)笑
でも、同時に非常に嬉しく思います!(`・ω・´)ゞ