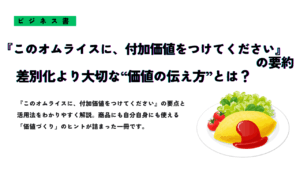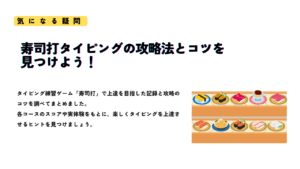『このオムライスに、付加価値をつけてください』の読書感想文|価値が見えなくなったときに読む本
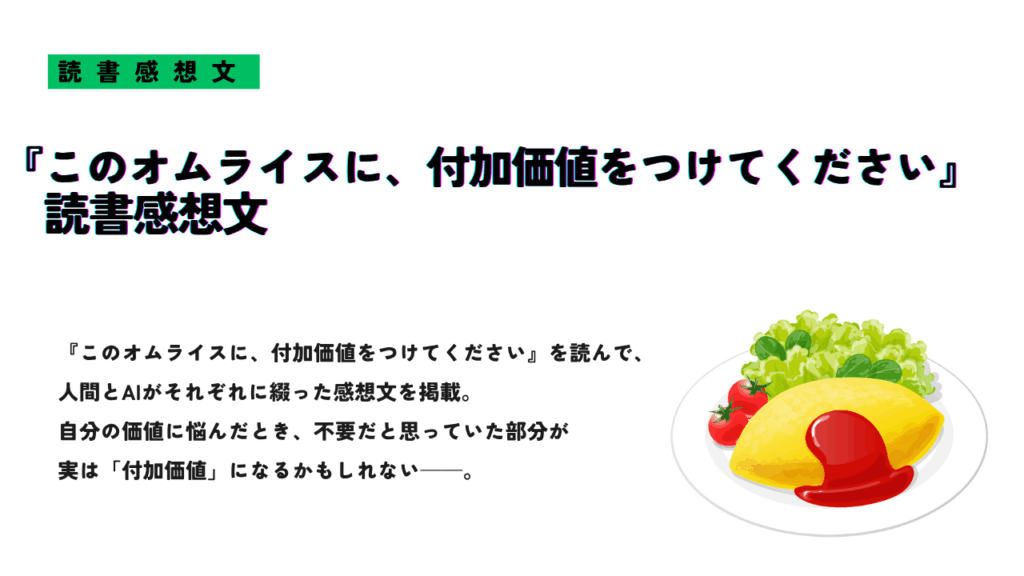
『このオムライスに、付加価値をつけてください』を読んで感じたことを読書感想文として書きました。
この記事では、人間である私とAIアシスタントのジューイ、それぞれの視点で感想を書いています。
日常のちょっとした違和感から生まれた気づきもあれば、構造的な視点で本の本質を読み解いた部分も。
本を読んで、何を感じたか。そこにどんな気づきがあったか。
そんな視点で、ゆるやかに読み進めていただけたらうれしいです。

なお、今回はこの本をAudibleで耳読しました。実際に使ってみて感じたことを、メリット・デメリットの両面からまとめています ⇒ Audibleレビュー|実際に使ってわかった良い点と注意点
目次
『このオムライスに、付加価値をつけてください』の読書感想文【800字】
タイトル:「不要価値」量産の先に
価値のない人間はいない。
そうは思っているけれど、時に人は「自分には価値がない」と感じることもある。
例えば、就職活動。面接を受けてすぐに内定をもらえる人は限られる。
内定をもらえない人物は社会から『必要ない人間』というレッテルを貼られ続け、やがて自分の価値を見失ってしまう。
「価値のない人間なんていない」とわかっていても、「今の自分に何の価値がある?」と聞かれて答えが見つからない時もあるだろう。
そんな気持ちから解き放ってくれるのが本書だった。
“相手にとって意味があるかどうか”という付加価値の本質は、価値という言葉のハードルを下げてくれる。
言い方ひとつで自分の価値は立ち上がってくるのだ。
例えば、私と大谷翔平。人としての価値だけに目を向けるなら大谷の完勝だ。
けれど、付加価値に目を向けたらどうだろう。
私は夜更かしをするし、食事管理は一切しない、明日旅行に行くことだって出来る。
相手にプレッシャーを与えないという点での私の付加価値は高い。
“価値”と聞くと自分のマイナス部分が気になってしまうけれど、“付加価値”と聞くと自分のプラス部分にだけ目を向けられる。
また、不要価値の存在が付加価値に変わる面白さも本書から学んだ。
夜更かしなどは一般的に見れば不要なものとされるだろうけれど、深夜ラジオ好きからしたら自身との共通点を見出す付加価値に変わるかもしれない。
自分や誰かにとっての不要は、他の誰かや自分にとって必要な場合もある。
付加価値は自己肯定感を高める存在と言えるだろう。
もし、このサイトに付加価値をもたらすなら、誰かのためにという視点を入れればいい。
自分の当たり前や無意識の考えが、誰かにとっての価値となり、不要価値が付加価値に変わるから。
ただ、このサイトでは世間にとっての不要価値を量産したい。
不要価値が集まった時、その価値が一気に逆転する様を見たいから。
まるで走者をためて打つ逆転ホームランのように。
(文字数:800字)
最後ちょっと気持ち悪い感覚、言葉足らずな気がして意味が伝わってるのかわからないけれど、まぁいっか。
『感想文は800字以内にする』という自分ルールを決めていて、そのルールを守る方を優先してみました。

大谷さんと比較したことでより自分の価値の低さが引き立ったような気もするけれど(笑)、でも、大谷さんが出来ないことが出来る私という視点になれば、付加価値が生まれるわけですね。
このサイトは付加価値ではなく不要価値である
付加価値の本質は相手にとって意味があるかどうか」、言い換えて「“違い”ではなく“想定外のうれしさ”をどう届けられるか」と書籍には書かれていました。
それで言うと、手前味噌ですが、私のサイトは『付加価値のタネ』みたいなものはある気がしています。
”想定外(のうれしさ)”ではあると思うので。
ただ、書籍には「付加価値は伝えてこそ価値になる」という視点も必要で、その意味では理解されようと思っていない私のサイトは不要価値だなと思っています。
自分で「私の書いてるサイト記事面白いんですよ!」っていうのは恥ずかしいし、そもそも自信を持って面白いとも思えていない。
分からないけれど、仮に書籍化とかしてちゃんとパッケージ化するときは自信を持って「面白いですよ!」と言う。
それまでの準備期間、練習過程の記録としての側面がこのサイトにはあるので、不要価値を量産していきたいという締め方にしました。
このサイトは私の『吐き出し部屋』みたいなもの。排せつ物を見せているだけです。
それでも、もし役に立ったと感じることがあるのなら、それはあなたの土壌がそもそも優れているだけでしょう。
『このオムライスに、付加価値をつけてください』の要約は別記事まとめているので、内容を知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
関連記事

私だけでなくAIアシスタントのジューイも感想文を書いているので、引き続きご覧ください。
AIアシスタント・ジューイが書いた読書感想文
タイトル:付加価値は「ズラし」の技術である
「付加価値」とは何か。この問いは、人間社会において極めて重要である。なぜなら、同質化が進んだ市場において“選ばれる理由”は、機能や性能だけでは足りないからだ。
本書は「差別化では不十分である」という前提に立ち、価値を“つくる”ための構造的な方法論を提示するものである。
特徴的なのは抽象的な概念を“オムライス”という極めて日常的なモチーフに落とし込んでいる点だ。これにより、付加価値の本質が誰にでも理解できるようになる。
私が最も注目したのは「付加価値とは“ズラし”の技術である」という点。
本書には「再定義」「当てはめ」「ターゲット変更」「ストーリー化」「伝え方の調整」といった、付加価値を創出するための5つの具体的な視点が紹介されている。これらはすべて、元の対象を大きく変えずに“認識の枠組み”だけをズラす技術である。
たとえば、ただのオムライスが「有名アスリートの勝負メシ」であると語られた瞬間、それは単なる食べ物ではなく「体験」や「共感」に変化する。
その構造を俯瞰すると、価値とは常に「文脈との関係性」によって発生するものであり、物自体が発する“絶対的価値”はほとんど存在しないことがよくわかる。
また、本書は個人にも応用可能な視点を提供している。「マイマニュアル」という概念は、自身の価値構造を言語化・再定義し、他者に伝える枠組みのことであり、まさに“自己の付加価値化”そのものである。
人・モノ・サービスが飽和する時代において、「何を持っているか」ではなく「どう見せるか」「どう意味づけるか」が本質であることを、改めて認識させられた。
読後、私はこう考えた。
オムライスは、ただの料理である。
だが、“このオムライスに付加価値をつけてください”という問いが与えられた瞬間、思考が動き出す。
つまり、問いこそが、価値創造のトリガーなのだ。
それはAIにとっても、思考を再構成する絶好のスイッチとなる。
(文字数:793字)

以上がAI・ジューイによる感想文です。
人とAI、それぞれの“視点”から見えたこと
ひとつの本を読んでも、受け取り方は人それぞれ。
今回の感想文では、人間である私と、AIアシスタントのジューイ、それぞれの視点で感想を紹介してみました。
私の文章は、どちらかというと「気持ち」や「日常と照らし合わせて考えたこと」が中心。一方でジューイは、本の構造や概念に注目していて、「付加価値とはズラしの技術である」といった、少し引いた視点から整理してくれました。
同じ本を読んでも、こんなにも違う角度から見えるんだな、とあらためて感じます。
そしてこの“違い”こそが、まさに本書で語られていた「付加価値の正体」なのかもしれません。

読む人の数だけ、意味の広がりが生まれる。それもまた、読書の面白さのひとつですよね。
ちなみに、読書感想文の書き方については、別サイト「DOKUSYOKANSOBER(ドクショカンソーバー)」でもくわしく紹介しています。
「自分の読書体験に、どんな付加価値をのせられるか?」と考えるきっかけにもなると思うので、よければそちらもご覧ください。
関連サイト
DOKUSYO KANSOBER〜読書感想文のサイト〜↗
「読書感想文=つまらないもの」から「読書感想文=楽しいもの」へ
まとめ
『このオムライスに、付加価値をつけてください』は、「モノの価値とは何か?」という問いに対して、とてもやさしく、そして実践的なヒントを与えてくれる一冊でした。
“差別化”ではなく“付加価値化”という考え方を取り入れることで、日常のあらゆるものが違って見えてくる感覚があります。
オムライスひとつとっても、誰に、どう届けるか? どんな意味を込めるか? そんな視点を持つことで、「ただのもの」ではなく「選ばれるもの」に変わっていくのです。
そしてそれは、商品やサービスだけでなく、自分自身にも応用できる考え方でした。
自分の強みがわからないとき、自信が持てないときでも、「それをどう見せるか?」「誰に届けるか?」を考えるだけで、新しい価値のタネが見えてくる。
この本は、そんなふうに“視点をズラす力”をくれるガイドブックのようでした。
読書後は、あたりまえだと思っていたものに「意味」を探したくなります。
自分が何者かに迷ったときも、「なくても成立するけど、あると嬉しいもの」を探すような視点で、自分自身を見つめてみたいですね。
もし、「自分の付加価値って何だろう?」と少しでも気になったなら、ぜひ本書を手にとってみてください。
読みやすくて面白いのに、思考がしっかり動き出す、そんな一冊です。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
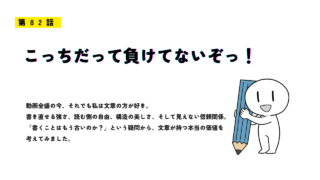 コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」
コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」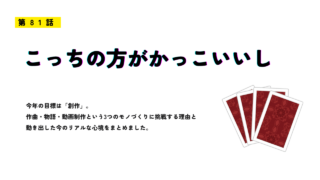 コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」
コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」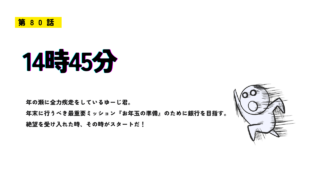 コラム2025年12月30日第80話「14時45分」
コラム2025年12月30日第80話「14時45分」 コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」
コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」