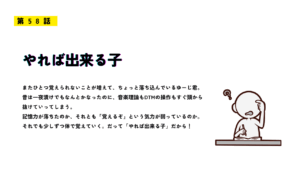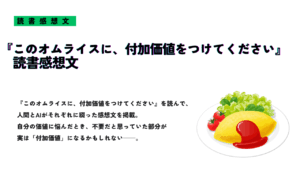【要約】『このオムライスに、付加価値をつけてください』|差別化より大切な“価値の伝え方”とは?
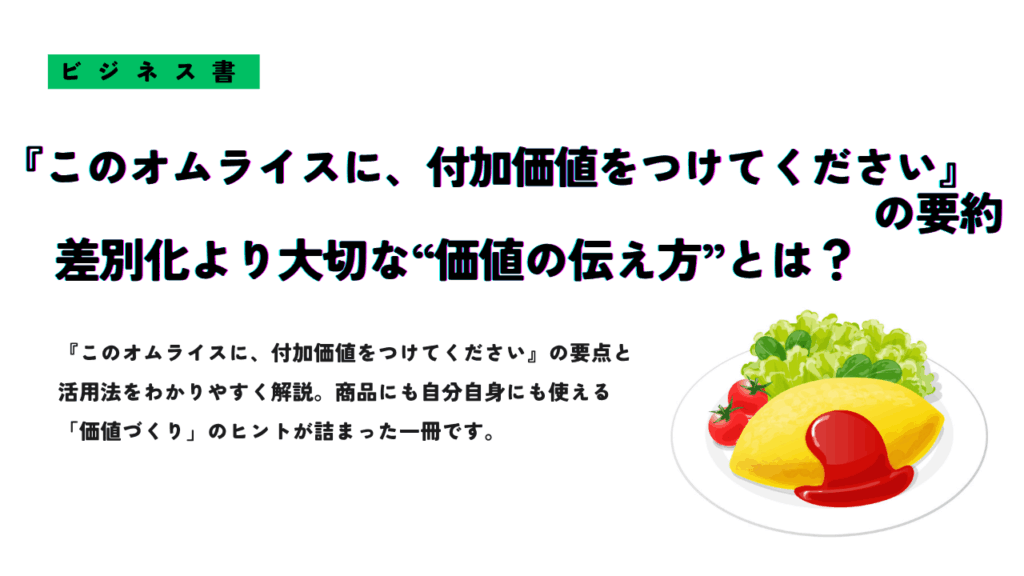
『このオムライスに、付加価値をつけてください』が教えてくれるのは、「何を変えるか」ではなく「どう意味づけるか」という視点。
すでに持っているものに“ちょっとした魔法”をかけて、「それが欲しい」と思ってもらえる価値をつくるための方法論です。
この記事では、そんな本書の魅力を5つの視点からやさしく整理しながら、あなたの商品やサービス、そして“あなた自身”にどんな付加価値を加えられるのか、一緒に考えてみます。

「足りない」を探すのではなく、「すでにある価値」を見つめ直す──
そんな視点を探している方へ、ぴったりのガイドになるはずです。

なお、私はこの本をAudibleで耳読しました。移動中や家事の合間にも学べて相性◎です。
初めての方は、登録から使い方までをまとめたこちらの記事をご参照ください
⇒ Audible初心者向け完全ガイド
目次
『このオムライスに、付加価値をつけてください』とは?
本書『このオムライスに、付加価値をつけてください』は、編集者として数々のベストセラーを生み出してきた柿内尚文さんによる、ビジネスにも人生にも役立つ「付加価値」の教科書です。
著者はこれまでに『パン屋ではおにぎりを売れ』『バナナの魅力を100文字で伝えてください』『このプリン、いま食べるか? ガマンするか?』といったユニークなタイトルの著書を通じて、「言葉と視点の力」で新たな価値を生み出してきました。
そんな柿内さんが本書で扱うのは「差別化ではなく、付加価値化」という考え方。
商品やサービス、さらには自分自身の強みや魅力をどうやって伝えるかに悩んでいる人に向けて、“誰でも使える付加価値づくりの技術”を、豊富な事例と図解でわかりやすく解説しています。
「差別化」ではなく「付加価値化」がテーマの一冊
「競合と違うことをやれば売れる」──これは、ビジネスにおいて長年信じられてきたセオリー。
つまり、差別化こそが生き残るためのカギだとされてきました。
けれど柿内さんは、こう問いかけます。
「その“違い”は、本当にお客さんの心を動かしているのか?」
ただ他と違っているだけでは、相手にとっての「価値」にはなりません。
たとえば、誰も望んでいない機能を搭載しても、それは単なる“不要価値”にしかならないのです。
本当に大切なのは「相手にとって意味があるかどうか」。
つまり、“違い”ではなく“想定外のうれしさ”をどう届けられるか。これこそが「付加価値化」の本質であり、本書のメインテーマです。
機能や特徴ではなく、「それがあることで、どんな感情や物語が生まれるか?」に着目する視点。
これにより、商品やサービス、そして自分自身に「お金を払いたくなる理由」を生み出すことができると、本書は教えてくれます。
タイトルの“オムライス”に込められた意味
なぜ“オムライス”なのか?
この素朴な疑問が、実は本書の核心につながっています。
普通のオムライスに見えても、たとえば「これは、あるオリンピック選手が子どものころから“勝負飯”として食べていたオムライスなんです」と言われたらどうでしょう?
同じ料理でも、一気に“特別な一皿”に感じられるはずです。そこにストーリーが乗ることで、人は共感し、魅力を感じ、価値を見出すのです。
つまり、“オムライス”とは、ただの料理ではなく「価値があるとはどういうことか?」を考えるための問いかけ。
「見た目は同じでも、文脈や意味づけによって“価値”は大きく変わる」という本書のテーマを象徴するアイコンなのです。
タイトルの問いかけ──「このオムライスに、付加価値をつけてください」──は、読者自身にも向けられています。
あなたの商品に、サービスに、仕事に、そして自分自身に、どんな付加価値をのせられるだろう?
そう考えることで、あらゆるものの見方が変わってくるはずです。
本書の要点を3つに要約
「付加価値って、なんとなくわかるけど、うまく説明できない」
そんなモヤモヤを、明快にほぐしてくれるのがこの本の魅力。
本書では、価値の正体をわかりやすく分類したうえで、「付加価値とは何か?」「どう生み出すのか?」「どう伝えるのか?」という3つの柱に沿って、私たちに大切な視点を与えてくれます。

まずは、そのエッセンスを順に見ていきましょう。
「付加価値」は“なくてもいいけどあると嬉しいもの”
本書では、「付加価値」を“なくても成立するけれど、あると喜びや感動を生むもの”と定義しています。
それは想定外の驚きであり、嬉しい意味づけであり、心がちょっと動く仕掛けです。
たとえば、あるレストランで出されるただの卵料理に高い値段がついていたとしても、「この卵料理は、30年間修業したシェフがたどり着いた一品です」と聞けば、それが単なる食事ではなく、物語や技術が込められた“体験”に変わります。
「美味しいから食べる」ではなく「この背景を知っているから食べたい」。
そう思ってもらえるのが、付加価値の力なのです。
この視点は、飲食に限らず、あらゆる商品、サービス、そして自分自身にも当てはまります。
「なくても困らない」けれど「あると選びたくなる」。
そんな価値を生み出すことが、これからの時代に求められているのです。
「価値」は誰かに届いてこそ意味がある
どんなに素晴らしいストーリーや背景があっても、それが伝わらなければ“ないもの”と同じです。
たとえば、オムライスに特別な意味があっても、黙って提供しただけでは、お客さんにはその価値が伝わりません。
だからこそ、「付加価値は伝えてこそ価値になる」という視点が非常に重要になります。
ここでポイントになるのが、「自分が価値だと思っているもの」と「相手が価値を感じるもの」は、必ずしも一致しないということ。
本書では、「誰に向けて」「どう伝えるか」という2つの視点が何よりも大切だと繰り返し説かれています。
つまり、付加価値は相手ベースでつくるもの。自分がいいと思うものではなく、相手が“欲しい”と感じるかどうかがすべてです。
伝わっていないなら、それはまだ「価値」ではない。
この厳しくも真っ直ぐな視点が、付加価値を考えるうえでの出発点になります。
付加価値は誰でもつくれる「技術」である
「付加価値をつけるなんて、センスや才能のある人にしかできないのでは?」
そう思ってしまうかもしれませんが、本書はきっぱりとこう語ります。
付加価値は“センス”ではなく“技術”である。
つまり、だれでも習得可能であり、再現可能な“考え方の技法”なのです。
たとえば、あるものの用途を変えて「再定義」する。
別の目的に「当てはめて」みる。
ターゲットを変更する、ストーリーをのせる、見せ方を変える──。
これらはすべて、本書で紹介されている「付加価値をつくる技術」です。
さらに、本書では多くの具体例(オムライス、高たんぱく食品、老舗肉屋、書籍のターゲット変更など)を通して、「視点の変え方」「届け方」「言語化の方法」まで丁寧に解説されています。

だからこそ、読後には「自分にもできるかもしれない」「さっそく試してみよう」と思わせてくれる実用性があるのです。
「オムライス」から学ぶ!付加価値を生む5つの視点
タイトルにもなっている“オムライス”は、本書の中で何度も登場する象徴的なモチーフです。
見た目は同じオムライスでも、ちょっとした視点のズラし方によって、その価値は驚くほど変化します。
ここでは、そんなオムライスを使った例から導き出された「付加価値を生む5つの視点」を紹介。
これらはどれも、商品やサービス、そして自分自身に応用できる、シンプルで強力な技術です。
「再定義」する|視点を変えて意味を変える
まずひとつ目は「再定義」というアプローチ。
たとえば、オムライスを「食事」として提供するのではなく、「甘いものが苦手な人の誕生日ケーキの代わり」として出す。
それだけでオムライスは、“代替スイーツ”という新たな存在に生まれ変わります。
同じモノでも、使う場面や目的をズラすことで、まったく新しい意味を持たせる。これが「再定義」です。
再定義は、「その商品・サービスは、何のために存在するのか?」という問いを、あえてズラしてみることで実現できます。
「当てはめる」|別の文脈で価値を持たせる
2つ目は、「当てはめる」という考え方。
本書では、オムライスを「応援メッセージを書くキャンバス」として使い、復興支援の募金につなげた例が紹介されています。
食べ物であるオムライスが、「想いを伝える手段」として使われたことで、まったく違った価値が生まれました。
これは、既存の商品やサービスに、別の意味や用途を“当てはめる”ことで、思わぬ付加価値をつける方法です。
すでにあるものに、まったく別の役割を担わせてみる。
「これ、こんな使い方もアリなのか!」と感じさせられる視点です。
「ストーリーを加える」|背景に物語をのせる
3つ目の視点は「ストーリー」。
たとえば、「このオムライスは、有名アスリートが子どものころからずっと食べていた“勝負メシ”です」と聞いたら──。
それだけで、ただのオムライスが、ぐっと特別な存在に変わりますよね。
背景にある「物語」は、感情を動かす最大の付加価値になります。
人は情報よりも、“意味”や“共感”によって行動します。
商品のスペックや見た目だけでは伝わらない“その奥にあるもの”を、物語としてのせてあげる。
それがストーリーの力です。
「ターゲットを変える」|届ける相手を見直す
4つ目の視点は「ターゲットを変える」こと。
たとえば、『のび太という生き方』という書籍は、当初は大人向けの自己啓発書として出版されました。
しかし、実際に読まれていたのは小学生やその親だったという分析から、子ども向けの読書感想文用の本として再設計されたことで、大ヒットにつながりました。
これは、提供する“価値”はそのままに、“届ける相手”を変えたことで成功した例です。
「この商品、本当に今のターゲットに合ってる?」
そう立ち止まって問い直すことが、新しい付加価値を生むきっかけになります。
「伝え方を工夫する」|価値を正しく“見せる”
最後は付加価値を「伝える技術」。
どれだけ素晴らしいストーリーがあっても、それが相手に伝わらなければ、価値として認識されません。
だからこそ、伝え方の工夫が不可欠です。
たとえば、お店で「このオムライスは〇〇さんのお母さんが作ったものです」と書かれたポップがあるだけで、その料理に込められた思いが伝わります。
本書では、伝え方の工夫として「名前をつける」「比喩で説明する」「図解する」「不要な説明を削る」といった具体的なテクニックも紹介されています。
価値は“届けて”はじめて成立する。
そのためには、「伝わるデザインと言葉」が欠かせないのです。
商品・サービスだけじゃない!自分にも使える付加価値の視点
本書『このオムライスに、付加価値をつけてください』で語られる付加価値の考え方は、モノやサービスに限りません。
実はこの視点、自分自身の強みや魅力を再発見するヒントにもなります。
「自分には特別なスキルがない」「アピールできる実績がない」と感じている人こそ、本書のエッセンスを取り入れてみてください。
“自分にしかない価値”は、ほんの少しの視点の変化で見えてくるのです。
仕事における“あなたらしさ”が付加価値になる
「この人にお願いしたい」「またあなたと働きたい」──
そんなふうに言ってもらえる人には、たいてい“その人らしさ”がちゃんと伝わっています。
仕事における付加価値とは、スキルや実績だけではありません。
「安心して任せられる」「細かいところまで気がつく」「いつも丁寧でやさしい」
こうした“無形の価値”こそ、じわじわと人の心に残り、信頼につながっていくのです。
つまり、あなたのふだんの姿勢やふるまいが、自然と「選ばれる理由」になっている。

それこそが、あなたにしか出せない付加価値です。
弱みも言い方次第で強みに変わる
「仕事が遅い」「おとなしい」「目立たない」──
そんなふうに、自分のことを“短所”として捉えてしまうこと、ありますよね。
でも、視点を変えてみましょう。
たとえば「仕事が遅い」は、「丁寧でミスが少ない」と言い換えられる。
「おとなしい」は、「冷静に周囲を見て判断できる人」ともとらえられる。
本書では、「できていないこと」にばかり目を向けるのではなく、“すでに持っているけれど自覚していない価値”を見つけることの大切さが語られています。
言い方ひとつ、見せ方ひとつで、自分の中に眠る価値は立ち上がってくる。
「自分の弱みは、裏を返せば誰かにとっての“安心ポイント”かもしれない」──そんな視点が、あなた自身の付加価値を引き出してくれるはずです。
「マイマニュアル」で自分の価値を言語化する
自分の付加価値を見つけるだけではなく、それを“人に伝えられる形”にする。これもまた、大切なステップです。
本書で紹介されているのが、「マイマニュアル」という考え方。
これは、自分の考え方やノウハウ、行動パターンを言語化し、整理してまとめておく方法です。
たとえば、「自分が仕事をするとき、何を大事にしているか?」「どんなときに力を発揮するか?」「どんな相談をよくされるか?」といった視点で棚卸ししてみると、自分では当たり前だと思っていたことに意外な価値が宿っていることに気づけます。
そしてそれを“伝えられる言葉”にしておくことで、あなた自身の付加価値が他者にとって明確に“見える化”されていく。

この「マイマニュアル」は、自己理解にも、自己表現にも役立つ、非常に実践的なツールです。

私とジューイが書いた読書感想文もあるので合わせてご覧ください。
関連記事
~準備中~
まとめ|「違い」より「意味」が伝わる工夫を
『このオムライスに、付加価値をつけてください』は、「差別化では不十分」というメッセージから始まり、「付加価値」という少し抽象的な概念を、誰でも使える“具体的な技術”として教えてくれる一冊です。
オムライスのように、ありふれた存在でも、視点や伝え方、届ける相手を変えるだけで、「選ばれる理由」になる。
その原理は、モノやサービスに限らず、私たち自身にも通じます。
重要なのは、「何が違うか?」ではなく、「それが相手にとってどんな意味を持つのか?」という問いです。
つまり、“違い”を探すのではなく、“意味”をつけること。
それが、これからの時代に必要な「付加価値化」の考え方です。
また、本書はビジネスパーソンだけでなく、「自分の価値をどう伝えたらいいかわからない」と感じているすべての人にとって、大きなヒントになるでしょう。
たとえスキルや実績が人より劣っていると感じていても、「あなたにしかない視点」や「あなたが持つ物語」は、誰かにとっての価値になります。

“あなたのオムライス”には、どんな意味をのせられるだろう?
そう自分に問いかけながら読むことで、この本のメッセージが、自分の人生にもすっとなじんでくるはずです。
気になった方は、ぜひ手に取ってみてください。
あなたの商品も、仕事も、そして生き方そのものも、もっと豊かで魅力あるものに変わっていくかもしれません。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
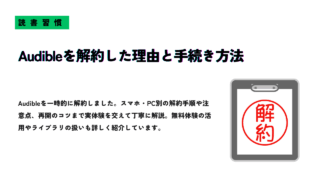 読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー
読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー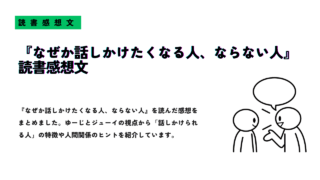 読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと
読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと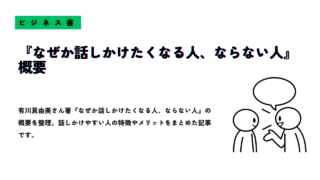 ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説
ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説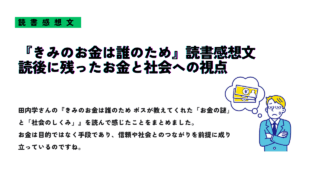 読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点
読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点