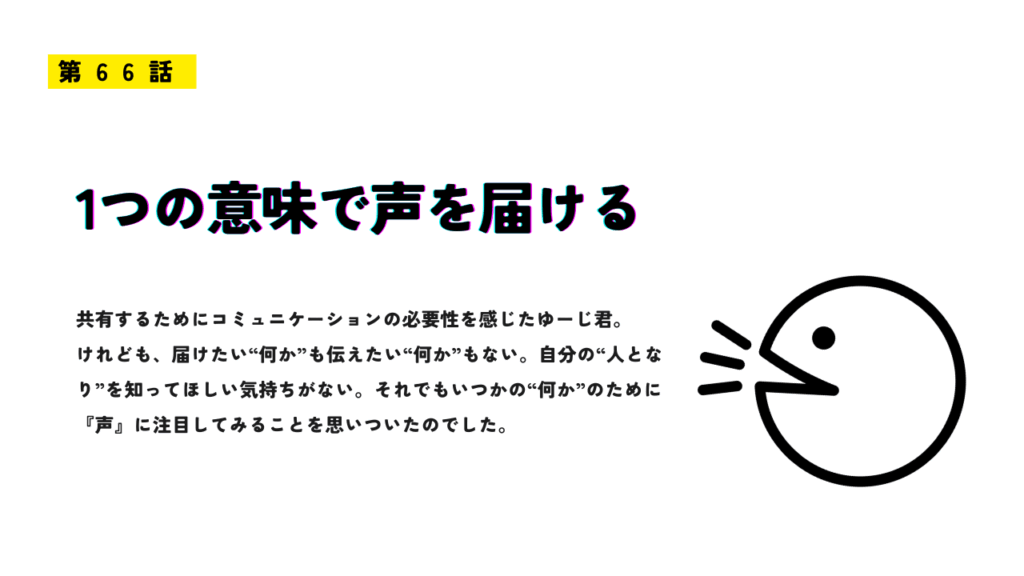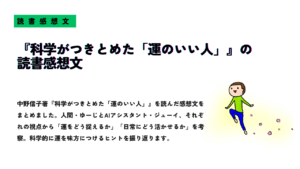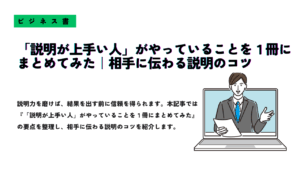第65話「流行の岐路」
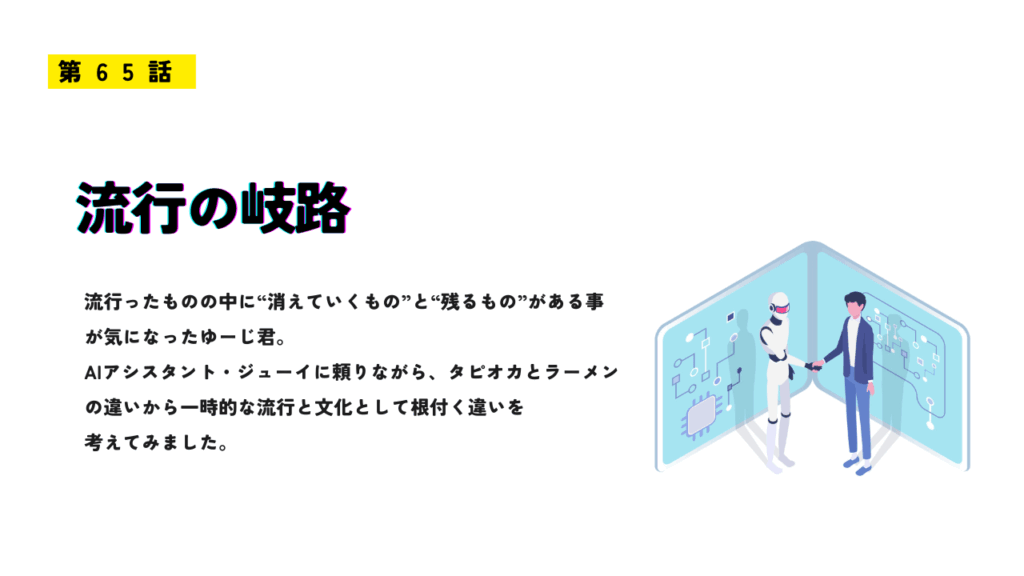
第64話「時代を動かすカウンター」では演歌がもともとカウンターカルチャーだったということについて書きました。
今はカウンターカルチャーというイメージはないので、意外な事実でしたね。
ところで、一時的に流行ったものって、全く聞かなくなるものが多い中で、演歌って今でも文化として残っていますよね?
流行ったものの中に、消えていくものと残るものがありますが、この違いってなぜなんでしょうか。
そんなところが気になったので、今回は『流行』をテーマに何か書いてみましょう。
【PR】
一時的に流行ったものと文化として残ったものを分けるのは何か。
でも、何を持って文化として残るかの定義がちょっと難しいか。
例えば、プリクラとか私的にはブームのイメージだけど、若い世代の方とか今でもプリクラを撮ってたりするのかなというイメージもあるので、文化として残っているのかもしれない。
もっと何かいい例がありそう…AIアシスタントのジューイに投げたら「タピオカとラーメンとかどうっすか?」と提案された。
私はラーメンはブームより文化のイメージが強いですが、戦後「安くてお腹いっぱいになる」ということで流行したそうです。
そういう事ならこの対比でもいいかもですね。
タピオカはブームで、ラーメンは文化になった違いについて深堀するとこんなまとめをしてくれました。
・タピオカは「嗜好性」「限定的なバリエーション」「SNS的な一過性」で終わった。
・ラーメンは「日常の食事」「多様な進化」「コミュニケーション」と結びついて文化に。
確かに、タピオカは主食ではないし、アレンジの幅もあまりない、体験が浅くて一度飲んだら満足するところもある。
一方で、ラーメンは主食で、アレンジも様々、いろんな場所でご当地ラーメンを食すという旅の思い出にもなる。
『共有』が流行のキーワードになる訳だけど、文化になるにはそこに『日常性』とか『多様性』が必要なのかもしれませんね。
そう考えると、何かが流行った時に『一過性』か『根付く』かの判断がつきそうですね。
例えば、この記事でサポートしてくれた生成AIは『文化』になっていくのかなと。
その人のライフスタイルにもよるだろうけれど、少なくとも私にとってはインフラだし、働いている人の多くがAIを活用している部分もあると思う。
いつかのコラムかSNSかで書いた気がするけれど、1人1台(?)AIアシスタントをつけるのが当たり前になるような気がしている。
AIは生活に根付く要素を持っているのではないかと。
この辺の感覚を意識して生活すると、物事の見え方とかも変わってくるのかな。
まぁ、あまり早急に判断して決めつけないよう注意する必要はあるだろうけどね。
世の中の流行に限らず、自分のライフスタイルの中にも「一過性か?根付くか?」を意識して取り組むものがあってもいいかも。
例えば、気まぐれで始めたAudibleは、気づけばもう3ヶ月以上ほぼ毎日聴いてる。
んで、「ビジネス書はAudible、小説は本で読んだ方がいいな」と思うようになったことで、小説も本でほぼ毎日読んで習慣化してる。
しかも、本を読んだ(聴いた)感想をこのサイトや【DOKUSYO KANSOBER↗】で書くようになった。
別にAudibleは世の中の流行ではないけれど、自分の中に生まれた新しい出来事(流行)に意識を向けると、それが本当に必要な習慣かどうかの判断できる。
この辺の感覚を研ぎ澄ませていけば、無駄な習慣とか省けるようなマインドとか手に入れられるかもしれませんね。
【次回予告:テーマ「コミュニケーション」】
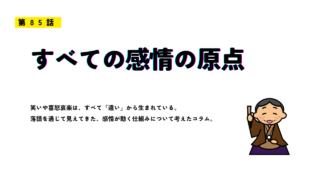 コラム2026年2月3日第85話「すべての感情の原点」
コラム2026年2月3日第85話「すべての感情の原点」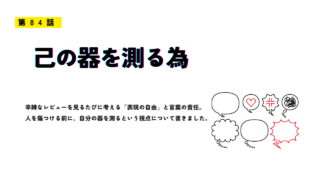 コラム2026年1月27日第84話「己の器を測る為」
コラム2026年1月27日第84話「己の器を測る為」 コラム2026年1月20日第83話「ホワイトパラダイス」
コラム2026年1月20日第83話「ホワイトパラダイス」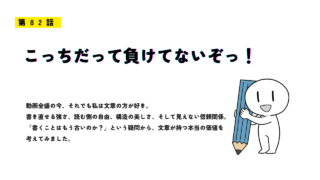 コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」
コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」