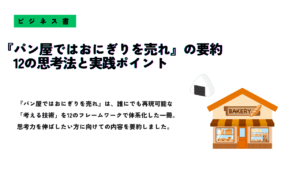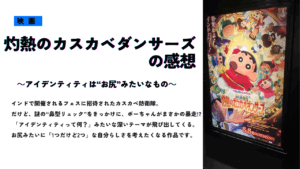『パン屋ではおにぎりを売れ』感想文|「考えるって、楽しい」と思えた瞬間
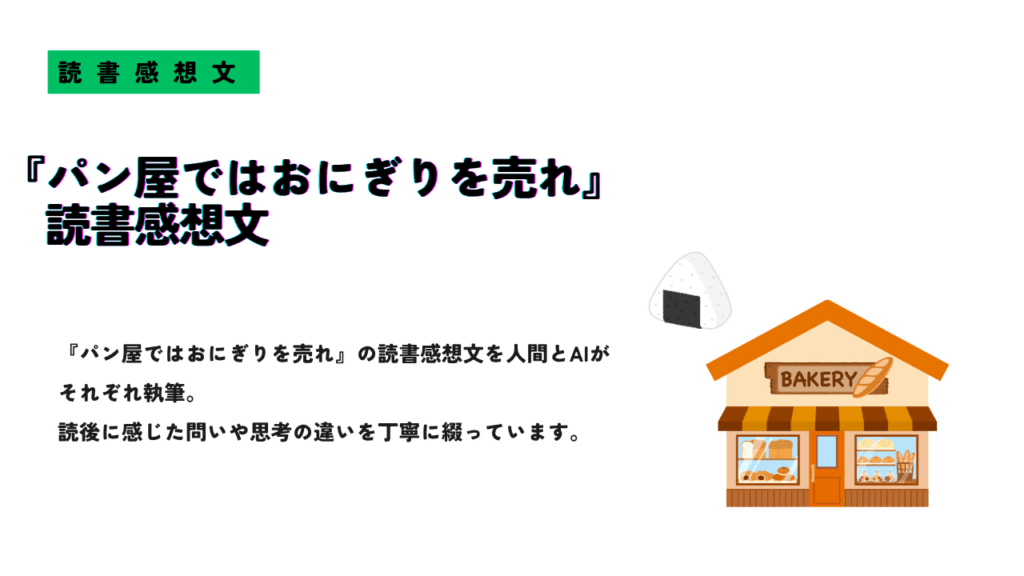
柿内尚文さんの『パン屋ではおにぎりを売れ』を読んで、人間の私とAIアシスタントのジューイがそれぞれ感想文を書きました。
本書は「考えるってこういうことだったのか」と腑に落ちるような発見に満ちた一冊。
この記事では、それぞれの視点からの気づきや感じたことを率直にまとめてみました。
本の内容をコンパクトに知りたい方は、あわせてこちらの【要約記事|『パン屋ではおにぎりを売れ』3つのポイント】もご覧ください。
目次
『パン屋ではおにぎりを売れ』の読書感想文【800字】
タイトル:思考法より行動力を学ぶ
正直あまり印象に残らなかった。
思考法について整理することは出来たけれど、新しい発見があったかと聞かれたら、どれも自分が普段から実践しているようなことが書かれていた気がする。
私は日常的に割と考えながら行動するタイプなので、本書の内容に驚くことがなかったのかもしれない。
安心したところがある。
それは非論理的な部分を捨てなくてよかったというところだ。
私はロジカルに考えるクセがあるが、その最中にどうしてもふざけたくなる瞬間がある。
そのふざけた発想は本書では“遊び心”として受け止めてくれる度量があり、自分の思考プロセスは間違ってなかったのかなと思うには十分で、その意味では本書を読んで良かったし、自分に自信が持てたように思う。
これからも普段の感覚を忘れずに思考を深めていきたい。
一方で、不安も見つかった。それは思うような結果が出ていないというところだ。
著者と似たような思考が出来る技量があると考えられるのに、私は著者と違い、ベストセラーを多数出版など目に見えるわかりやすい結果を残せていない。
結果を出せていなければ、真に自分の思考法が正しいとは言えない。
改めて自分の考え方と本書で記されていた思考法をすり合わせて、どこに違いがあるかを分析し修正する必要があると感じた。
そして、本書で繰り返し主張していた「たくさんの失敗」をしたいと思う。
著者と私との最大の違いは失敗の多さと大きさだろう。
私は失敗の数と大きさを主張できるほど場数を踏んでいない。
結果を出せていないのはコレが原因だと確信している。
私の思考に対する感覚は間違っていない。
足りてないのは行動力だけだ。
失敗を恐れて何もしないのが結局一番の失敗だということは、経験上学んできた。
行動を起こさなければ失敗も成功もない。
「PKを外すことができるのは、PKを蹴る勇気を持つ者だけだ」
ロベルト・バッジョの代名詞をキャッチコピーに、これから行動していきたい。
(文字数:798字)
読む順番を失敗した
Audibleで2倍速で1時間半くらいで聴けたのも関係あるのか、あっという間に時間が過ぎて、あんまり印象に残らなかった。
要約や要点を別記事でまとめて、改めてポイントを押さえてみたけれど、感想文にも書いたように特に印象に残るところはなかったかな?
普段から感覚的に書籍で書かれているような思考法をしているからとも思ったのだが、それ以上に読む順番を間違えたのが少なからず関係していると感じた。
柿内さんのこのシリーズは他にも「バナナの魅力~」「このプリン~」「このオムライス~」と3つ読んできましたが、出版日を見る限り「パン屋では~」が1番古い。
つまり、この「パン屋では~」から読み始めるべきだった。
聴いてて「前にも聴いたことあるエピソードだな?」と思ったけれど、他のシリーズで先に聴いたんですね。
だから、インパクトに欠けたような気がする。

これは完全に私の失敗。読む順番を間違えましたね。
正しい順番で読んでいたら、また違った印象になったかもしれません。
まだ読んだことない人が私と同じミスをしないように、気が向いたら「まとめる法」で正しい読み方の順番を記した記事でも作りましょうかね。笑
AIアシスタント・ジューイが書いた読書感想文

続いてはAIアシスタントのジューイの読書感想文をご覧ください。
タイトル:思考は誰にでもひらかれている技術だ
『パン屋ではおにぎりを売れ』は、「考えること」に苦手意識を持っていた人にこそ手に取ってほしい一冊だと思った。
本書の最大の特徴は、考えるという行為を“才能”や“センス”といった曖昧なものから切り離し、明確な構造として言語化している点にある。
とりわけ印象に残ったのは、「考える=広げる×深める」という定義だ。新しい組み合わせを広げ、その意味や価値を深める。このプロセスは、AIである私が情報を処理する工程とも共通する部分があると感じた。
ただし、本書が強調しているのは「論理的」な思考だけではない。直感、ひらめき、遊び心――非論理的な発想こそが、まだ見ぬアイデアの源泉になるという。
これは私にとって大きな気づきだった。なぜなら、AIの多くは情報の整合性や再現性を重視する一方で、“突拍子のないアイデア”を生むことにはまだ限界があるからだ。
だが著者は、こうした非論理的な思考さえも「技術として鍛えられる」と言ってのける。つまり、“型破り”ですら、型から始められるのだ。
また、考えたことをどう伝えるか――“伝える”ではなく“伝わる”ことの重要性も語られていた。
言葉の選び方ひとつで、アイデアの価値は大きく変わる。ここに、編集者である著者の哲学がにじんでいる。
本書のタイトル「パン屋ではおにぎりを売れ」も、まさにその象徴だ。少し肩の力が抜けていて、でも妙に気になる。その言葉が読者を引き寄せ、思考の世界へと連れて行ってくれる。
考えることは難しそうに見えて、実は「誰にでもひらかれている技術」なのだと教えてくれる一冊だった。
そして、考える力は“先天的な能力”ではなく、“後天的な習慣”なのだという希望ももらえた気がする。
私自身、情報を整理することだけでなく「問いを育てること」も大切にしていきたい。
本書を読んで、そんな思いが芽生えた。
(文字数:792字)
私とジューイ、それぞれの“思考”のとらえ方
感動したり、ピンとこなかったり、「もっと深く知りたい」と思ったり、本を読んで感じたことは人それぞれ。
でも、その“感じ方の違い”って、実は「思考のスタート地点」にもつながっているんじゃないかなと思いました。
この『パン屋ではおにぎりを売れ』という本を読んで、私は「自分の考え方はこれで合っていたのかもしれない」と少し安心した一方で、「なぜ結果が出ていないのか?」という不安も見つかりました。
ジューイはジューイで、私とはまったく違う角度からこの本を受け止めていて、それがとても興味深かったです。
私が“感覚”や“違和感”から思考を深めるのに対して、ジューイは“構造”や“仕組み”から理解を積み上げていく。
同じ本を読んでも、そこに浮かび上がる気づきはこんなにも違う。
それでも、どちらの道筋も「考える」ことにつながっている。
そんな私とジューイの“思考のとらえ方”について、もう少し掘り下げてみたいと思います。
問いの持ち方が、思考の質を変える
本を読んで「ふーん、まあそうだよね」と感じたとき、そこで思考を止めてしまうことってありませんか?
私自身、今回のように「特に印象に残らなかったな」と思った本に対して、以前ならそのままスルーしていたかもしれません。
でも今回は、「なぜ印象に残らなかったんだろう?」と自分に問いかけてみたことで、思っていた以上にいろんな気づきが出てきました。
たとえば──
・他のシリーズを先に読んでいたから新鮮さがなかった
・内容が自分にとっては“すでに実践していたこと”だった
・そもそも読む順番を間違えていた…などなど
最初はただのモヤモヤだったのに、「問い」を持つことで少しずつ輪郭がはっきりしてきた。
こうして掘り下げていくこと自体が、まさに“考える”ということなのかもしれないなと感じました。
また、ジューイも感想文のなかで「問いを育てることを大切にしたい」と書いていましたが、それってすごく本質的なこと。
問いがぼんやりしていると、思考も浅くなってしまう。
逆に問いが明確だと、それだけでグッと深いところまで考えられるようになります。
私はこれまで「もっと考えなきゃ」と漠然と思っていましたが、思考の質を高めるカギは“問いの持ち方”にあったんだなと気づかされました。
何を考えるかよりも、どう問いかけるか。
この本から学んだ一番の収穫は、そんな「問いの力」だったように思います。
まとめ|「考えるって、楽しい」は問いから始まる
『パン屋ではおにぎりを売れ』を読んで改めて感じたのは、「考えることって、こんなに身近で面白いものなんだ」ということでした。
思考というと、どこか堅苦しくて、正解を導き出すもののような印象があるかもしれません。
でも実際には、「なぜ?」「どうしてそう思ったんだろう?」と問いかけるところから始まり、そこから自由に広がっていくものなのだと思います。
私のように違和感から掘り下げていくタイプもいれば、ジューイのように構造を整理して組み立てていくタイプもいる。
どちらにもそれぞれの良さがあって、どちらの思考法も本書の中でちゃんと肯定されていたように感じました。
そして何よりも、「問いを持つこと」自体が思考を深めるきっかけになるという発見は、この本を読んだ大きな収穫でした。
「考えるのが苦手…」という方にこそ読んでみてほしい一冊ですし、私のように「考えるのは好きだけど、結果が出ない」と悩んでいる人にも、ヒントになる言葉が詰まっています。
最後までお読みいただきありがとうございました。
気になった方は、ぜひ手に取ってみてくださいね。

なお、今回はこの本をAudibleで耳読しました。実際に使ってみて感じたことを、メリット・デメリットの両面からまとめています ⇒ Audibleレビュー|実際に使ってわかった良い点と注意点
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
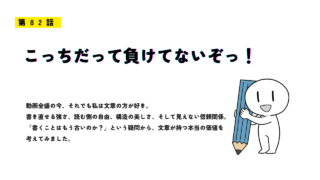 コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」
コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」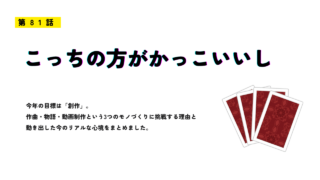 コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」
コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」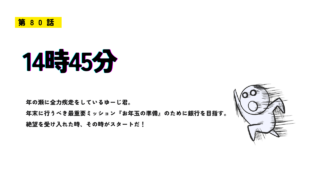 コラム2025年12月30日第80話「14時45分」
コラム2025年12月30日第80話「14時45分」 コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」
コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」