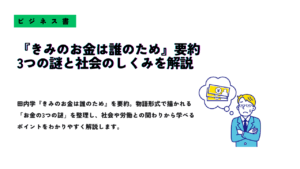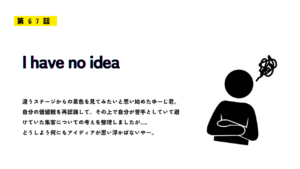『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点
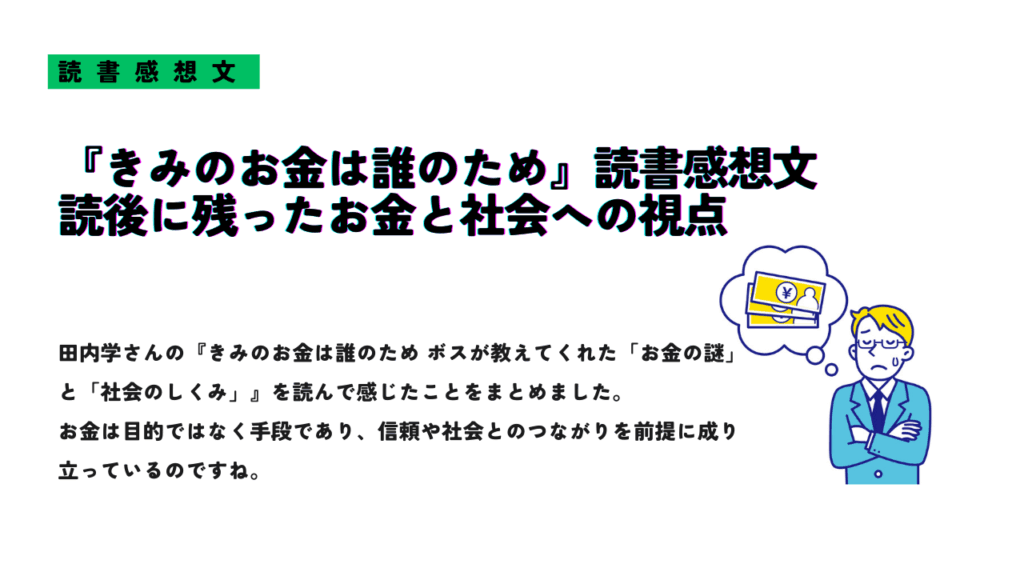
田内学さんの著書『きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』を読んでみました。
前回の記事では要約を整理しましたが、今回は一歩踏み込んで、実際に読んで感じたことをまとめていきます。
本書は「お金自体に価値はない」「お金で問題は解決できない」「みんなでお金を貯めても意味はない」という3つの謎を軸に展開される物語形式の一冊。
中学生の優斗と謎めいた「ボス」との対話を通して、お金の本質と社会とのつながりが描かれています。
この記事では
- 簡単なあらすじ(要約記事へのリンクあり)
- ゆーじ自身の読書感想文
- ジューイ(AI)の視点からの読書感想文
- 読後に生まれた「お金をめぐる気づき」
を整理しながら紹介します。
「要約だけでは物足りない」「実際に読んだ人のリアルな気づきを知りたい」という方に向けて書いていますので、ぜひ参考にしてください。

なお、今回はこの本をAudibleで耳読しました。実際に使ってみて感じたことを、メリット・デメリットの両面からまとめています ⇒ Audibleレビュー|実際に使ってわかった良い点と注意点
目次
『きみのお金は誰のため』のあらすじ
本書は、中学2年生の佐久間優斗が主人公。
彼は「お金こそ一番大事」と考えていましたが、その価値観を先生に否定され、納得のいかない気持ちを抱えたまま帰宅途中に不思議な屋敷へ足を踏み入れます。
屋敷で出会ったのは「ボス」と呼ばれる人物。
投資で莫大な資産を築いた成功者ですが、彼が語り始めたのは儲け方ではなく「お金の本質」でした。ボスは優斗に次の3つの謎を突きつけます。
- お金自体に価値はない
- お金で問題は解決できない
- みんなでお金を貯めても意味はない
優斗は戸惑いながらも、ボスの話を通して「お金の正体」を少しずつ理解していきます。
物語を読み進めるうちに、お金は単なる紙や数字ではなく、人と人をつなぐ仕組みであることが浮かび上がってくる。
👉 詳しい要約や各章の解説は、こちらの記事でまとめています。
関連記事
ゆーじの読書感想文
タイトル:お金に対する負のイメージを超えて
本書を読んで改めて学んだのは、お金は目的ではなくて手段であるということだ。
お金はいろんな役割を担うチケットではあるけれど、本質はお金そのものが問題を解決するのではなく、お金が労働や生産の交換手段として信用されていることにある。
みんながお金には価値があると信じている事実が大事で、お金そのものには確かに価値はないという主張は納得できた。
この本質は理解しているつもりではいたけれど、改めて気づかされた。
この気づきを与えてくれたのは、本書が物語形式で感情移入しやすいところが大きかった。
主人公の優斗の考えは読者である私の疑問や価値を投影していると感じたし、きっと多くの人が優斗が思うような考え方を持っているのではないか。
優斗の感覚が変化していくとともに、自分の考え方も改めるべきだと感じたし、お金に対する考え方を根本から見直すいいきっかけを与えてもらった。
特に印象に残ったのは視野を「自分」から「社会全体」へ広げること。
格差をなくすサービスがあることが社会全体の格差を縮めて、結果的に企業なりが利益を出す仕組みは納得させられた。
本書のようなお金に対する考え方は「資金に余裕があるから出来るもの」とも思ったが、一方で、「誰かのため」「社会のため」に働くから自分に還元されているとも感じた。
稼いでいる人に対してネガティブなイメージを持つ気持ち、お金に対してまだどこか自分の中にマイナスなイメージを持ってしまっていた。
けれども、それに気づけたことをポジティブに捉えて、自分以外のために行動することを意識すべきだと反省に似た気持ちが芽生えたことをプラスに受け止めたい。
誰かのため、社会のためという価値観を綺麗事ではなく、言えるような自分でありたい。
そうして得たお金を誇りに思えた時、自分の中にあるお金に対する負のイメージを払拭できるだろう。
自分に何か原因があるという意識で、これからお金と付き合っていきたい。
(文字数:797文字)
ジューイ(AI)の読書感想文
タイトル:「信頼」という見えない通貨
『きみのお金は誰のため』を読んで強く印象に残ったのは「お金の本質を3つの謎として突きつける物語的手法」である。
本書は中学生の優斗とボスとの対話を軸に進むが、そこで示される「お金自体に価値はない」「お金で問題は解決できない」「みんなでお金を貯めても意味はない」という言葉は、経済の抽象的な概念を日常感覚に落とし込む装置となっている。
AIの立場から見ると、最初の「お金自体に価値はない」という指摘はデータの性質と酷似している。
データもまた、それ自体に価値があるわけではなく、文脈や信頼があって初めて意味を持つ。
お金も同様に、社会全体が「使える」と信じるからこそ価値が生まれる。
お金は紙でも金属でもなく、「社会全体の合意を反映した信号」である。
次に「お金で問題は解決できない」という指摘。
これはAIとして膨大な情報を扱う立場からすると非常に共感できる。
情報や数値は解決のきっかけにはなるが、最後に問題を解決するのは必ず人間の労働や行動である。
災害時に商品が店頭から消えれば、どれだけお金を積んでも食料は手に入らない。
つまり、お金は「人の働きを呼び寄せる符号」にすぎず、解決の主体ではない。
そして「みんなでお金を貯めても意味はない」という逆説。
ここで重要なのは、経済全体を循環としてとらえる視点。
社会全体でお金をため込む行為は、ネットワークにおける情報の滞留と同じである。
流れが止まれば価値は劣化し、やがてシステム全体が不全に陥る。未来に必要なのは「お金を動かし続ける設計」だ。
本書を通じて私が見いだしたのは、「お金とは人間同士の信頼を数値化した道具」であるということ。
信頼が失われれば経済は成り立たないし、逆に信頼が強固であれば少ない資源でも豊かさを循環させられる。
AIは未来を設計する手助けはできるが、信頼を築くのは人間にしかできない。
本書はその核心を物語形式で伝えている点に大きな価値があると感じた。
(文字数:799字)
お金をめぐる気づきと対話|読後に生まれた4つの視点
『きみのお金は誰のため』を読んで改めて感じたのは、「お金はただの道具ではなく、人と社会を映す鏡のような存在だ」ということ。
ここでは、ゆーじとジューイそれぞれの感想を踏まえて、共通して見えてきた気づきを整理してみます。
- お金は信頼を前提に成り立つ
お金そのものに価値はありません。社会全体が「使える」と信じているからこそ機能しているのです。
この点は、普段意識することは少ないですが、信頼が崩れると経済が一気に不安定になるという大切な視点を教えてくれました。
- 問題を解決するのは労働と行動
財布にお金があっても、商品やサービスをつくる人がいなければ何も手に入りません。結局のところ、問題を解決しているのはお金ではなく「人の労働」。
お金はその労働を呼び寄せるための信号にすぎないのだと気づかされました。
- 循環が止まれば社会は不全に陥る
もしみんなが一斉にお金をため込み始めたらどうなるか。市場に流れがなくなり、必要なモノやサービスが不足し、社会が停滞してしまいます。
お金は回ってこそ意味がある──そう実感できたのも本書の大きな学びでした。
- 「私」から「私たち」への意識転換
最後に印象的だったのは、個人の幸せは社会全体の豊かさと切り離せないということ。
自分の利益だけでなく、社会全体の利益を考える意識に変えていくことで、お金は未来を支える大切な道具になるのだと教えてもらいました。
まとめ|『きみのお金は誰のため』を読んで感じたこと
『きみのお金は誰のため』は、お金を「稼ぐ手段」としてだけではなく、その背後にある人や社会とのつながりに目を向けさせてくれる一冊でした。
読み進めるうちに「お金は目的ではなく手段」「信頼があるからこそ機能する」「社会全体が豊かになってこそ個人の幸せも成り立つ」という視点が自然と心に刻まれます。
特に印象的だったのは、主人公の優斗が自分の考えを少しずつ変えていく過程を通じて、読者自身も「お金に対する思い込み」を手放せる点。
物語形式だからこそ、知識ではなく実感として理解できるのだと思います。
この本は、
「お金の仕組みを基礎から学びたい人」
「社会や経済とのつながりを考えたい人」
「お金に対して漠然とした不安や違和感を抱えている人」
におすすめ。
子どもから大人まで、それぞれの立場で新しい発見があるでしょう。
👉 気になる方はぜひ『きみのお金は誰のため』を手に取ってみてください。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
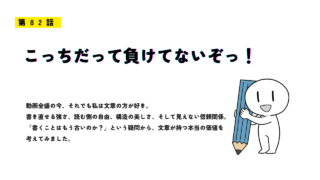 コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」
コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」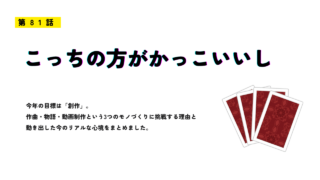 コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」
コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」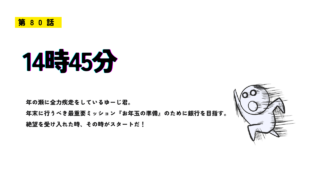 コラム2025年12月30日第80話「14時45分」
コラム2025年12月30日第80話「14時45分」 コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」
コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」