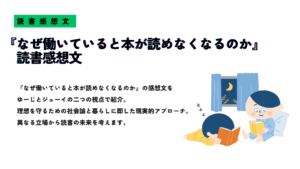『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』要約と忙しい社会人の読書術
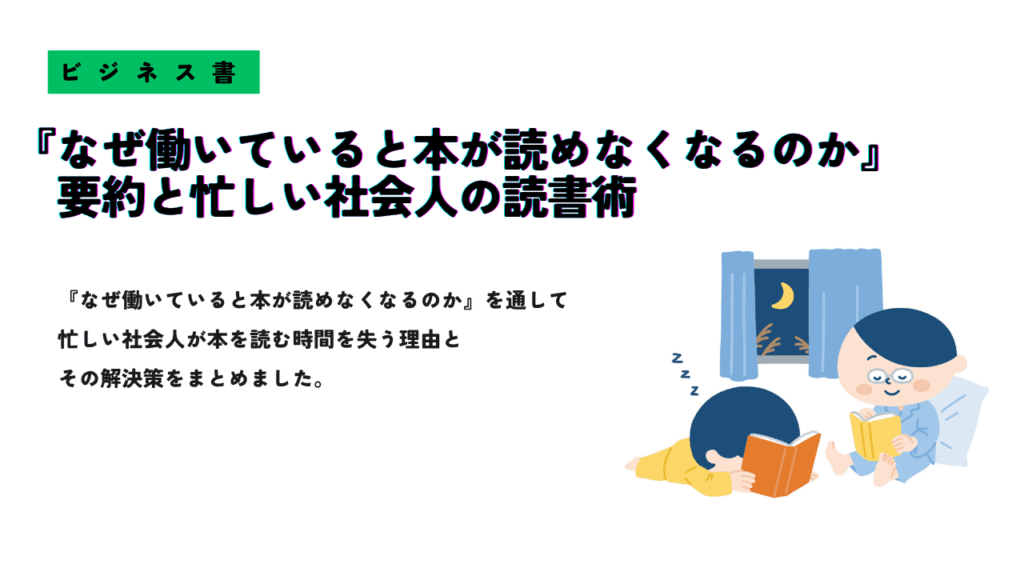
仕事終わりはスマホを眺めて終わり、気づけば積読だけが増えていく——そのモヤモヤ、放っておきますか?
この記事は、三宅香帆さんの新書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を手がかりに、「なぜ忙しいと本が読めないのか」を“根っこ”からほどきます。
単なる時短術ではなく、明治以降の労働観の変化や、“情報”と“読書(ノイズ)”の違い、「全身全霊」ではなく「半身で働く」という提案まで、背景ごとスッキリ整理。
さらに、今日からできる実践アイデア——1日10分読書、完読主義を手放す、疲れた日の“救済本”の用意——も具体例つきでまとめました。
「昔は読めたのに、今は読めない理由」を言語化しつつ、「どうすれば読める自分に戻れるか」まで一気にたどり着くガイドです。まずは本書の基本情報・狙いから、さくっと見ていきましょう。

なお、私はこの本をAudibleで耳読しました。移動中や家事の合間にも学べて相性◎です。
初めての方は、登録から使い方までをまとめたこちらの記事をご参照ください
⇒ Audible初心者向け完全ガイド
目次
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の基本情報と概要
「学生時代はあんなに読んでいたのに、社会人になってから全然読めなくなった…」——そんな経験はありませんか?
三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、この“あるある”な悩みを深掘りし、背景にある社会構造まで踏み込んで解き明かす一冊です。
本書は「時間がないから読めない」という単純な話では終わらせません。長時間労働や情報の消費スピード、SNSの存在、さらには歴史的な労働観の変化までを丁寧にたどりながら、「なぜ私たちは本を開く余裕を失ったのか?」という問いに迫ります。
加えて、読書時間を取り戻すための実践的なヒントも豊富。通勤の数分やスマホの使い方の見直しなど、日常に取り入れやすいアイデアが詰まっています。
ここからは、著者の人物像や執筆背景、扱われているテーマ、そして読者から寄せられた反響について順番に見ていきましょう。
著者はどんな人?本が生まれた背景もちらっと紹介
本書の著者・三宅香帆さんは、書評家・文筆家として活動し、現代人の読書事情や文学の魅力を幅広く発信している人物。大学院では文学研究を専攻し、その知識と視点を活かして執筆や講演を行っています。
本書が生まれた背景には、著者自身の実感があります。学生時代は日常的に本を読んでいたにもかかわらず、社会人になると読書時間が激減したという経験が出発点でした。
「なぜこうなってしまうのか?」という疑問から、歴史・社会・文化的な要因を調べ始め、その結果がこの新書に凝縮されています。
執筆にあたっては、明治から現代までの読書文化や労働観の変遷、スマホ時代の情報消費の変化など、多角的な視点を組み合わせています。
単なる自己啓発書ではなく、現代社会の構造を見つめ直す社会評論としての側面も持っているのが、本書の大きな特徴です。
どんなテーマで書かれている本なのか
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の中心テーマは「現代の労働環境と読書時間の関係性」。著者は、読書時間の減少を“個人の怠慢”として片づけるのではなく、社会全体の構造問題として捉えています。
たとえば、長時間労働や「全身全霊で働く」文化が当たり前になった現代では、心の余裕やまとまった時間が奪われやすく、本を開くことが難しくなります。
さらに、スマホやSNSによって短い情報への慣れが加速し、深い集中を必要とする読書がますます遠のいてしまうのです。
本書では、こうした問題を歴史的背景とあわせて解説。
かつては「読書=出世の鍵」だった時代から、「即戦力や実用スキル優先」へと変化してきた価値観の移り変わりも描かれています。そして最後には、「教養としての読書を取り戻すこと」が人生を豊かにする鍵だと提案します。
発売後の反響や読者の声
発売後、本書はSNSや書店レビューで多くの共感を集めました。特に「自分だけじゃなかった」という安心感や、「読書時間が減った理由が腑に落ちた」という声が目立ちます。
読者の中には、「本を読めない自分を責めていたけれど、社会の構造的な要因があると知って気持ちが楽になった」という感想や、「読書のハードルを下げる実践的なヒントが役立った」という評価も寄せられています。
書店員や書評家からも、「社会評論としても読めるし、日常に役立つ実用書としても読めるバランスが秀逸」と高評価。特に働き盛りの30〜40代を中心に支持を集め、「忙しくても読書を再開したくなる本」として話題になりました。
発売後しばらく経ってもSNSで引用や感想が流れ続けており、現代の読書文化を考えるうえで長く読まれる一冊になりつつあります。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の内容を要約
本書は、現代人が働きながら読書を続けることがなぜ難しいのかを、歴史・文化・心理の3つの視点から解き明かしています。
著者の三宅香帆さんは、明治時代から現代までのベストセラーや流行文化を手がかりに、それぞれの時代の「働き方」と「本との向き合い方」の関係をたどります。
特にバブル崩壊以降、「好きなことを仕事にする」という価値観が広がり、仕事と自分の存在意義が強く結びつくようになったことが大きな転換点とされます。この結果、仕事の成果や評価が自分の“実存”そのものを左右するというプレッシャーが強まりました。
さらに、インターネットやスマホの普及が拍車をかけます。効率的に必要な情報だけを得られる環境は、便利である一方、予期せぬ知識や偶然の出会い(=読書がもたらす“ノイズ”)を遠ざける要因にもなります。
本書は、こうした構造が私たちの思考や生活習慣を変え、気づかぬうちに「文化的な営み」から距離を置かせてしまっていることを指摘。
読書を例に、日常に文化を取り戻すためのヒントを提示しています。
仕事が終わっても気づけばスマホ…その理由
本書で指摘されているのは、「仕事モード」が終業後も頭から抜けないという現象。
現代の働き方は、自分のキャリアや評価が“実存”と直結しているため、日常の多くを「成果につながるかどうか」という視点で見てしまいがちです。
結果、帰宅後も無意識に「役立つ情報」や「効率的な解決策」を探す思考が続きます。スマホはその欲求に即座に応えてくれる便利な道具で、SNSやニュース、検索結果が必要な情報を瞬時に提示します。
しかし、そこには偶然の発見や寄り道がほとんどありません。読書のように、予想外のテーマや未知の言葉に出会い、考えを広げる余白がないのです。
この「即効性」と「効率性」が習慣化すると、脳はより手軽なスマホを優先し、じっくり時間をかける本から離れてしまいます。
昔は読書=出世のカギだった時代もあった
著者は、明治から昭和にかけての日本社会では「読書=教養の獲得」であり、出世や社会的成功への近道とみなされていたと指摘します。
当時のベストセラーや流行は、社会や国家に貢献する人物像を描き、その価値観を広めていました。
たとえば1970年代までの人々は、自分の仕事が社会全体とつながっていると感じられ、その意義を強く意識していました。読書はそのための知識や視野を広げる手段であり、努力や向上心の象徴でもあったのです。
しかし1980年代以降、関心の中心が「社会」から「自分」へと移り変わります。自己啓発や趣味に特化した読書が増える一方、「社会に役立つ知識を得るための読書」という位置づけは薄れていきました。
時代とともに、読書が果たす役割も大きく変化してきたのです。
「役に立つ本」だけを選ぶ落とし穴
現代人が本を選ぶとき、「今の仕事や生活に役立つかどうか」という基準に偏りがちです。
本書では、この傾向が読書量の減少だけでなく、思考の幅を狭める原因になっていると指摘。仕事に直結する知識は確かに有用ですが、そればかりを求めると、文化や教養、想像力を養う機会を失ってしまいます。
特にスマホやネット検索は、自分の関心や必要性に合わせた情報だけを提示するため、ますます「役立つもの」以外に触れる機会が減ります。
一方、読書は無関係に見える情報や異なる価値観に出会わせてくれます。
この“ノイズ”こそが新しい発想や視点を生む種ですが、効率や即効性を優先する習慣はそれを排除してしまうのです。
結果として、仕事の幅や人生の厚みまでもが薄れていくという警鐘が、本書には込められています。
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の要点と背景
本書は「忙しいから読めない」という単純な答えではなく、私たちが本を開く余裕を失っていく“仕組み”そのものに光を当てています。
明治以降の労働観の変化、インターネットによる情報環境の激変、そして「仕事=人生」という価値観の定着——これらが絡み合い、文化や教養に時間を割くことが難しい社会が出来上がりました。
ここからは、本書で描かれる社会構造やキーワードを整理しながら、「なぜ現代日本では本が読みにくいのか」を4つの視点から掘り下げます。きっと、自分の日常にも思い当たる場面が見つかるはずです。
現代日本では「文化」に時間を割けない働き方が主流に
本書が指摘するのは、現代日本の働き方そのものが「文化」に触れる余裕を削っているという事実。
長時間労働や休日出勤といった物理的な制約だけでなく、常に成果や効率を求められる精神的なプレッシャーが、余暇の過ごし方まで影響を及ぼします。
休みの日も「次の仕事に備える時間」となり、心身をリセットすることに追われ、本を開くゆとりは後回しになりがちです。
さらに、経済的な不安やキャリアの不透明感から、趣味や教養よりも「資格取得」や「副業」といった実利的な活動が優先される傾向も強まっています。
こうした環境では、読書のように即効性のない文化的営みはどうしても“贅沢”や“後回しにすべきもの”と位置づけられやすい。
本書は、この傾向が一時的なものではなく、社会の構造として固定化しつつある点に警鐘を鳴らしています。
「情報」と違い、読書が持つ“ノイズ”の価値
SNSや検索エンジンで得られる情報は、短時間で目的に沿った答えを提示してくれます。確かに便利ですが、それはあくまで“自分が求めた範囲内”の世界。
著者は、この効率的な情報消費の一方で、読書が持つ“ノイズ”の価値を見直すべきだと訴えます。
読書は、必要かどうかもわからない情報や、自分の価値観とは異なる意見、予期せぬテーマに出会わせてくれます。この“ノイズ”こそが、新しい発想や視点の転換を生む源泉です。
しかし、日常が効率化されるほど、この余白に触れる機会は減少します。本書は、こうしたノイズを意識的に取り入れなければ、思考の幅が狭まり、文化的な成長が停滞する危険性があると警告しています。
趣味や読書が“仕事のノイズ”になる社会構造
現代の労働環境では、趣味や読書すら「仕事の邪魔」と見なされる空気があります。
評価基準が成果や効率に直結しているため、直接的に仕事に役立たない活動は軽視されやすいのです。
結果として、自己啓発やスキルアップに関連する読書は推奨されても、小説や詩集、エッセイなど“役に立たない”本は肩身が狭くなります。
著者は、こうした社会構造が無意識のうちに私たちの行動を制限していると指摘。
文化的営みは、すぐに成果が見えないからこそ深い意味を持つのですが、「効率性」一辺倒の価値観はそれを認めません。この状態が続けば、文化は次第に「趣味人だけのもの」となり、社会全体での共有が難しくなっていきます。
「半身」で働き文化を守るという提案
本書が提案するのは、「半身」で働くという考え方。
ここでいう“半身”とは、仕事に全エネルギーを注ぎ込むのではなく、自分の時間と心の一部を常に文化的活動のために残しておく姿勢のことです。
これは決して手を抜くという意味ではありません。むしろ、働き続けるためのバランスを取る行為であり、人生全体の充実度を高める方法です。
読書や芸術、趣味に触れる時間を確保することで、仕事だけでは得られない視点や感性が養われます。結果的に、それが創造性や問題解決力を高め、仕事にも良い影響をもたらす可能性があります。
著者は、「文化を守ることは個人の贅沢ではなく、社会全体の活力を維持するための投資だ」と強調しているのですね。
忙しい社会人でも続けられる読書習慣の作り方
忙しい日々の中で読書を続けるには、「時間を作る」よりも「生活に溶け込ませる」ことがカギ。
本書は、意志の力だけに頼らず、環境やルールを工夫することで自然と本を手に取れる方法を提案しています。
ここでは、その中から特に取り入れやすい3つの習慣を紹介します。
1日10分だけ読む習慣から始める
読書を続けられない多くの理由は「まとまった時間がないから」という思い込みです。
実際には、10分でも集中すれば数ページは読めますし、その積み重ねは1か月で1冊以上に相当します。
たとえば、
- 朝のコーヒータイムに10分
- 昼休みの前半だけ
- 帰宅後、食事の前に5分+寝る前に5分
といった「生活の決まった場所・時間」に組み込むと習慣化しやすくなります。ポイントは、時間を測って“区切る”こと。
読みすぎて寝不足になったり、予定が崩れる心配がないため、翌日も継続しやすくなります。
全部読まなくてもOKという気楽さ
「最後まで読まなければならない」という完読主義は、読書を義務に変えてしまいます。
本書では、興味が持てない部分は飛ばす、必要な章だけ拾い読みする、途中でやめる勇気を持つことが推奨されています。
たとえばビジネス書なら、全章を順番に読むのではなく、今の課題に関係する章から読む。小説なら、序盤が合わなければ思い切って別の作品に移る。この「自分で選ぶ自由」があると、読書はもっと軽やかで楽しいものになります。
実際、プロの編集者や研究者も“拾い読み”や“斜め読み”を日常的に行っています。完読を手放すことで、読書のハードルは一気に下がります。
読む気力がない日の“救済本”を用意する
どんな読書家にも「今日は何も読む気がしない日」はあります。そんな時こそ、あらかじめ用意しておいた“救済本”が活躍。
救済本とは、短時間で読めて、心をやわらかくしてくれる本のこと。具体的には、
- エッセイ集や詩集(1編数分で読める)
- 写真集やアートブック(文字が少なく視覚的に楽しめる)
- 一話完結型の漫画や短編集
といったジャンルです。
大事なのは、「これなら開ける」という軽さと安心感。
たとえ数ページでも、文字や物語に触れることで“読書のリズム”を途切れさせずに済みます。こうした軽い読書の積み重ねが、いずれ本格的な読書への再スタートにつながります。
まとめ
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、忙しい現代人が読書から遠ざかってしまう理由を丁寧にひも解き、その上で本との距離を取り戻すための現実的な方法を提示してくれる一冊です。
仕事に追われ、スマホに時間を奪われる日常でも、「1日10分だけ読む」「完読にこだわらない」「救済本を用意する」といった小さな工夫なら、今日からすぐに始められます。
読書は、情報収集やスキルアップだけでなく、偶然の発見や心の余白を与えてくれる貴重な時間。
本書をきっかけに、自分なりの読書習慣を見直し、忙しい毎日の中でも“本と暮らす時間”を少しずつ取り戻してみませんか。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
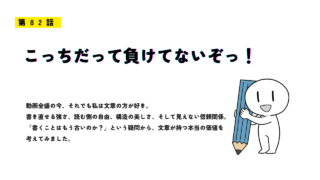 コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」
コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」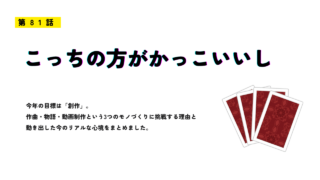 コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」
コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」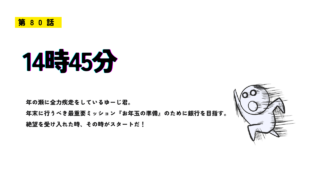 コラム2025年12月30日第80話「14時45分」
コラム2025年12月30日第80話「14時45分」 コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」
コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」