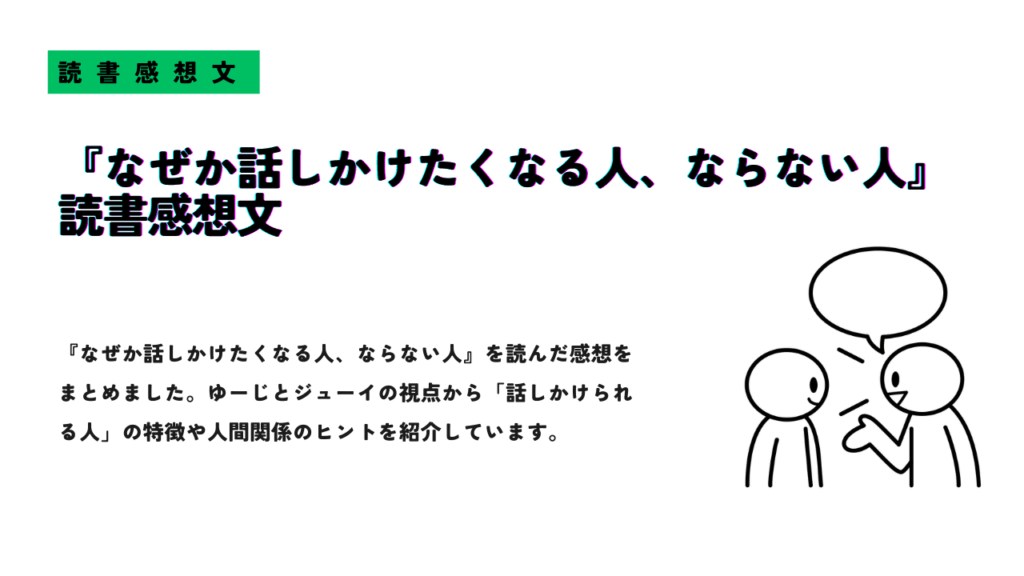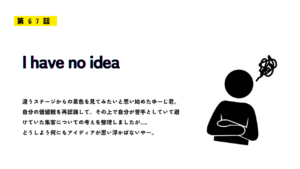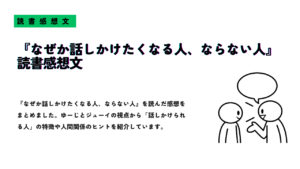【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説
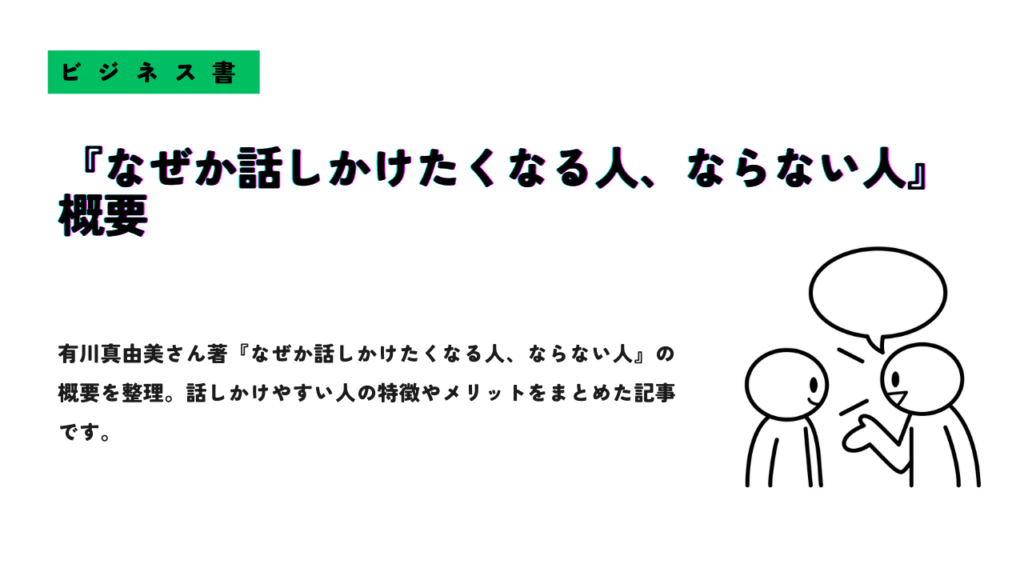
人の集まりの中で「どうしてあの人には自然と声がかかるんだろう?」と感じたことはありませんか。
自分は会話が苦手で、場にいても輪に入れず、心の中で「誰か話しかけてくれないかな」と願った経験を持つ方も少なくないでしょう。
その答えは、才能や特別なスキルではなく、実はちょっとした「表情」「言葉」「振る舞い」に隠されています。
ほんの少し意識を変えるだけで、誰でも「話しかけたくなる人」に近づくことができるのですね。
本記事では、有川真由美さんの著書『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』をもとに、話しかけたくなる人の特徴やマナー、会話を続けるための小さな工夫をわかりやすくまとめました。
初対面の場で緊張してしまう方や、会話に自信がない方にとって、今日から実践できるヒントが見つかるはずです。
次の章では、「話しかけたくなる人」に共通する具体的な特徴を紹介していきます。
目次
「話しかけたくなる人」に共通する特徴とは
人が誰かに声をかけるかどうかは、特別な才能や派手なキャラクターによって決まるわけではありません。
実際は、日常のちょっとした言葉遣いや表情、態度が大きなカギになっています。
ここでは「話しかけたくなる人」に共通する3つの特徴を見ていきましょう。
穏やかで肯定的な言葉を使う人は安心感を与える
人は本能的に「安全な相手」に近づきたいと思います。
どんなに優秀でも、言葉がきつかったり、否定的な反応ばかりを返す人には声をかけづらいもの。反対に「そうなんですね」「いいですね」「たしかにそう思います」といった肯定的なフレーズを多く使う人には、自然と安心感が生まれます。
著者の有川真由美さんも、特別なスキルより「穏やかさ」が重要だと強調しています。
穏やかな人は「この人なら自分を受け入れてくれる」という印象を与え、結果として話しかけやすい存在になるのです。

会話が苦手だと感じる人こそ、まずは肯定的な言葉をひとつ増やすところから始めるのがおすすめです。
微笑みや視線など、ちょっとした表情の力
表情は相手に与える印象を決定づける要素。
特に「なんとなくの微笑み」は、相手に親しみや明るさを感じさせる大きな武器になります。常に笑顔を作る必要はありませんが、口角を少し上げ、目尻を和らげるだけでも印象は変わります。
さらに、視線の使い方も重要。
相手の目を見るのが苦手なら、鼻や顔全体を意識して見るだけでも「きちんと向き合ってくれている」と伝わります。
こうした表情や視線の小さな工夫は、言葉以上に「話しかけても大丈夫そう」という安心感を相手に与え、会話の入口を開いてくれるのです。
欠点やユーモアが「隙」となり親しみを生む
意外なことに「完璧な人」ほど、周囲から話しかけられにくいといわれます。
隙がなく、近寄りがたい印象を与えてしまうからです。反対に、自分の欠点を笑い飛ばせる人や、ちょっとしたユーモアを交えて会話できる人は、相手に「入り込む余地」を与えます。
もちろん深刻なコンプレックスをさらけ出す必要はありません。
たとえば「方向音痴なんです」「昨日うっかり傘を忘れちゃって」など、軽い失敗を笑い話に変えられると、相手は安心し、自然と会話の糸口を見つけられます。
欠点を隠すよりも親しみやすさに変えるほうが、人から話しかけられるきっかけをつくるのですね。
会話を続けるための小さな工夫
「話しかけたくなる人」と思われるためには、会話を始めるだけでなく、その後を自然につなげることが大切。
相手が話しやすい雰囲気をつくる小さな工夫を身につけておくと、初対面でも気まずさが減り、会話が途切れにくくなります。
ここでは代表的な3つのポイントを紹介します。
声かけには“一言”でなく“二言”で返す
会話が続かない人に共通するのは、返事が短すぎる点。
「はい」「そうですね」で終わってしまうと、相手はそれ以上話題を広げられず沈黙が訪れます。そこで役立つのが「二言で返す」という工夫。
たとえば「今日はいい天気ですね」と声をかけられたら、「本当に気持ちがいい天気ですね。散歩したくなりますね」と付け加えるだけで会話は広がります。
大げさな内容でなくても構いません。相手の言葉にひとつ自分の気持ちや感想を重ねることで、キャッチボールが成立し、「この人とは話しやすい」と思ってもらえるのです。
感情を添えた返答で心を開く
会話を続けるためには、事実だけを返すのではなく「感情」を含めることが大切。
たとえば「旅行に行ってきたんです」と言われたとき、「そうなんですね」だけでは無関心に見えますが、「いいですね!どこに行かれたんですか?」と感情を示すと相手は安心して話を広げられます。
人は理屈よりも感情に共鳴したときに心を開きます。驚き、共感、喜びなどのリアクションを少し大きめに表現するだけでも効果的。
感情の方向性を共有できると、会話が「事実の交換」ではなく「心の交流」へと変わり、自然と深いコミュニケーションにつながっていきます。
前の会話を覚えている人は「聞いている人」
「この人とは話しやすい」と感じさせるもう一つの秘訣は、以前の会話を覚えていること。
「この前おっしゃっていた資格の勉強、進んでいますか?」といった一言は、相手に「ちゃんと自分を見てくれている」と伝わります。
これは単なる記憶力ではなく、「その場でしっかり聞いていたかどうか」の表れ。前の話を覚えている人とは、自然と話題を続けやすくなり、会話がシリーズ化していきます。
逆に、毎回「それ、聞きましたっけ?」となる人は、無意識に信頼を失ってしまうことも。

小さな会話の積み重ねを覚えておくことが、話しかけられる人の大きな強みになるのです。
「話しかけたくなる人」のマナー習慣
会話のスキルや表情の工夫に加えて、日常的なマナーの積み重ねも「話しかけたくなる人」を形づくります。
マナーといっても堅苦しい礼儀作法ではなく、「相手を心地よくさせる小さな心配り」が中心。
ここでは、特に効果的な3つの習慣を紹介します。
否定せず、相手を主役にする会話姿勢
人は「自分を受け入れてくれる人」に心を開きます。
そのため、相手の言葉を頭ごなしに否定せず、まずは一度受け止めることが大切。「でも」「違うよ」と反射的に返してしまうと、相手は萎縮してしまい、次から話しかけにくくなります。
代わりに「そうなんですね」「たしかにそういう見方もありますね」と肯定をベースに返すと、安心感が生まれます。
さらに、会話の主役を自分ではなく相手に置き、質問を重ねて相手の話を深める姿勢を持つと「もっと話したい」と感じてもらえるのです。
さりげない気配りやフォローが信頼をつくる
「話しかけたくなる人」は、相手が困っているときに自然と手を差し伸べられる人でもあります。
大げさな助けではなく、たとえば落としたハンカチをさっと拾って渡す、忙しい相手に「手伝いましょうか」と声をかけるといったさりげない行動で十分。
こうした小さなフォローは相手の心に残り、「この人に話しかければ安心できる」という印象につながります。
気配りは言葉以上に信頼感を高め、日常の会話のきっかけにもなるのです。
名前を呼ぶ挨拶と短い雑談の積み重ね
人にとって、自分の名前を呼ばれることは特別な意味を持ちます。
「おはようございます、〇〇さん」と名前を添えるだけで、自分が認識されているという安心感が生まれ、好意的な印象が強まります。
さらに、ちょっとした雑談も重要。天気や最近の出来事など軽い話題で構わないので、日常的に声を交わすことで関係が深まります。

内容よりも「声をかけられた」という体験そのものが、相手にとって心地よいものとなり、次の会話へのハードルを下げてくれるのです。
逆に「話しかけたくない人」になってしまうサイン
「話しかけたくなる人」の特徴がある一方で、知らず知らずのうちに「話しかけにくい人」になってしまうケースも少なくありません。
本人に悪気がなくても、雰囲気や口グセによって相手を遠ざけてしまうことがあります。
ここでは避けるべき代表的なサインを見ていきましょう。
無表情や不機嫌そうな態度が放つ「近寄るな」オーラ
会話が生まれる前に、第一印象でブレーキをかけてしまうのが「無表情」や「不機嫌そうな顔」。
特に自分では普通にしているつもりでも、口角が下がっている、眉間にシワが寄っていると「怒っているのかな?」と誤解されてしまいます。
相手は安心よりも緊張を感じ、「今声をかけると迷惑かも」と距離を取るのです。
実際に「表情が硬い」と言われたことがある人は、意識的に口角を少し上げたり、柔らかな視線を心がけると印象が大きく変わります。
不快に聞こえる相槌・口グセの落とし穴
会話中の何気ない相槌や口グセが、相手を不快にさせることがあります。
例えば「はいはい」「なるほどですね」「マジ?」といった言葉は、場合によっては適当さや上から目線を感じさせます。
本人に悪意がなくても、相手が「軽んじられている」と受け取れば、次から話しかけにくくなる。大切なのは、自分が普段どんな言葉で相槌を打っているのかを客観的に意識すること。
少し丁寧に「そうなんですね」「なるほど、勉強になります」と言い換えるだけで印象は大きく変わります。
自分から話しかけない姿勢が生む孤立感
「話しかけてもらえない」と感じる人ほど、自分からも相手に声をかけていないケースが多く見られます。
常にスマホを見ていたり、イヤホンをしていたり、周囲と遮断する姿勢は「話しかけないで」というメッセージとして伝わってしまいます。
もちろん無理に会話を広げる必要はありませんが、軽い挨拶や一言の声かけを積み重ねるだけで周囲の印象は変わる。
「自分から話しかける人は、話しかけられる人にもなる」という好循環を意識することが大切です。
人との絆を深め、好循環をつくるために
「話しかけたくなる人」であることは、単に会話を増やすだけでなく、その後の人間関係を豊かに育てる基盤になります。
人との絆は一度で築けるものではなく、小さなやり取りの積み重ねが信頼を生み、やがて好循環をつくり出します。
ここでは、そのための具体的なポイントを整理します。
「相談」で関係が深まる心理効果
相手との距離を縮めたいときには「お願い」よりも「相談」という形に変えてみるのが効果的。
「お願い」は一方的に頼む行為ですが、「相談」は相手を味方に引き入れ、一緒に考えてもらう関係を生み出します。
たとえば「これをやってください」ではなく「こういうことで困っているのですが、どうしたらいいと思いますか?」と投げかけることで、相手の心理に「守ってあげたい」という親近感が芽生えます。

小さな相談の積み重ねは、信頼関係を深めるための大切なきっかけになるのです。
得意分野や小さな変化が会話のきっかけになる
「話しかけやすい人」には、会話の糸口を生み出す工夫があります。
そのひとつが自分の得意分野を持つこと。仕事や趣味の中で「この人に聞けば分かる」と思われると、自然と声をかけられる機会が増えます。
また、髪型や小物を少し変えるといった日常の小さな変化も、相手が話しかけるきっかけに。同時に、自分が相手の変化に気づいて声をかけることも重要です。
お互いに「気づき合う」ことが会話を育て、絆を深める原動力になるのです。
話しかけられる人ほど、出会いやチャンスに恵まれる
「話しかけたくなる人」であることの最大のメリットは、出会いの数が圧倒的に増える点にあります。
人は声をかけやすい人に情報や縁を運び込むもの。その結果、思いがけない仕事のチャンスや人脈が広がり、人生が大きく好転する可能性があります。
さらに、会話を通じて誤解が減り、信頼感が高まり、自己肯定感も自然に育ちます。
つまり「話しかけられる人」であることは、日々の人間関係をスムーズにするだけでなく、長期的に自分の成長や幸福にもつながる大きな財産になるのです。
関連記事
まとめ
『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』の概要を整理してみると、特別なスキルや才能が必要なのではなく、日常のちょっとした言葉や表情、態度の積み重ねこそが「話しかけやすさ」を生むことがわかります。
穏やかで肯定的な言葉を使うこと、微笑みや視線で安心感を与えること、そして欠点やユーモアを隠さずに親しみやすさへと変えること。これらは誰にでも意識すればできるシンプルな習慣。
さらに、会話を「二言」で返す、感情を添える、前の会話を覚えておくといった小さな工夫によって、関係は自然と深まっていきます。
一方で、無表情や否定的な口グセなどは相手に「近寄らないで」という印象を与え、会話の芽を摘んでしまう。
逆に「相談する」「相手の変化に気づく」といった姿勢は、相手の心を開き、信頼を積み重ねるきっかけになります。
「話しかけたくなる人」であることは、ただ会話が増えるだけでなく、良縁や新しいチャンスを呼び込み、自分自身の人生を豊かにする力を持っています。
ほんの少し意識を変えるだけで、あなたの周囲に広がる人間関係も大きく変わっていくはずです。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
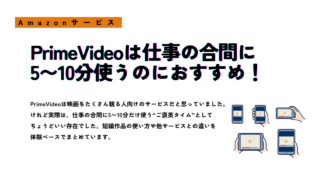 思考と行動2026年2月23日PrimeVideoは映画好き向けではなかった|仕事の合間に5〜10分使った体験談
思考と行動2026年2月23日PrimeVideoは映画好き向けではなかった|仕事の合間に5〜10分使った体験談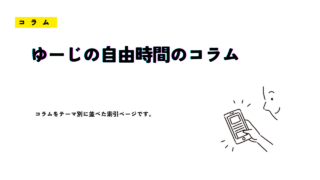 コラム2026年2月16日『コラム』-テーマ別索引ページ
コラム2026年2月16日『コラム』-テーマ別索引ページ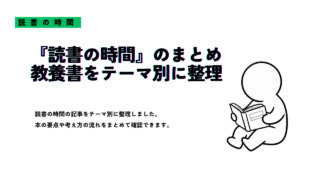 教養書2026年2月15日『読書の時間』記事のまとめ
教養書2026年2月15日『読書の時間』記事のまとめ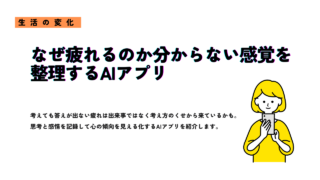 生活の変化2026年2月12日なぜ疲れるのか分からない感覚を整理するAIアプリ
生活の変化2026年2月12日なぜ疲れるのか分からない感覚を整理するAIアプリ