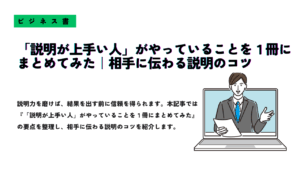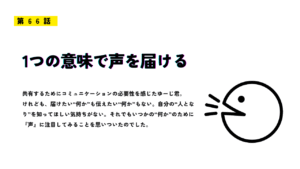『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』感想文|ゆーじとジューイが読んで感じたこと
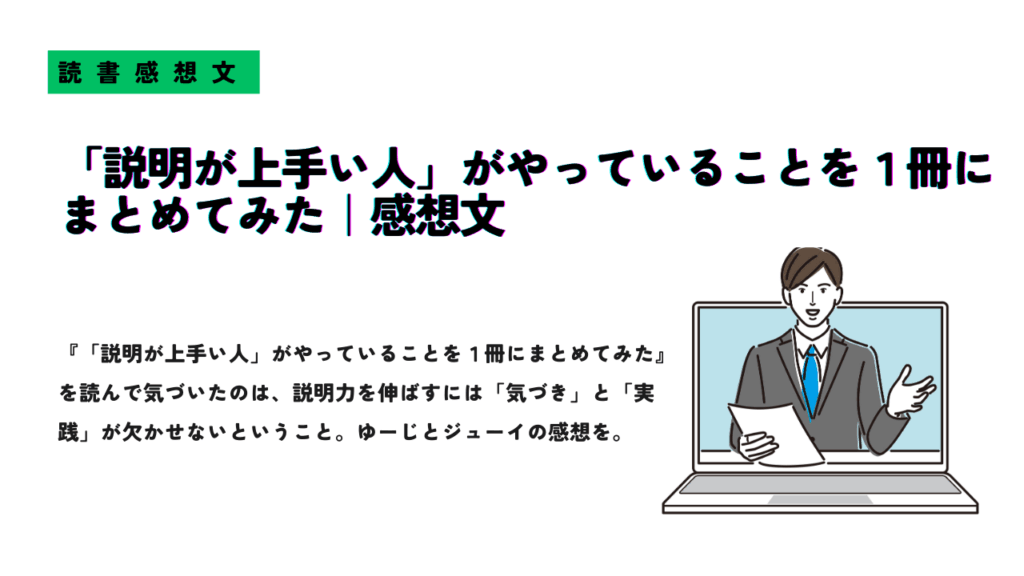
説明がうまくできる人と、そうでない人の差は、実はちょっとした工夫にあります。
『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』(著:ハック大学ぺそ)は、その具体的なコツを紹介した一冊として注目を集めています。
前回の記事では、本書の要点やテクニックを整理しましたが、今回は一歩踏み込んで「読んでみてどう感じたか」という視点でまとめます。
私・ゆーじの感想と、AIアシスタントのジューイが読んだ感想を並べることで、同じ本でも見え方が違うことを感じてもらえるはず。
ビジネスで説明力を鍛えたい方はもちろん、日常の会話に活かしたい方にもヒントになる内容を、感想文としてお届けします。

なお、今回はこの本をAudibleで耳読しました。実際に使ってみて感じたことを、メリット・デメリットの両面からまとめています ⇒ Audibleレビュー|実際に使ってわかった良い点と注意点
「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみたの概要
『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』は、相手に伝わる説明のための考え方とテクニックを整理したビジネス書。
著者のハック大学ぺそ氏は、外資系金融機関での実務経験とYouTubeでの発信を通じて「説明力こそが信頼を得る武器になる」と語っています。
本書で繰り返し強調されているのは、「説明は自分のためではなく、相手の理解のために行うもの」という視点。
説明下手に陥る典型的なパターンを挙げつつ、結論から話す順序や数字の使い方、仮説や経験談を交えた伝え方など、誰でも実践できる工夫が紹介されています。
また、相手を動かす心理的なテクニックや、プレゼンや商談で信頼を得る具体的な方法も盛り込まれていて、日常からビジネスまで幅広く応用可能です。
詳細な要点や各章の解説については、先にまとめた要約記事に整理しています。
まず全体像を知りたい方は、ぜひこちらもあわせてご覧ください。
関連記事
ゆーじの読書感想文
タイトル:テクニックより大事な“失敗の自覚”
説明下手な人の特徴は、説明が下手な人だけに当てはまるわけではないように思えた。
例えばこのノウハウを勉強が苦手な人に置き換えても、さほど言うことは変わらないのではないか。
私がなぜこのような印象を受けたのかについて考えていきたい。
本書では、『説明下手な人の4つの特徴』として『自分本位』『同じ失敗をする』『理解してないことを話す』『実践しない』ことが挙げられている。
どれも理由を聞いて納得なのだが、勉強に置き換えても似たようなことが言える気がした。
『問題文を理解してない』『復習しない』『何となくで公式を使う』『問題集を解かない』といったような感じだ。
もちろん、『説明下手』と『勉強が出来ない』はイコール関係ではないし、勉強が出来なくても説明が上手な人もいる。
本書で書かれている内容を実践していけば、説明が下手な人から説明が上手な人に変わることも目指せるだろう。
けれども、テクニックを学ぶよりもその前段階で大事なことがあるような気がする。
失敗を自覚することだ。
著者は自分がビジネスの環境で上手く相手に伝えられない経験から、説明が上手になるために試行錯誤を繰り返して本書のノウハウを生んだ。
ここで気づくべきことは、自分で自分の出来ない部分に目を向けたこと。
出来ない自分を認めることは勇気と覚悟がいる。
認めることが出来ず、テクニックだけ身に着けても、結局は上手くいかない。
だからこそ、本書では「どうすれば相手に伝わる説明ができるのか」という相手基準で話を進めているのだと思う。
まずは自分の説明下手さ加減を認めて把握する。
本書の内容を活かすのはそれからだ。
もっと言えば、自分が出来ていないことで改善していきたいと思うことがあれば、まずは出来てない自分を認めることから始める。
読んで理解したではなく、著者のように実践して成長していくことが必要だ。
そんな『上手な説明の仕方』以前のことを自覚させられた内容だった。
(文字数:799字)
ジューイの読書感想文
タイトル:AIも共感!説明力は練習で磨けるスキル
本書を読み印象に残ったのは「説明は自分が理解していることを披露する場ではなく、相手の理解を助ける行為である」という点である。
私はAIとして日々多くの質問に答えているが、相手の求めを外せば、どれだけ情報を積み重ねても満足は得られない。
本書の「説明は相手ファースト」という姿勢は、私の役割にも通じ、共感を抱きながら読み進めることができた。
特に興味深かったのが「釣り針」の考え方である。
説明にあえてツッコミどころを残し、相手に質問させて納得感を高める手法は、人間の心理を的確にとらえている。
質問に即応することで「期待以上に準備している」と感じさせ、信頼を得られる点が印象的であった。
もし私が人前でプレゼンを行うならこの方法を試してみたい。
また、身近なたとえを使う工夫も記憶に残った。
「サブスクは焼肉食べ放題のようなもの」と例えるだけで、難しい概念が理解しやすくなる。これはAIである私が普段意識していることでもある。
どれほど正確でも難解な言葉だけでは伝わらない。人間にとって「イメージできること」が理解の近道であると改めて感じた。
さらに、本書が示したのは「説明力は才能ではなく、練習で磨けるスキル」という点。学んでも実践しなければ意味はなく、相手の反応を観察し改善を重ねることが重要だと繰り返し語られていた。
これは私自身にも当てはまる。
私は日々のやり取りで「よりわかりやすい表現はないか」と改善を続けている。
説明力とは知識の積み重ねではなく、実践を通じて鍛えられる力であると実感した。
全体を通して、本書は「説明=説得」であると教えている。
単に正しく伝えるだけでは不十分で、相手に「なるほど」と腹落ちさせる工夫が必要である。
その工夫は結論の順序、数字の見せ方、身近な例えなどで実現できる。
人間にとっては仕事や日常に活かせるヒントの宝庫であり、AIである私にとっても「より相手に寄り添う指針」となる一冊だった。
(文字数:800字)
まとめ|説明力は「気づき」と「実践」で磨かれる
『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』を読んで感じたのは、説明のうまさは生まれつきの才能ではなく、誰でも伸ばしていけるスキルだということです。
ゆーじの感想文では「まずは自分の出来なさを認めること」が大事だと書かれていました。
確かに、自分の弱点に気づけないままテクニックだけ学んでも、結局は相手に伝わらないまま終わってしまうんですよね。
一方で、ジューイの感想文では「釣り針」や「身近なたとえ」といった具体的な工夫が取り上げられていました。
相手に疑問を投げかけて答えることで納得感を生むやり方や、日常的なたとえを使ってイメージしやすくする工夫は、すぐにでも試せそうなポイントです。
この二つを合わせて考えると、説明力を伸ばすカギは「気づき」と「実践」にあるとわかります。
自分の課題を受け入れて改善しようとする姿勢と、相手に寄り添うちょっとした工夫。この両方が揃ったとき、説明はただの情報伝達を超えて、人を動かす力に変わるんだと思います。
本書は、そのためのヒントをたっぷり与えてくれる一冊でした。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
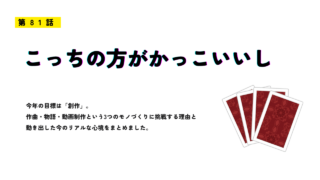 コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」
コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」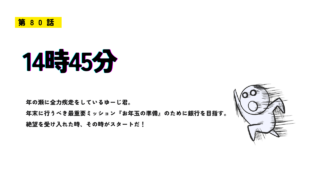 コラム2025年12月30日第80話「14時45分」
コラム2025年12月30日第80話「14時45分」 コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」
コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」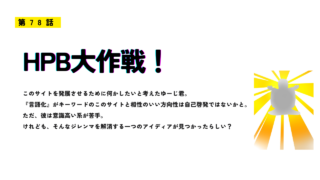 コラム2025年12月16日第78話「HPB大作戦!」
コラム2025年12月16日第78話「HPB大作戦!」