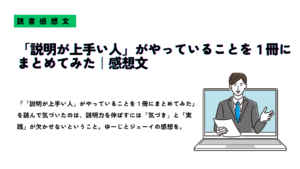【要約】「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた|相手に伝わる説明のコツ
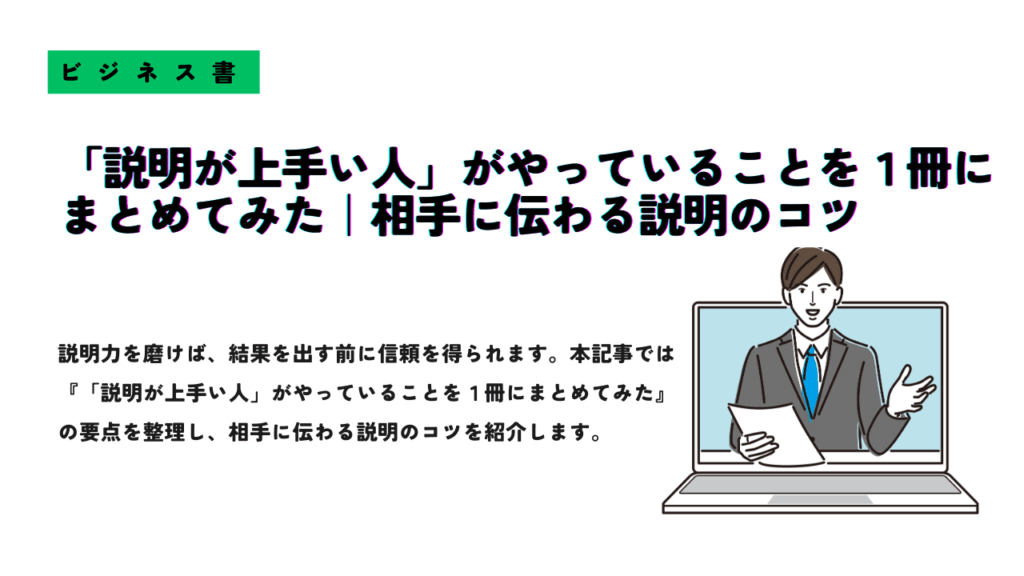
「説明が上手い人」と「説明が下手な人」の違いはどこにあるのでしょうか。
結果を出す前に周囲の信頼を得られる人は、実は“説明力”を武器にしています。
今回ご紹介する『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』(著:ハック大学ぺそ)は、外資系金融機関での経験とYouTubeで培った知見をもとに、相手に伝わる説明の具体的なテクニックをまとめた一冊。
本書では「相手ファースト」の姿勢を軸に、説明下手に陥りやすいパターンの分析から、短く伝える工夫、相手を納得させる方法、さらにプレゼンや商談で活かせる実践的なテクニックまで幅広く解説されています。
単なる話し方の指南書ではなく、相手に「理解してもらう」ことを徹底的に意識した内容が特徴です。
この記事では、本書の要点を整理しながら、「結局何が言いたいの?」と悩まなくて済む説明のコツや、相手を動かす工夫を段階的にご紹介します。
ビジネスはもちろん、日常の会話や人間関係にも応用できるエッセンスを一緒に見ていきましょう。

なお、私はこの本をAudibleで耳読しました。移動中や家事の合間にも学べて相性◎です。
初めての方は、登録から使い方までをまとめたこちらの記事をご参照ください
⇒ Audible初心者向け完全ガイド
目次
本書の概要と著者について
本書『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』は、2022年にアスコムから出版されたビジネス書。
タイトルの通り、「どうすれば相手に伝わる説明ができるのか」という疑問に真正面から応える内容で、説明下手に悩む人からプレゼンや会議の場で成果を出したい人まで幅広く役立つ実践的なエッセンスがまとめられています。
特徴的なのは「説明は自分のためではなく、相手の理解のために行うもの」という姿勢が一貫している点です。
論理やデータを重視するだけではなく、相手の関心や状況に合わせてどう伝えるかを考えることで、相手に納得感を与えられる。
そのための思考法やテクニックが段階的に整理されています。
ビジネスの場だけでなく、家庭や友人との会話にも応用できるのも魅力で、説明を通じて人間関係そのものを円滑にするヒントが詰まった一冊です。
著者「ハック大学ぺそ」とは?
著者のぺそ氏は、YouTubeチャンネル「ハック大学」の運営者として知られ、登録者数は25万人を超えています。
動画ではキャリア戦略や仕事術をテーマに、誰もが実践できる具体的なノウハウをわかりやすく発信していて、その中でも「説明の仕方」に関するコンテンツは特に人気を集めています。
興味深いのは、彼が専業YouTuberではなく、外資系金融機関に勤める現役のビジネスパーソンであること。
年収2000万円規模の職場で日々成果を求められる環境にあり、その中で「説明力」がいかに評価や信頼に直結するかを肌で感じてきたといいます。
本書は、そうした実体験から得られた知見を整理し、多くの人が真似できる形で提示したものだと言えるでしょう。
本書の出版背景と特徴
本書が生まれた背景には、著者自身の「説明下手からの脱却」があります。
外資系の厳しいビジネス環境で、上司や顧客にうまく伝えられず苦しんだ経験から、説明上手な人を観察し、自らの工夫を積み重ねてきたのです。
その過程で気づいたのは、従来の「理路整然と論理で伝える」だけでは限界があるということ。
相手の理解を第一に置き、時には比喩や具体例を交え、数字や仮説を駆使して「なるほど」と思わせる説明が有効だと学びました。
本書ではその気づきを体系化し、「説明下手の典型パターン」から「相手を動かす工夫」まで段階的に整理。
さらに、プレゼンや商談に活かせる実践的なテンプレートも紹介されています。
単なる話し方指南ではなく、実務に直結するスキルブックとして構成されているのが大きな特徴です。
説明下手にありがちな4つの特徴
説明が苦手な人には共通するパターンがあります。
本書では「なぜ説明が伝わらないのか」を明確に分析し、4つの典型的な特徴を挙げています。
単なる「話し方の癖」ではなく、考え方や準備不足が原因となっている点がポイント。
自分自身を振り返ることで「なぜ相手に理解してもらえないのか」が見えてくるので、この章は最初のチェックリストとして読むと効果的です。
「相手が聞きたいこと」を無視してしまう
説明がうまくいかない最大の理由は、自分本位で話してしまうこと。
多くの人は「自分が伝えたいこと」ばかりを並べがちですが、相手は必ずしもそれを求めていません。
相手の立場や目的を理解し、「どんな情報を知りたいのか」を意識するだけで、説明の精度は大きく変わります。
これは「説明は自分のためではなく相手のために行う」という本書の核となる考え方です。
同じ失敗を繰り返して攻略法を考えない
会議や報告の場で、毎回同じ人から指摘されるのに、改善の工夫をしない人がいます。
これは準備不足ではなく、相手への「攻略法」を考えていないことが原因。
相手の性格や判断基準をリサーチし、どのような伝え方を好むのかを分析することが大切です。
説明は一方通行ではなく、相手に合わせて戦略を変える柔軟さが求められるのです。
自分が理解していないことを話してしまう
自分の中で十分に理解できていないことを、そのまま人に説明すると混乱を招きます。
上司に意見を求められても答えられないのは「考えていないから言葉にならない」ケースが多いのです。
まずは自分の頭の中で情報を整理し、要点をつかんでから話すことが、わかりやすさの第一歩になります。
学んでも実践しない
説明に関する本や動画で知識を得ても、それを実際の場面で試さなければ身につきません。
テクニックを“知っているだけ”の状態では、いざというときに活かせないからです。
小さな場面でもいいので、学んだことを繰り返し使うことで、自分なりの説明スタイルが磨かれていきます。
説明力は訓練によって初めて成長するスキルだと本書は強調していました。
「結局、何が言いたいの?」と言われなくなる方法
説明が長くなったり要点が伝わらなかったりすると、相手から「で、結局何が言いたいの?」と突っ込まれてしまいます。
本書では、この問題を解消するための具体的な方法が提示されています。
その鍵は「論理の順序」「数字やデータ」「仮説や経験談」の三つを組み合わせること。
これらを意識することで、聞き手はスムーズに話を理解でき、納得感を持って受け止められるようになります。
単なる情報の羅列ではなく、相手がストレスなく結論にたどり着ける説明を設計することが重要です。
結論から話す4ステップ
わかりやすい説明には必ず“順序”があります。
本書では、まず結論を提示し、次に根拠、具体例、最後にまとめを添える「4ステップ」が推奨されています。
冒頭で結論を明示することで、聞き手は安心して説明を追えるのです。
途中で情報が増えても「最初に言っていた結論にどうつながるのか」という軸を持って聞けるため、理解が格段に早まります。
数字やデータを使う重要性
説明を説得力あるものにするには、感覚的な言葉よりも数値を使うことが効果的。
「多い」や「少ない」といった曖昧な表現よりも、「前年比20%増」「1時間あたり30件」といった具体的な数字を提示することで、相手は判断しやすくなります。
もし十分なデータがない場合でも、仮の数値を置いて考える「仮説思考」を使えば、筋道を立てた説明が可能になります。
仮説や経験談を交えた伝え方
新しい提案や前例のない案件では、完璧なデータが揃わないことも多いでしょう。
そのようなときに有効なのが「仮説」と「経験談」を組み合わせた説明。
自分の過去の事例や他人の成功体験を例に挙げることで、聞き手は「なるほど、そういう可能性もあるのか」と納得しやすくなります。
特に経験談は数字よりも感情に訴える力が強く、相手の共感を得やすいのが特徴です。
説明を分かりやすくするメソッド
「話が長い」「要点が見えにくい」と言われる人の多くは、説明の組み立て方に課題があります。
本書では、相手が理解しやすい説明を行うための具体的なメソッドを提示しています。
特に重要なのは、抽象と具体の行き来、時間の制約を意識した伝え方、そして感情的にならない工夫の3点。
これらを意識することで、冗長さを避け、相手の集中力を保ちながら必要な情報を届けられるようになります。
「抽象から具体」への流れを意識する
説明がわかりにくいと感じさせる要因のひとつは、具体的な事例から入って迷子になってしまうパターン。
本書では、まず抽象的な大枠を提示し、そのあとに具体的な情報を加える流れを推奨しています。
たとえば「市場全体で需要が増えている」という抽象的な枠組みを示したうえで、「実際に当社の商品も前年比20%伸びている」という具体例を続けると、聞き手は安心して情報を受け止められます。
1分以内で話す習慣をつける
ダラダラと説明を続けると、相手の集中は途切れてしまいます。
そのため「1分以内で要点を伝える」ことを意識するのが効果的。
本書では、最初に短くまとめてから、必要であれば補足を加える方法を紹介しています。
相手に「もっと詳しく知りたい」と思わせる余地を残すことで、対話のリズムも良くなり、自然にキャッチボールが生まれるのです。
感情的な説明を避けるポイント
説明の場で感情的になると、論点がぶれたり相手が防御的になったりします。
本書では「感情は熱意に使い、論理は冷静に伝える」ことを勧めています。
たとえば、不満を強調するのではなく「改善のためにこの提案をしたい」と前向きに表現することで、相手の受け止め方は大きく変わる。
説明において感情を適切にコントロールすることは、理解と信頼を得るために欠かせないポイントです。
相手を納得させるための工夫
説明は「伝える」だけでは不十分で、相手に「納得してもらう」ことが最終的なゴール。
いくら論理的に整った説明をしても、相手が腹落ちしなければ行動にはつながりません。
本書では、納得感を生むために重要なのは「相手の立場に寄り添う工夫」だと説かれています。
そのための具体的な方法として、相手のレベルや期待値を把握すること、身近なたとえ話を使うこと、そして目的を先に伝えることが紹介。
これらを意識することで、説明は単なる情報共有から「相手を動かす力」へと進化します。
相手のレベルや期待値に合わせる
専門用語や業界知識を前提にした説明は、相手がその分野に詳しくなければかえって混乱を招きます。
本書では「中学生でも理解できる言葉で話す」ことを基本とし、相手の理解度や期待値に応じて説明を調整することを勧めています。
上司であれば意思決定に必要な要素、同僚なら実務に直結するポイントなど、相手が知りたいことに焦点を合わせることで納得感が高まります。
たとえ話は身近なものを使う
難しい概念や新しいサービスを説明するときには、抽象的な説明だけでは伝わりにくいことがあります。
そこで有効なのが、身近なたとえ話。
本書では「半径3メートル以内のもの」を例に挙げると理解されやすいと解説しています。
たとえば「サブスクは焼肉の食べ放題のようなもの」と例えると、相手の頭に具体的なイメージが浮かびやすく、記憶にも残りやすいのです。
目的を先に伝えて考えを引き出す
部下や同僚に指示を出す際に「何をしてほしいか」だけを伝えると、その範囲内でしか動いてもらえません。
しかし「なぜそれをするのか」という目的を先に伝えることで、相手は自分なりに工夫を考えるようになります。
本書では、相手の潜在的な知識やアイデアを引き出すために、手順よりも目的を重視して説明することを強調。
結果として、相手の納得感が増し、主体的な行動につながるのです。
相手を動かすためのテクニック
説明の目的は、単に理解してもらうことにとどまりません。
最終的には相手に「動いてもらうこと」が重要です。
本書ではそのための工夫として、共感を得て心を開かせる導入、相手の興味を刺激する仕掛け、さらに説明の展開に変化をつける工夫を紹介しています。
これらを使うことで、説明は単なる情報伝達ではなく「行動を促す説得力」へと変わります。
心理的な要素を意識的に取り入れることが、相手の納得と行動を引き出す鍵なのです。
共感を呼ぶ「マクラ」を使う
話の冒頭で相手に寄り添う言葉を投げかけると、聞き手は自然と耳を傾けやすくなります。
本書では、これを「共感マクラ」と呼びます。
たとえば「私も同じことで悩んだ経験があります」と一言添えるだけで、相手は「自分ごと」として話を受け止めやすくなる。
相手が置かれた状況に共感しながら説明を始めることで、信頼感を築きやすくなるのです。
質問を誘導する「釣り針」の仕掛け
説明の中で、あえて「ツッコミどころ」を残しておくと、相手は思わず質問を投げかけてきます。これが「釣り針」の仕掛け。
自発的に質問した内容に即座に答えることで、相手は深く納得し、説明者に信頼を寄せやすくなります。
重要なのは、質問に対して十分な答えを準備しておくこと。意図的に疑問を誘発し、それに応えることで、説明は双方向的で説得力あるものに変わります。
一人ツッコミや情報の出し惜しみで惹きつける
プレゼンや会話の中で、あえて自分で「ツッコミ」を入れることで、相手の注意を引きつける手法も効果的です。
「ここで疑問に思う人もいるかもしれませんが…」と一人ツッコミを入れると、聞き手は自然に集中します。
また、最初から全てを語らず、少し情報を出し惜しみすることで「続きが気になる」という心理を喚起できます。
こうした小さな演出が、相手を最後まで引き込み、行動へとつなげるのですね。
プレゼン・商談で使えるポイント
説明の中でも特に難易度が高いのが、複数人を相手にするプレゼンや商談の場。
本書では、相手を惹きつけながら納得感を高めるための実践的なポイントが紹介されています。
どんなに優れた商品やサービスであっても、説明の仕方を誤れば相手の心には届きません。
逆に、ちょっとした工夫を加えるだけで、相手の印象は大きく変わり、結果にも直結します。
ここでは、著者が提案する「テンプレート」「カスタマイズ」「マイナス共有」の3つを取り上げます。
プレゼン必勝のテンプレート
聞き手の集中力を最後まで保つには、話の構成に工夫が必要。
本書では「導入→問題提起→解決策→結論」という4段階のテンプレートを推奨しています。
導入で関心を引き、課題を明確化し、解決策を提示してから結論で締める流れは、誰にとっても理解しやすく説得力があります。
型を守ることで安心感を与えつつ、内容を自在にアレンジできるのもメリット。
相手企業に合わせた資料のカスタマイズ
どんなに完成度の高い資料でも、相手にフィットしていなければ響きません。
本書では、相手企業や業界に特化した情報を少しでも織り込むことを勧めています。
たとえば「御社の市場シェアは業界平均より高い」など、相手に関連するデータを加えるだけで「自分たちのために準備してくれた」という好印象につながる。
資料はテンプレート化して効率化しつつ、最後の仕上げでカスタマイズする姿勢が評価を高めるのです。
信頼を生む「マイナスの共有」
多くの人はプレゼンで「良い面」ばかりを強調しがちですが、本書はあえて「弱点やリスク」を伝えることの重要性を説きます。
たとえば「初期導入に時間はかかりますが、その後の運用コストは大幅に削減できます」と伝えることで、かえって誠実さが伝わり、信頼が深まる。
弱点を隠さず共有することで、相手は「この人の説明は信用できる」と感じ、最終的な合意形成がスムーズになるのです。
まとめ|説明は「相手のため」に行うもの
本書を通して一貫して語られているのは、「説明は自分のためではなく相手の理解のために行う」という姿勢です。
論理的に整理された話し方や、データを駆使した説得力も大切ですが、それ以上に重要なのは「相手が何を求めているか」を踏まえた上で伝えること。
相手の立場や期待値を意識し、身近なたとえや数字を交えながら説明することで、理解だけでなく納得と信頼を生むことができます。
また、本書で紹介されたテクニックは決して難しいものではなく、日常のコミュニケーションでもすぐに応用できる実践的なものばかりです。
会議での発言やプレゼン、上司や部下とのやり取りに取り入れるだけで、相手の反応は大きく変わるでしょう。
説明が上手くなるということは、自分の考えを相手に届ける力を高めることでもあり、ひいては仕事や人間関係を円滑に進めるための大きな武器になります。
これからのキャリアを築くうえで欠かせないスキルとして、ぜひ本書で紹介される考え方を実生活に取り入れてみてください。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
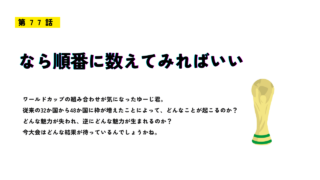 コラム2025年12月9日第77話「なら順番に数えてみればいい」
コラム2025年12月9日第77話「なら順番に数えてみればいい」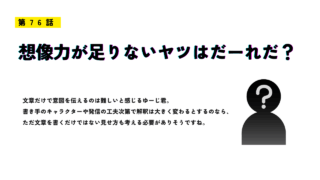 コラム2025年12月2日第76話「想像力が足りないヤツはだーれだ?」
コラム2025年12月2日第76話「想像力が足りないヤツはだーれだ?」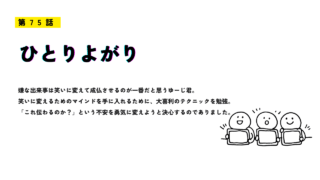 コラム2025年11月25日第75話「ひとりよがり」
コラム2025年11月25日第75話「ひとりよがり」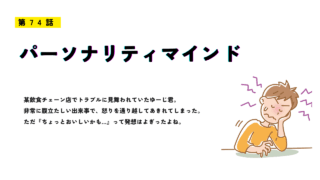 コラム2025年11月18日第74話「パーソナリティマインド」
コラム2025年11月18日第74話「パーソナリティマインド」