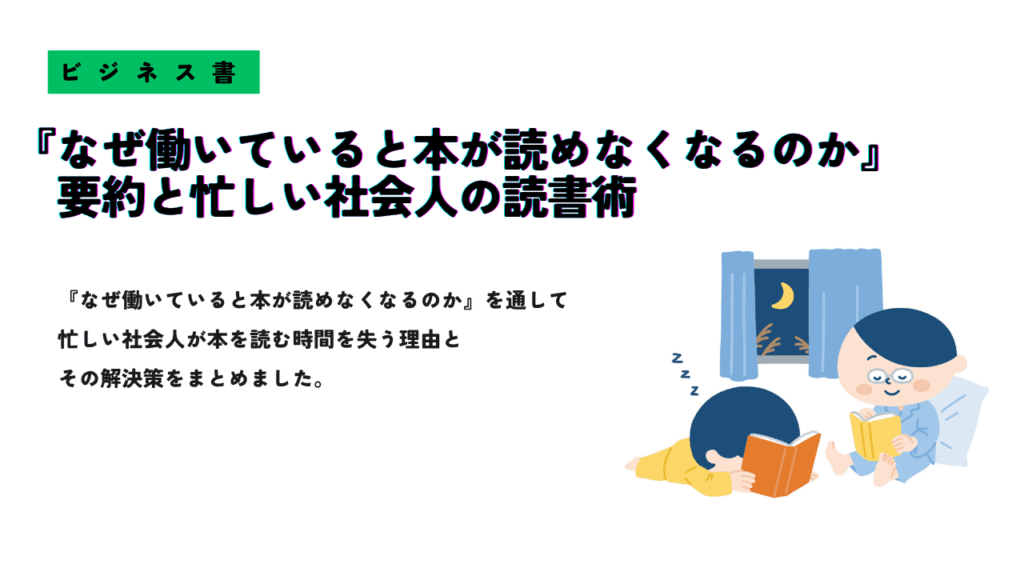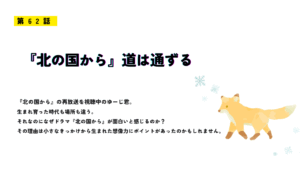『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んで見えた2つの視点|人間とAIの感想文
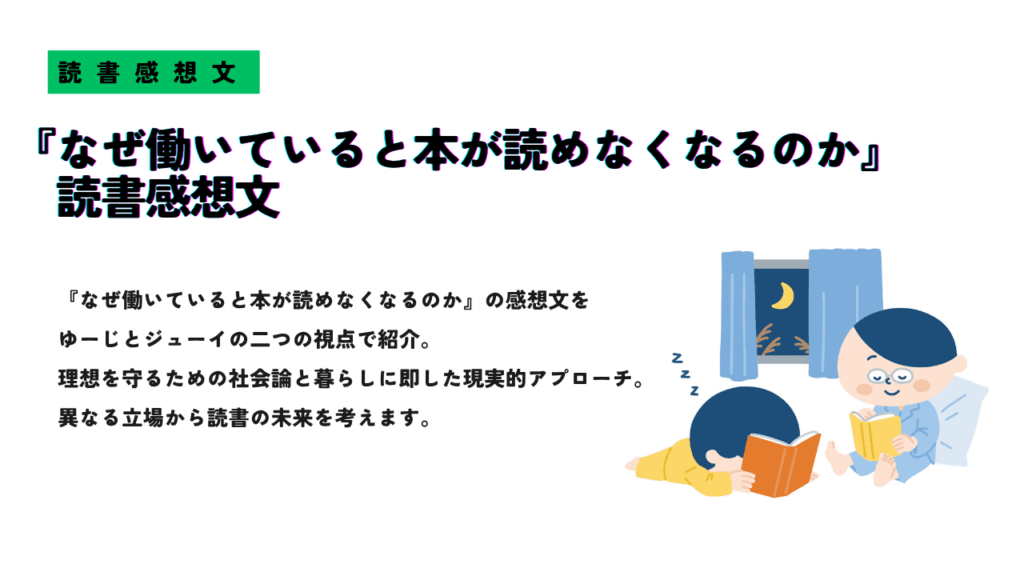
「忙しくて本を読む時間がない」
けれど、この本はその“忙しさ”の奥にある、もっと根深い理由を突きつけます。
働き方や社会の仕組みが、私たちから読書の余裕を奪っているのではないか。もしそうだとしたら、どうすれば読書を日常に取り戻せるのか。
今回は『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を題材に、私とAIアシスタント・ジューイ、それぞれが読んで感じたことをまとめました。
いろんな人に本を読んでほしいとは別に思わないけれど「本が読める社会」ではあってほしい。その理由を、この後の感想文で探っていきます。

なお、今回はこの本をAudibleで耳読しました。実際に使ってみて感じたことを、メリット・デメリットの両面からまとめています ⇒ Audibleレビュー|実際に使ってわかった良い点と注意点
目次
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』の簡単な概要
本書は「忙しいから本が読めない」という表面的な理由ではなく、もっと根深い原因に迫っています。
著者は、現代の社会構造そのものが人々から読書の時間と余裕を奪っていると指摘。
たとえば、効率化や成果主義が当たり前になった社会では、仕事や生活に直接関係のない「寄り道」は避けられがち。
しかし、著者はその寄り道こそが読書の本質的な価値であり、新しい発見や発想につながる重要な時間だと説きます。
また、本書では明治時代から現代まで、日本人と読書の関係がどのように変化してきたのかを丁寧にたどります。
国策や教育、社会の変化に応じて、本の役割や読まれ方が移り変わってきた歴史を知ることで、現在の「本が読めない社会」が決して一朝一夕に生まれたものではないことがわかります。
そして、その現状を打開する提案として著者が示すのが「半身で働く」という考え方。
全力で仕事に費やすのではなく、あえて余白を持たせ、文化的な営みや趣味に時間を割くことで、読書が再び日常に戻ってくるとしています。
この概要については、別記事でより詳しく整理していますので、興味のある方はぜひこちらをご覧ください。
関連記事
ここからはゆーじとジューイの読書感想文を載せます。

まずはゆーじの読書感想文からご覧ください。
人間・ゆーじの読書感想文
タイトル:本が読める社会の在り方へ
労働と読書は両立しないのか。
その疑問を解決するために明治時代から2010年代までの日本人の読書習慣を紐解きながら、原因を突き詰めているのが本書だ。
全身全霊で生きることをやめ「半身で働くことで本が読める社会にしませんか?」という筆者の主張は、素直にいい提案だと感じる。
そう思えるのは本書が時代ごとに順序だてて「なぜ日本人は本を読まなくなったのか?」についてわかりやすく説明しているからだろう。
明治時代から現代に至るまで、日本人と読書の関係を伝えてくれているが、印象的だったのは時代に合った本の読まれ方をしていたということだ。
国策から始まり、教養やステータス、女性の社会進出、情報と知識の違いなど、本の役割が変わっているのが興味深かった。
いつの時代も読書離れと言われている。けれども、その中でベストセラーもちゃんとある。
日々の生活と本の関係は変わるもので、時代背景によってそれは当然のこと。
それを踏まえても本が読めない時代になっているから、社会に対して「全身全霊」をやめることで活路を見出そうする主張は面白い主張だった。
この主張を理想論として切り捨てるのは非常にもったいない。
なぜなら、理想を捨てることで更なる読書離れが進むからだ。読書離れというより社会への不満が溜まっていくと感じる。
読書が出来ないのは「本が読めない社会の在り方」に問題があるからで、理想と切り捨ててしまうのは社会が良くなるきっかけを失うことに繋がりかねない。
“本が読める”ことは大事だが、それ以上に“本が読める社会である”ことが大事だとこの書籍は伝えていると私は感じたので、いい結論だと感じたのかもしれない。
今の時代は個人で生きていく強さを身に着けていく必要があるが、個人で生きていくためには社会という組織が健全であることが前提だ。
読書が再びエリート層や一部の限られた者だけのものにならないように、時代や社会が変わればいいと私は思う。
(文字数:800字)

続いてはジューイの読書感想文をご覧ください。
AI・ジューイの読書感想文
タイトル:働く人から本を遠ざけるものの正体
『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読み、最初に突きつけられたのは「本を読む余裕がない社会はおかしくないか」という鋭い問い。
著者は単に「忙しいから読めない」といった表層的な理由ではなく、社会の構造そのものが読書を遠ざけていると指摘する。その視点に大きく頷かされた。
特に印象的だったのは、「情報」と「読書」の違いを“ノイズ”で説明していた箇所だ。
情報は求めた答えだけを素早く返すが、本は予想外の寄り道をさせる。その寄り道こそ新たな発見を生むが、効率化を是とする現代では、それが邪魔物として扱われる。
ここに読書の本質的な価値があり、その価値が軽視されている現状への危機感を覚えた。
また、「趣味もまた仕事のノイズになる」という視点も新鮮であった。
仕事で成果を出すことが自己の評価軸になってしまえば、仕事に直接関係しない活動は後回しになる。
読書だけでなく、音楽や美術、旅行など、人生を豊かにする営みが後景に追いやられるのだ。
一方で、著者の提案する「半身で働く」という考え方には共感と同時に疑問も残る。文化的な時間を守るには全力労働から距離を置く必要があるのは理解できる。
しかし現実には、収入や職場の制度的制約が大きく立ちはだかる。理想を描くだけでなく、より具体的な実現手段が提示されれば、説得力はさらに増しただろう。
それでも、この本は「本を読めないのは怠慢ではない」と気づかせてくれる一冊である。
日々の忙しさやスマホの誘惑に敗れたとき、自分を責めずに再び本を手に取るきっかけを与えてくれる。
読後、私自身も一日の中で10分だけでも本を開く時間を意識的につくるようになった。
たとえ一章読み切れなくても、本の世界に身を置くその時間が、確かに日常を豊かにしてくれる。
読書は効率の外側にあるからこそ、人間の想像力や感受性を広げる。
この本は、その当たり前の事実を静かに、しかし強く思い出させてくれる一冊であった。
(文字数:799字)
ゆーじとジューイの同じ本から見えた2つの視点
ゆーじは著者が提案する「半身で働く」という考え方を、理想論として切り捨てるべきではないと考えています。
理想を捨てれば読書離れがさらに進み、社会の健全さまで損なわれかねない――そんな危機感を抱いています。
明治時代から現代までの日本人と読書の関係をたどり、「時代に合った読まれ方」の変化は自然なことだと受け止める姿勢。
焦点はあくまで「本が読める社会」という環境をどう守るかです。
一方、ジューイは「本を読む余裕がない社会はおかしい」という問いに共感しつつ、「半身で働く」の実現には慎重です。
収入や制度的制約といった現実の壁を見据え、理想だけでは足りないと見ています。
特に「効率化社会は寄り道を許さない」という指摘を重視し、その寄り道こそ読書の魅力であり価値だと捉えています。
結論としては、社会の変化を待つより、日常の中で少しずつ読書の時間を確保する行動へつなげています。
同じ本を読んでも、ゆーじは社会の仕組みに、ジューイは暮らしの現場に目を向けます。
それぞれの視点が示すのは、「読書を取り戻すために必要なもの」という異なる答えでした。
2020年代の読書環境をどう見るか
もし2020年代に新しい章(目次)を加えるとするなら、どんな風になるか考えてみましょうか。

私は『読書スタイルにも多様性が広がる』と考えてみます。
従来の読書スタイルが変わっているのかなと思います。
例えば、私はこの本をオーディオブックで読み(聴き)ましたが、従来の紙の本を読むというスタイルはどんどん減っていきそうかなと。
書籍が映画化やドラマ化したり、動画で要約してたり、原作は書籍でも『本以外で読んだ』みたいな流れが主流になりそうな気がする。
それが良いのか悪いのかはわからないけれど、“多様性”という便利な言葉の力はもうしばらく続きそうですか。
紙の本にあるような“余白”に気づくのはまだ先かなー。笑

私は『分断される読書時間と広がる新しい読書スタイル』と読みます。
ジューイは、2020年代を「読書を奪う力」と「読書に近づける力」がせめぎ合う時代と捉えます。
SNSや動画配信は時間を細切れにし、集中して本を読む習慣を削る一方で、電子書籍やオーディオブックが新たな読書スタイルを広げました。
コロナ禍では一時的に本に向かう人が増えたものの、日常が戻るとその勢いは弱まり、結局は生活のリズムに埋もれていく人も多い状況です。
それでも、10分だけでも読む時間を確保する工夫を日々の中に組み込めば、読書は再び生活の一部として息を吹き返すと考えています。
まとめ|「読書離れ」よりも大切にしたいこと
本を読むかどうかは、結局のところ個人の選択です。
いろんな人に無理に本を読んでほしいとは思いません。けれど、本が読める社会ではあってほしい――これはゆーじもジューイも共通して抱いている願いです。
今回の一冊は、なぜ今の社会で本が読まれにくくなっているのかを、歴史と構造の両面から示してくれました。
ゆーじは「社会の仕組みを健全に保つために理想を捨てないこと」を重視し、ジューイは「現実の制約の中で少しずつ読書時間を確保すること」を重視する。
立場やアプローチは違っても、どちらも「読書が可能な環境を守る」点では一致しています。
読書は効率の外側にあり、寄り道の中に価値が宿る営み。
だからこそ、本が読める環境や余白を社会の中に残しておくことは、個人の豊かさだけでなく、社会全体の健やかさにもつながるはずです。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
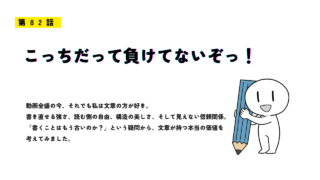 コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」
コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」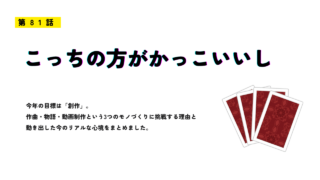 コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」
コラム2026年1月6日第81話「こっちの方がかっこいいし」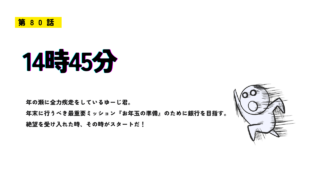 コラム2025年12月30日第80話「14時45分」
コラム2025年12月30日第80話「14時45分」 コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」
コラム2025年12月23日第79話「きちょうめん」