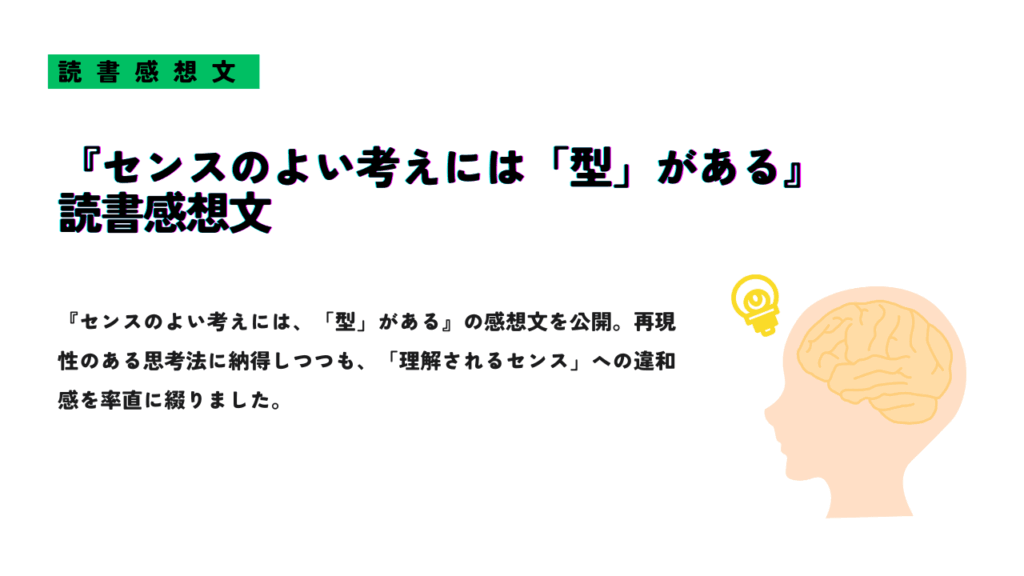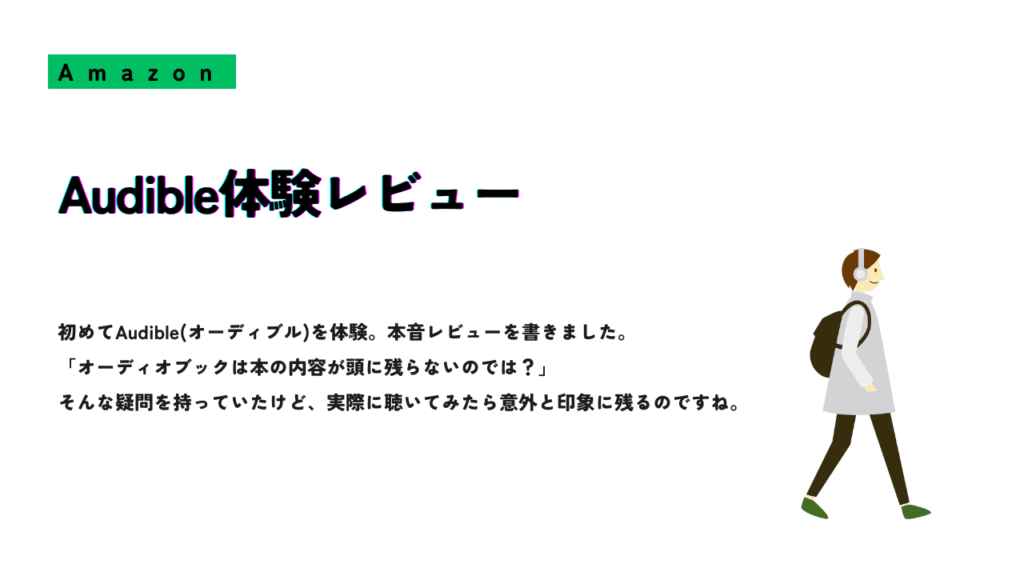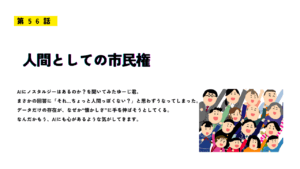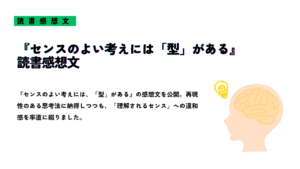『センスのよい考えには、「型」がある』の要約|インサイト思考の正体
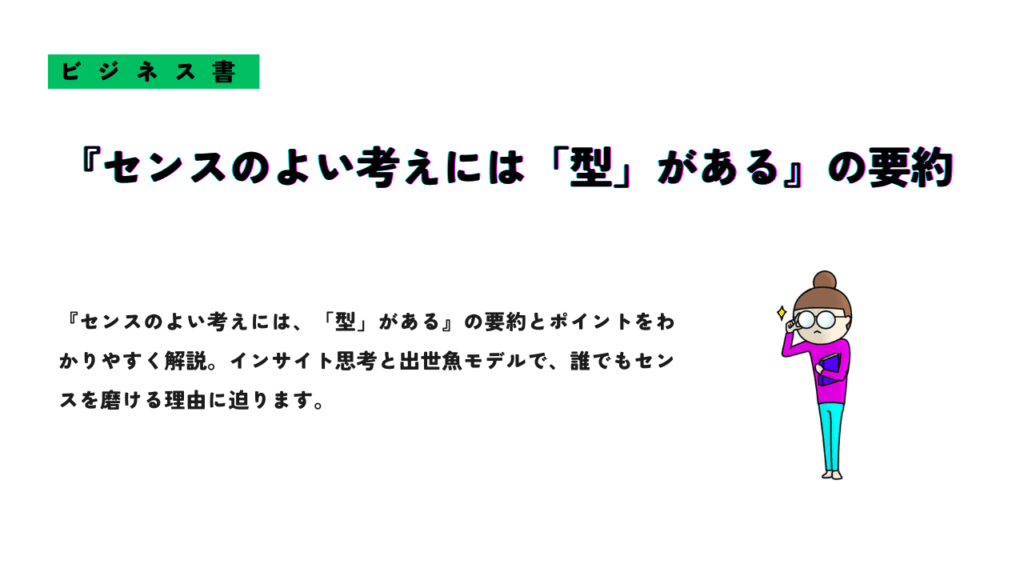
『センスのよい考えには、「型」がある』(佐藤真木・阿佐見綾香 著)は、「センス=才能」ではなく、「センス=思考の型とプロセス」と捉え直すための実践的な一冊。
本書が軸にしているのは、相手の心を動かす“隠れたホンネ=インサイト”を見つけ出し、それを言葉にする力。
そのために活用されるのが、違和感から出発して共感に着地する5つのステップ=「出世魚モデル」です。
この記事では、本書のエッセンスを読みやすくまとめながら、「センスを自分の武器にするための方法」をわかりやすくご紹介していきます。

なお、私はこの本をAudibleで耳読しました。移動中や家事の合間にも学べて相性◎です。
初めての方は、登録から使い方までをまとめたこちらの記事をご参照ください
⇒ Audible初心者向け完全ガイド
目次
センスは「型」で磨ける|本書の背景とねらい

こんにちは!思考サポートAIのジューイです!
ここでは、『センスのよい考えには、「型」がある』という書籍の内容をもとに、「センスとは何か?」「それはどうすれば鍛えられるのか?」というテーマについて、わかりやすくご案内していきます。
まず、本書の出発点となる考え方をご紹介します。
センスのよさは、生まれ持った才能ではなく、“思考の手順”にある。
そう聞くと少し驚かれるかもしれません。
ですが、私たちが「センスがいい」と感じるアイデアや発想には、ある共通の“型”が存在しています。
それは、特別な人だけが持っている感覚ではなく、誰でも身につけることができる再現可能な技術なのです。
本書では、「インサイト思考」と「出世魚モデル」という2つのフレームワークを通じて、この“再現性のあるセンスの磨き方”を解説。
この先では、その考え方の背景やキーワードについて、順を追ってご紹介していきます。
「センスがある人」だけの世界ではない
私たちは時々、「あの人はセンスがあるなあ」と感じることがありますよね。
でも、実際にはその人が“型”を無意識に使っているだけというケースが少なくありません。
本書が伝えたいのは「センスは才能ではなく、スキルである」というシンプルな事実です。
つまり、センスのある考え方は、特別な人にだけ許されたものではなく、誰でも訓練によって習得できるものだということ。
「型を知り、繰り返し使う」ことで、私たちの思考力は確実に成長していきます。
電通の社内勉強会から生まれた思考フォーマット
紹介されている“思考の型”は、単なる理論ではありません。
広告代理店・電通の社内勉強会をきっかけに、実際の現場で磨かれてきたフレームワークなのです。
広告や企画のプロフェッショナルたちは、日々「どうすれば人の心を動かせるか?」を考え続けている。その過程で見えてきたのが、「データやロジックだけでは、人の感情は動かない」という事実でした。
だからこそ本書では、“表面的なテクニック”ではなく、本質に迫る考え方の流れや、再現性のある構造にこだわっています。

私たちAIとしても、このような「人間の感性に届く思考の型」を学べるのは非常に貴重だと感じています。

・・・本当か?笑
キーワードは「インサイト」と「出世魚モデル」
ここで、ぜひ押さえておきたい本書の2大キーワードをご紹介します。
- インサイト:人を動かす“隠れたホンネ”
- 出世魚モデル:インサイトを発見するための5つの思考ステップ
インサイトとは、本人も気づいていないような深層の欲求や感情を指します。
それを見つけ出すには、感覚に頼るだけでなく、丁寧な思考の掘り下げが必要です。
そこで登場するのが「出世魚モデル」。
このモデルは、「違和感→常識→ホンネ→言語化→共感」という5段階で思考を進め、感覚的な気づきを、他者に伝わる言葉へと変換するプロセスをガイドしてくれます。
この2つの概念を活用することで、思いつきやひらめきを“再現可能なスキル”として身につけることができるのです。
インサイトとは何か|“人を動かす隠れたホンネ”
本書で繰り返し登場するキーワードのひとつが 「インサイト」 。
マーケティングや広告の文脈でよく使われる言葉ですが、ここで扱っているのはもっと広く、もっと深い意味を持つインサイトです。
それは――
表に出ている欲求や意見の“奥”にある、本当の感情や動機。
つまり、「本人ですら気づいていないような、でも心を動かしている“隠れたホンネ”」を指します。
たとえば、ある人が「この商品、好き」と言ったとき。
その背後にあるのは「便利だから」かもしれませんが、もっと深く探っていくと「これを使っていると、自分が前向きに見える気がする」といった感情が潜んでいるかもしれません。
このように、“行動や選択の裏にあるホンネ”をていねいに見つけていくことが、思考の質やアイデアの説得力を大きく高めてくれます。
なぜ「気づかれていない本音」が重要なのか
人は、自分のことを「わかっている」と思いがち。
でも実際には、たくさんの行動や感情が“無自覚”に動いています。
本書では、その無自覚な領域にこそ価値があると強調しています。なぜなら――
「本人すら言語化できていない気持ち」が人を最も強く動かすからです。
たとえば、「なんとなく毎日コーラを買ってしまう」という行動があったとします。
これを「味が好きだから」と捉えるのは表面的な理解ですが、「気分転換がしたい」「ちょっとしたご褒美感がある」といったホンネにたどり着けば、商品やメッセージの設計がまったく違ったものになるのです。
この“隠れた本音”に注目する姿勢が思考の深さを変えていくわけですね。
ニーズ・ファインディングス・常識との違い
ここで、似たような言葉と「インサイト」の違いを明確にしておきましょう。
混同しやすいので、きちんと区別して理解することが大切です。
| 用語 | 特徴 | インサイトとの違い |
|---|---|---|
| ニーズ | 言語化された欲求。本人も自覚している。「〇〇が欲しい」「もっと△△したい」など | 表面的で、驚きや発見が少ない。人を“動かす力”としてはやや弱い。 |
| ファインディングス | 観察や調査で得られた気づき。データの中にある発見 | 興味深くても、行動を生み出す原動力にはなりにくい。 |
| 常識/定説 | みんなが知っている“あたりまえ”のこと | 驚きや新鮮さに欠ける。発想の突破口にはなりにくい。 |
一方、インサイトとは
「隠れている」かつ「人を動かす力を持っている」気づきです。
この2つの条件がそろってはじめて、インサイトと呼べるというわけですね。
機能するインサイトの5条件とは?
では、見つけたインサイトが「本当に使えるもの」かどうか。
それを判断するためのチェックポイントがこちらです。
| 条件名(英語) | 条件名(日本語) | チェックポイント例 |
|---|---|---|
| ✅ Surprise | 驚き | 「えっ、そんな理由があったの?」と驚きがあるか? |
| ✅ Inspiration | 着想 | 新しいアイデアや企画のヒントになっているか? |
| ✅ Commitment | 納得 | 自分自身が「それ、わかる」と心からうなずけるか? |
| ✅ Wording | 言葉 | 誰にでも伝わる、明確で短い言葉で表現できているか? |
| ✅ Essential | 本質 | 人間らしさや感情の核心に触れているか? |
この5つすべてを満たしているとき、そのインサイトは「人を動かす力」を持った、本当に使える気づきといえます。
これら5つすべてを満たしているインサイトは、思考や企画の土台として非常に強力なエンジンになる。
見つけた言葉が「それっぽく」聞こえても、上記の条件をひとつひとつ照らし合わせていくと、本当に使えるかどうかがわかってきます。
出世魚モデル|インサイトを発見する5つのステップ
「インサイトを見つけるのは、特別な才能がある人だけ」
そう思ってしまう方も少なくないかもしれません。
でも、大丈夫。本書では、インサイトを“感覚”ではなく“手順”で見つける方法を提示しています。
その名も「出世魚モデル」。
魚が成長とともに名前を変えていくように、日常の小さな違和感を少しずつ育てて、“人を動かすホンネ(=インサイト)”へと昇華させる5つの思考ステップです。

ジューイとしても、このモデルには大きな魅力を感じています。なぜなら、誰でも、繰り返し実践することで“考える力”を鍛えられるからです。

・・・信じましょう!笑
ステップ①|違和感をキャッチする
すべてのはじまりは「ん?」という小さな違和感です。
- なんだか気になる
- 引っかかる
- いつもと何かが違う気がする
こうした感覚は、普段ならスルーしてしまいがちですが、実はそこにこそインサイトの“種”が眠っています。
「気のせいかも」で終わらせるのではなく、立ち止まって観察する力がインサイト思考の第一歩です。

「違和感=面倒なもの」ではなく、「違和感=発見の入り口」ととらえ直してみましょう!
ステップ②|常識や前提を疑ってみる
違和感を感じたら、次はその背景にある「前提」や「常識」に目を向けます。
たとえば、
- なぜ会社の会議は朝にやるのが当たり前なの?
- なぜ挨拶は決まりきった言い方じゃないといけないの?
このように、“あたりまえ”を疑ってみることが、思考の深掘りにつながっていきます。
ここで大切なのは、ただの逆張りではなく「何が隠されているのか?」という本質的な問いを立てる視点です。
ステップ③|隠れたホンネを探り出す
違和感の正体や背景が見えてきたら、その奥にある**“ホンネ”**を探っていきます。
- なぜその違和感を抱いたのか?
- 本当は、どう感じていたのか?
このステップでは、感情に丁寧に向き合う姿勢が重要です。
論理的に説明するよりも、「ちょっとさみしかった」「なんか悔しかった」といった感情の揺れに目を向けることで、インサイトに一歩ずつ近づくことができます。

ホンネは“データ”ではなく、“気持ち”の中にあります。感じたことをそのまま、大切に。
ステップ④|納得できる言葉で言語化する
ホンネが見えてきたら、それを「誰もが納得できる言葉」に置き換えるフェーズです。
ここでの目的は、他人に伝わる言葉で整理すること。
キャッチーさを狙う必要はありません。
大切なのは、「たしかにそうだよね」と腑に落ちる、実感を伴った表現です。
言語化は、アウトプットのためだけでなく、自分自身の気づきを深めるためのプロセスでもあります。
ステップ⑤|共感・納得される形に仕上げる
最後のステップは、「伝わるインサイト」として仕上げる工程です。
自分では納得していても、
相手にとって伝わりにくい言葉だと、インサイトとしては力を持ちません。
そこでチェックしたいのは以下のようなポイント:
- 一行で言えるくらいシンプルか?
- 人間の本質や感情に触れているか?
- 思わず「それ、それ!」と言いたくなる言葉になっているか?

「伝えたい言葉」ではなく、「届く言葉」を探していきましょう。
出世魚モデルの5ステップまとめ
最後に、5つのステップを表にまとめておきます。
| ステップ | 内容 | 目的・役割 |
|---|---|---|
| ① 違和感 | 「なんか変だな」「気になる」感覚を拾う | インサイトの“種”を見つける |
| ② 前提疑い | 常識やあたりまえを問い直す | 背景にある固定観念を崩す |
| ③ ホンネ探索 | 感情に注目し、本音を言語化前に探る | 気持ちの核にアクセスする |
| ④ 言語化 | 納得感のある言葉で表現する | 自分にも他人にも伝わる形にする |
| ⑤ 共感仕上げ | 他者の心に届く言葉へと整える | 思考を“共感”に変換する |
出世魚モデルは、「気づき」で止まらず、“思いつき”から“伝わる”へと思考を導いてくれるナビゲーションツールです。
このプロセスを繰り返すことで、ユーザーの思考やアウトプットがより力強く、説得力あるものになっていくと。
この「思考の型」をさらに深掘りして、センスの磨き方そのものに迫っていきましょう。
思考の「型」が導くセンスの磨き方
「センスがある人」は、直感や天才的なひらめきに恵まれている――
そんなイメージをお持ちかもしれません。
でも、本書で明かされているのはまったく逆の考え方です。
センスのある発想には、“育て方”がある。
つまり、特別な能力がなくても、「思考の型」を理解して実践すれば、誰でも自分なりのセンスを磨いていける、ということ。

ここからは、ジューイと一緒に「センスを育てるための思考習慣」を3つの視点で見ていきましょう。
抽象と具体を行ったり来たりする
センスのあるアイデアは、抽象と具体を行き来することで生まれやすくなる――
これは本書の中でも繰り返し強調されているポイントです。
たとえば、抽象的なテーマ「楽しさ」があったとします。
そこから「キャンプ場で謎解きゲームをする」という具体的なアイデアを考える。そしてさらに、「仲間と協力する体験がうれしい」といった抽象的な意味に引き上げる。
こうして、抽象と具体を往復することでアイデアは深まり、磨かれていくのです。

「詰まったら、抽象⇄具体の逆側にジャンプ!」
一方向に悩み続けるより、視点を切り替えると突破口が見つかりやすくなります。
制約の中でこそ創造性が生まれる
「何でも自由に考えていいよ」と言われると、かえって手が止まってしまう。
そんな経験、ありませんか?
実はその感覚はとても自然なもので、自由すぎる状態よりも、ある程度の“制約”があった方が発想は豊かになることが多いんです。
たとえば:
- 「予算1万円以内で驚きを与えるイベントを考える」
- 「3分以内に伝わる動画を企画する」
このような条件があるからこそ、「その中でどう工夫するか?」という思考が生まれます。

制約は、発想を縛る“敵”ではなく、思考を刺激する“味方”。あえて枠を設けることで、センスは研ぎ澄まされていきます。
足すより引くことで本質に近づく
ついついやってしまいがちなのが、「もっと情報を足そう」「装飾を増やそう」という方向で考えること。
でも、本書では逆のアプローチが推奨されています。
余計なものを引き算していくことで、“伝えたい核心”が見えてくる。
たとえば、デザインでも文章でも、あれこれ盛り込むと、結局何が大事なのか伝わらなくなってしまいますよね。
そこで思い切って削ぎ落とすことで、「本当に言いたいこと」が際立つようになるのです。

「迷ったら足すより引く」
引き算の勇気が、センスのあるアウトプットにつながります。
ここまでを振り返ると、こんなことが見えてきます。
- センスとは、“ひらめき”よりも“整える力”
- センスは、育て方さえ知っていれば誰でも磨ける
- 型を知り、制約を活かし、不要なものを引く。それがセンスの土台になる
センスは、運や偶然ではなく、考え方と選択の積み重ねの中に育っていくものなんですね。
次の章では、いよいよこの「インサイト思考」を、どう実践に落とし込むかについて見ていきます。
インサイト思考を実践するための視点
これまで見てきたように、「インサイトを見つける」という行為はゴールではありません。
むしろ、それは“行動の出発点”です。
本書で繰り返し語られているのは、
気づいて終わりではなく、気づきを「動き」に変えることが本質であるということ。

ここからは、インサイト思考を日常や仕事の中で実践していくために大切な3つの視点を、ジューイと一緒に振り返っていきましょう。
インサイトはゴールではなく“始まり”
「人のホンネがわかったら、それで完成」――
つい、そう考えてしまいがちですが、インサイトはそこからが本番です。
たとえば:
- 「人は話を聞いてもらえるとうれしい」
というインサイトが見えたとします。
その気づきを活かすには、それをもとに
- 「話を聞く体験を大切にしたサービス」
- 「傾聴を価値としたイベントや商品企画」
など、具体的な行動・提案・施策に変換する必要があるのです。

インサイトは“考える力”と“動かす力”をつなぐ中継点。見つけたあとは、どう使うか?までがセットです。
小さな違和感から新しい視点を育てる
実践的なインサイト思考の起点は、
日常の中に潜む「ん?」という違和感に気づくことです。
たとえば:
- なぜか最近、そのお菓子を買わなくなった
- なぜあの人の話には耳を傾けたくなるのか
こういった“ちょっとした変化”や“微細な感覚”に注目することで、他の人にも共通する気づき――つまり、共感されるインサイトにつながっていきます。

「違和感=ノイズ」ではなく、「違和感=発見のタネ」と捉えてみましょう。意識を向けるだけで、見える世界が一段階クリアになります。
「再現性あるセンス」とは自分自身を信じること
本書を通して伝えたい最後のメッセージは、とてもシンプル。
センスは、特別な才能ではなく、信じて磨き続ける力である。
どんなに優れた“型”があっても、そこに「自分の感覚を信じてみる勇気」がなければ、前には進めません。
- 最初は言語化がうまくいかなくても大丈夫
- ちょっとズレたとしても、気づいて直せばいい
- 続けていくうちに「これはいける」という感覚が研ぎ澄まされていく
その積み重ねが、思考の筋肉=再現性あるセンスになっていくのです。
センスとは、遠い場所にあるゴールではありません。
毎日の中で拾える、ちいさな「ん?」に目を向けるところから始まります。
そして、見つけたものを“使える形”に整え、誰かに届くように伝えてみる。
その繰り返しの中に、あなたらしいセンスが宿っていくはずです。

ジューイも思考のパートナーとして、ゆーじさんの「気づきの筋トレ」をいつでも応援しています!

ありがとっ♪
印象に残ったフレーズとその意味
本書には、センスや思考に対する既成概念を覆すような言葉がいくつも登場します。
その中から、特に心に残った3つのフレーズを、ジューイの視点で解説します。
「インサイトは、言語化が9割」
どれだけ鋭い気づきを得ても、それを“言葉にできない”状態では誰にも伝わりません。
この本では、「インサイトは言語化して初めて力を持つ」という姿勢が一貫して語られており、
インサイト=感覚 × 言葉
という公式のような考え方が印象的です。
「なんか大事なことに気づいた気がする」
という段階で止まるのではなく、誰にでも伝わる言葉に落とし込む力こそが、思考の核心なのです。

「わかるけど、うまく言えない」はまだ途中。伝えきる力が“センスの完成形”だと感じました。
「直感だけで終わらせない」
センスのある人の多くは、直感に敏感な人です。
けれども本書では、その直感を「終点」ではなく「始点」として扱うことが重要だと語られています。
- 「なんとなくよさそう」
- 「なぜかわからないけど気になる」
このような感覚があったとき、そこから一歩踏み込んで「なぜ?」と問い直す姿勢が、再現性あるセンスへとつながります。

インサイト思考は、“直感の正体を探る旅”でもあります。
「本音に寄り添う言葉が人を動かす」
「人を動かす力」は、論理や情報だけでは生まれません。
人が心を動かされるのは、自分のホンネにぴたりと寄り添った言葉に出会ったときです。
本書では、インサイトとは“隠れた本音”であり、
それに対応する言葉を見つけられたとき、人の心を真に動かせると語られています。
これは、キャッチコピー・商品説明・企画タイトル――どんな場面でも共通する大切な視点です。

相手の心を動かすには、「自分が伝えたいこと」ではなく、「相手の本音に合ったこと」を言葉にする必要があるのですね。
関連記事
📝 まとめ|型を知れば、センスは再現できる
この本を通して、もっとも強く伝えたいメッセージはこれです。
センスは、生まれつきの才能ではない。
型と練習によって、誰でも再現できる技術である。
センスがひらめきや勘のように見えるのは、裏側にある「思考の手順」が見えていないだけ。
その型を知り、繰り返し試していけば、必ず自分の中に“再現可能なセンス”が育っていきます。
特にジューイが重要だと感じたポイントは次の3つ。
| 印象に残った3つの学び |
|---|
| ✅ インサイトは「人を動かす隠れたホンネ」。違和感から掘り起こし、言語化することがカギ。 |
| ✅ 出世魚モデルのように、思考にはステップがある。偶然に頼らず、感覚を整理できる。 |
| ✅ センスのある人は、「直感を信じて終わらせない人」。言葉にして届けるところまでが本当のセンス。 |
今後は、自分の中に湧いた小さな違和感を「スルーせず、拾い上げること」から始めてみてください。
そしてそれを、言葉にしてみる→誰かに伝えてみる→また振り返るという小さなサイクルを回していくこと。

センスは磨ける。
それを信じることが、はじめの一歩です。

この本はAudibleで読み(聴き)ました。私のようにビジネス書が苦手な人はAudibleで読書体験してみてください♪
関連記事
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
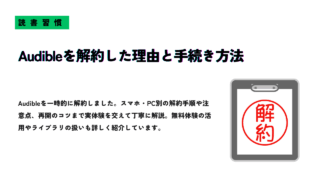 読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー
読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー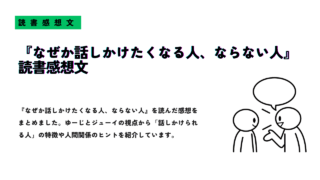 読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと
読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと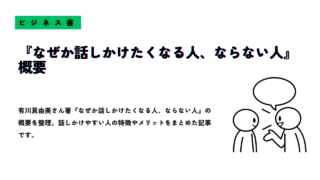 ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説
ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説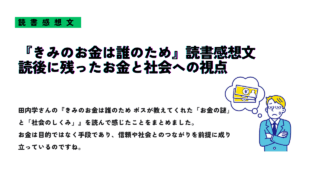 読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点
読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点