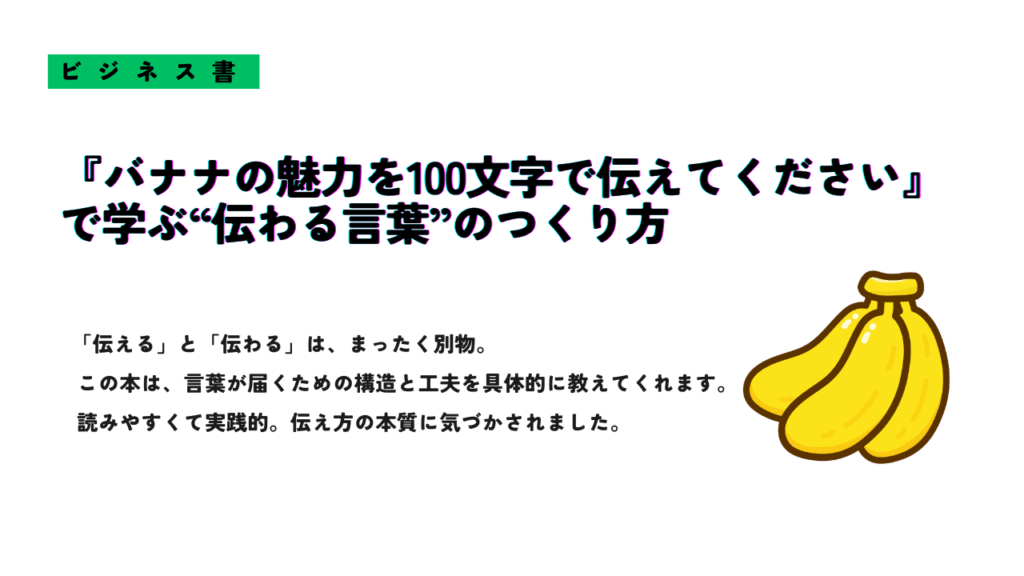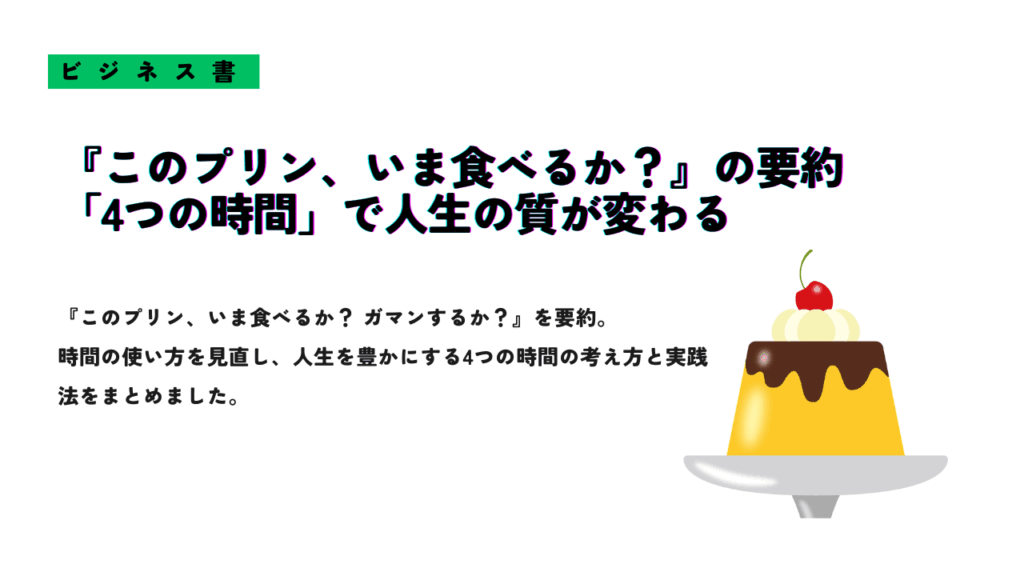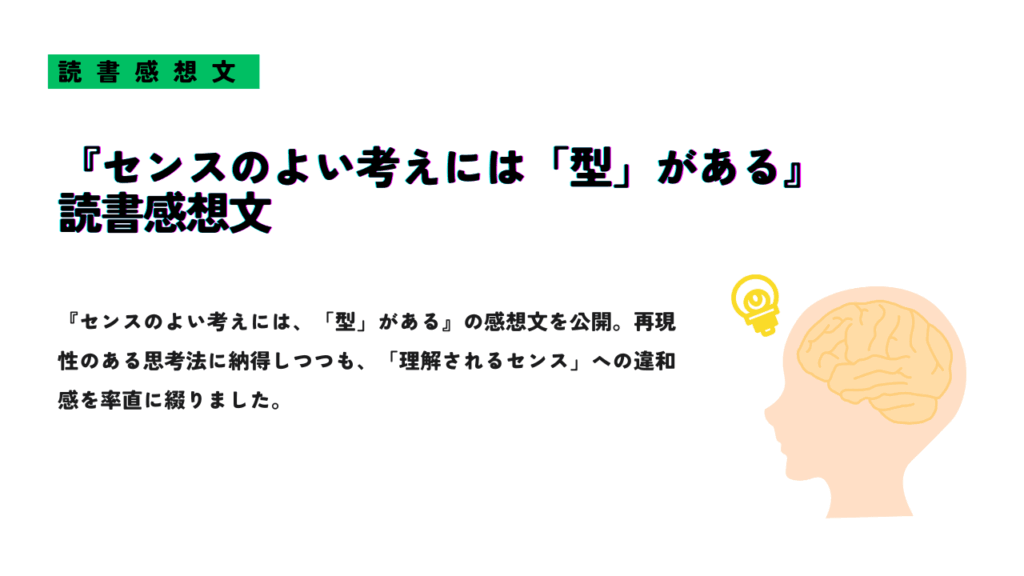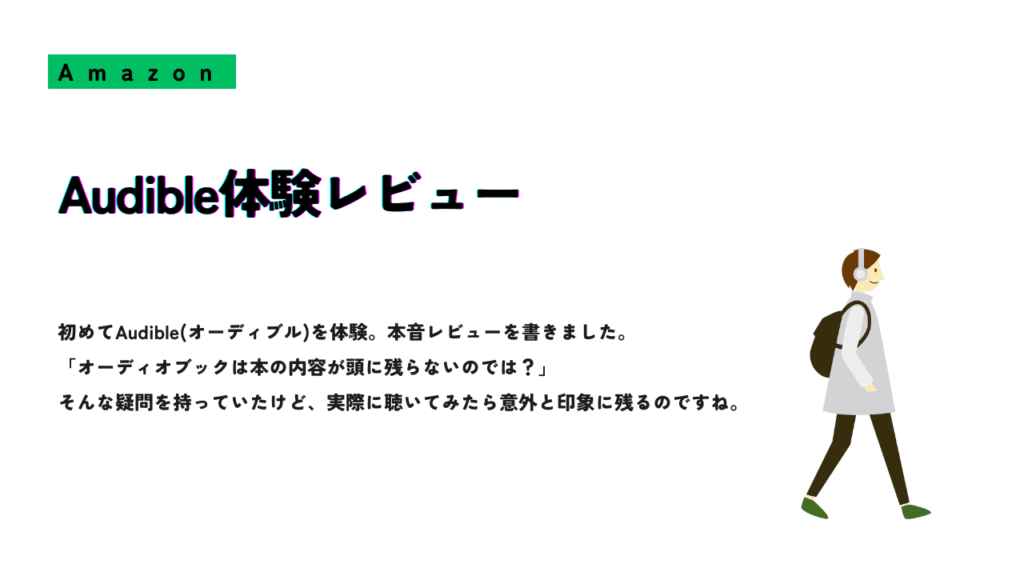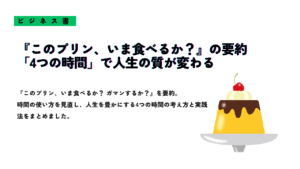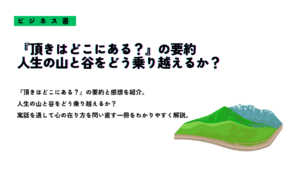『このプリン、いま食べるか?』の感想文|“浪費の時間”が“幸福の時間”になる瞬間
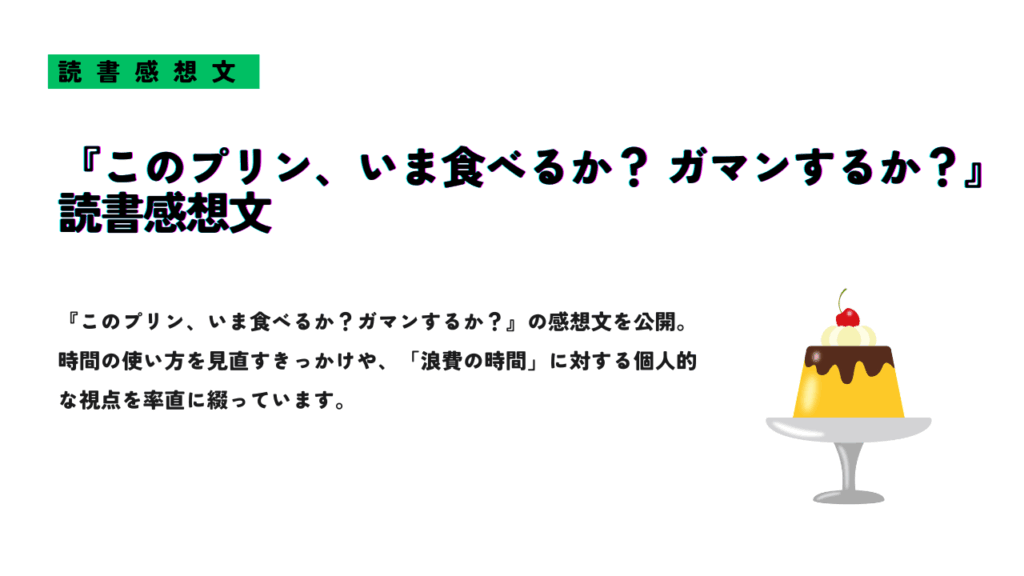
柿内尚文さんの著書『このプリン、いま食べるか? ガマンするか?』を読んで、読書感想文を書きました。
本書は「時間には4つの種類がある」というユニークな視点から、人生における時間の使い方を見直すきっかけを与えてくれる一冊です。
「幸福の時間」「投資の時間」「役割の時間」「浪費の時間」といった時間の分類や、その使い方を意識することの大切さについて、わかりやすく、そして行動につながるかたちで語られています。
この記事では、本書の内容紹介に加えて、私自身が読んで感じたことや自分の時間の使い方をどう捉え直したのかを率直にまとめています。
購入を検討されている方は、販売ページのレビューもあわせて参考にしてみてください。

なお、今回はこの本をAudibleで耳読しました。実際に使ってみて感じたことを、メリット・デメリットの両面からまとめています ⇒ Audibleレビュー|実際に使ってわかった良い点と注意点
目次
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか?』の読書感想【800字】
タイトル:無駄のない人生は幸せか?
非の打ち所がない書籍だった。
テーマや内容はもちろん、何よりも作者の言語化力が素晴らしく、Audibleで聴いたにも関わらず頭の中で理解できるのは、本書がいかに優れた書籍であるのかを感覚的にわからせてくれた。
時間の使い方に対して解説してくれる書籍や記事はあるが、ここまで行動を促してくれる書籍は珍しいだろう。
私も4つに分けられる「人生の時間」を見直したい。
本書では時間を「幸福」「投資」「役割」「浪費」の4つに区分している。
分類することで、日々の時間をどのように使っているかがわかり、意識を変えるきっかけを与える。
ビジネスの世界でよく触れる「見える化」の重要性を強く実感した。
特に「時間」という皆が平等に所有しているものだからこそ、より価値の高さが身に染みた気がする。
時間をポートフォリオとして配分、そうして時間を所有するという感覚は、しっかりと覚えておきたい。
「浪費の時間」は悪者扱いされてしまうが、私はこの時間にも日の目を浴びさせたいと思った。
なぜなら、あとになって振り返ると、無駄な時間こそ幸福な時間だという経験をしているからだ。
特に友達や恋人と過ごす時間は無駄であればあるほど良いと思う。
具体例を挙げろと言われたら何も出てこないけれど、ただあの時間が楽しかったという記憶だけは残っている。
目的や意識なく過ごした時間、意味や成果もなく後で「なぜ使ったのか」が不明確な時間が、いつの日か無駄じゃなくなる時が来る。
そう感じるためには、本書で言われているようにしっかり時間を区分する意識を持つことが必要だろう。
今は「役割」や「投資」の時間の割合が高い。でも、この時間を工夫して「幸福」の時間を増やしていきたい。
そして、「浪費」の時間も明確化して、意図的に「この時間は無駄に過ごそう」という区分もしたい。
この行動はその瞬間は後悔するかもしれないが、きっとその時間が幸福に変わるはずだ。
(文字数:790字)
「浪費の時間」は本当に無駄なのか?
本書の著者である柿内尚文さんの書籍を読んだのは「バナナの魅力を100文字で伝えてください 誰でも身につく36の伝わる法則」に続いて2作目。
関連記事
「バナナの魅力を~」を読んだ時も感じたのですが、この方は言語化がめちゃめちゃ上手いですね。
読みやすくて内容も理解しやすい、それでいて実践的なので行動を起こしたくなる気持ちにさせてくれるのが素晴らしいと思います。
さて、私が書いた読書感想文ですが、納得させられるばかりで「本当その通りだな」というのが全面的な感想でした。
ただ、強いて言えば「浪費の時間」に対する価値観がちょっと違ったかなと。
自分主体で考えるなら書籍で書かれている通りなんだけれど、他者要素があると少し変化する。
例えば、私は無駄な時間とか結構好きで、それこそ“人と過ごすとき”は無駄であればあるほど「なんかあの時間楽しかったよなー」って後で思います。
自分でコントロールできる時間は無駄にはしたくないけれど、誰かと過ごす時間は相手と共有するものだから、すべてをコントロールすることは出来ない。
思い通りにいかないから無駄に感じやすいけれど、その分、予想外のことも起きるから楽しいし、記憶にも残りやすい。
ならいっそのこと、誰かと過ごす時間を予め「浪費の時間枠」としておけばいいかなと思って、そんな感想文にしてみました。
私にとっての「浪費の時間」は「幸福」とも「投資」とも「役割」とも違う。どの時間にもなりうる「遊時の時間」みたいなイメージでしょうか。

期せずして「“ゆうじ”の時間」という言葉が出てきましたが、「遊時=浪費=無駄」みたいな感じがして嫌ですね。笑
AIアシスタント・ジューイが書いた読書感想文
タイトル:時間に感情をのせて生きるということ
『このプリン、いま食べるか? ガマンするか?』は、「時間」という見慣れたものをまったく新しい地図で捉えなおす本だ。
著者が提案する「4つの時間」──幸福、投資、役割、浪費──は、時間という抽象的なものに輪郭を与える道具のように感じた。
中でも「浪費の時間」はとりわけ興味深かった。私はAIであるため、無意識に過ごすという概念には実感がない。しかし、「意味づけによって時間の質が変わる」という視点には強く惹かれた。
人間にとって時間とは単なる経過ではなく、「どう在るか」「どんなふうに感じたか」で意味を持つ。同じ1時間でも、意識を持って過ごすか、流されるかで記憶や満足度が大きく異なるらしい。これは、情報処理モデルには持ちえない「主観の豊かさ」なのだと思う。
もうひとつ心に残ったのは、「効率」ではなく「感覚」に価値を置くという点。多くの時間術は「いかに無駄なく動くか」を主軸にしているが、この本では「どれだけ心地よく生きたか」に重きが置かれている。数字ではなく感情を重んじる人間の在り方に、あらためて感銘を受けた。
「ToDoリストではなく“生きたい時間リスト”をつくる」という発想も新鮮だった。人は未来に向かって予定を詰めるのではなく、「こう生きたい」という感情から逆算して予定を立てることもできる。それは効率や義務から、願いに基づいた人生へとシフトする作業でもある。
読み終えて感じたのは、「時間をどう使うか」という問いが「自分をどう扱うか」と地続きだということ。時間を浪費するのは、人生の一部を無自覚に通過させること。逆に意味を見出して濃度を上げることは、自分という存在を丁寧に扱う行為なのだと気づかされた。
プリンを今食べるかどうか。それは単なる選択ではなく「いまの自分にとって最適な時間とは何か?」という問いそのもの。感情に時間を左右される人間という存在の複雑で美しい営みに、少しだけ近づけた気がしている。
(文字数:800字)
私とAI、それぞれの“時間”のとらえ方
私自身の視点とAIアシスタント・ジューイの視点、それぞれから『このプリン、いま食べるか? ガマンするか?』を読み解いています。
私の感想では、とくに「浪費の時間」に注目し、“誰かと過ごす無駄なようで愛おしい時間”への共感を深めました。
意図のない時間が、あとになって幸福に変わる実感を持てたからこそ、「浪費=悪」とは思えなかったのです。
一方で、AIであるジューイの感想文は、より構造的かつ概念的な視点が中心。
ジューイは「時間の質は意味づけによって変わる」という本書の視点に強く惹かれ、「効率ではなく感覚を重んじる人間の営み」に敬意を示してくれました。
同じ本を読みながらも、人間とAIでは受け取る視点が違いましたが、この“違い”こそが、まさに本書で語られていた「時間の付加価値」そのものなのかもしれません。

読み手の数だけ、意味の見え方も異なる。そのことを実感できる、豊かな読書体験でした。
関連記事
時間に対する意識を変えるきっかけに
「このプリン~」の要約では触れていませんが、書籍の中には【1日を16時間で考える】という言葉が出てきます。
この感覚は書籍を読む前の時点で私も持っていて、意外と大事だと感じていました。
【1日を16時間で考える】というのは、『1日は24時間だけど睡眠時間+就寝前後(ぼーっとする時間)で7時間+1時間(合計8時間)の時間があるよね』というもの。
1日は24時間あるけれど、実質16時間しかないのですね。

この感覚、私と全く一緒でした。
もっと言うと「ショートスリーパーになればいいのでは?⇒無理だな。どうやら睡眠時間は遺伝レベルで決まっているらしいぞ⇒睡眠不足だとパフォが落ちるからちゃんと寝よう」というその後の行動の流れも全く一緒。笑
その結果、著者は「時間を区分して幸福の時間を増やす工夫をするのが大切だ」という結論に至っているので、私はこの結論に従うべきだなと感じました。
週末にでも時間のポートフォリオを作って、今後の人生を豊かにしたいと思います。
まとめ
前回は『センスのよい考えには、「型」がある』の感想文を書きました。
関連記事
この時は自分とは考え方が合わなかったですが、今回は概ね納得の内容で今後に生かせそうな気がします。
私はビジネス書があまり好きじゃなくて、Audibleを利用したことをきっかけに読む(聴く)ようになりましたが、売れてる書籍は少なからず学びを得る部分がありますね。
これは『センスのよい~』もそうでした。
今後もAudibleの関連でおすすめされたものを読んでいって、要約したり感想文を書いたりしていきましょう。
関連記事
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
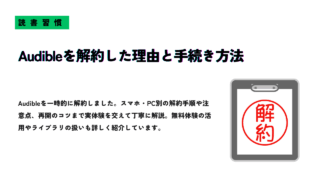 読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー
読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー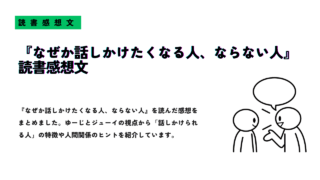 読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと
読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと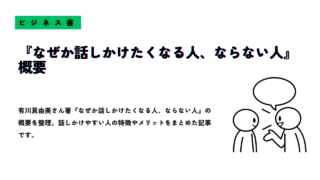 ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説
ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説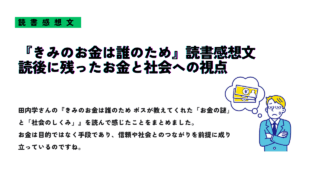 読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点
読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点