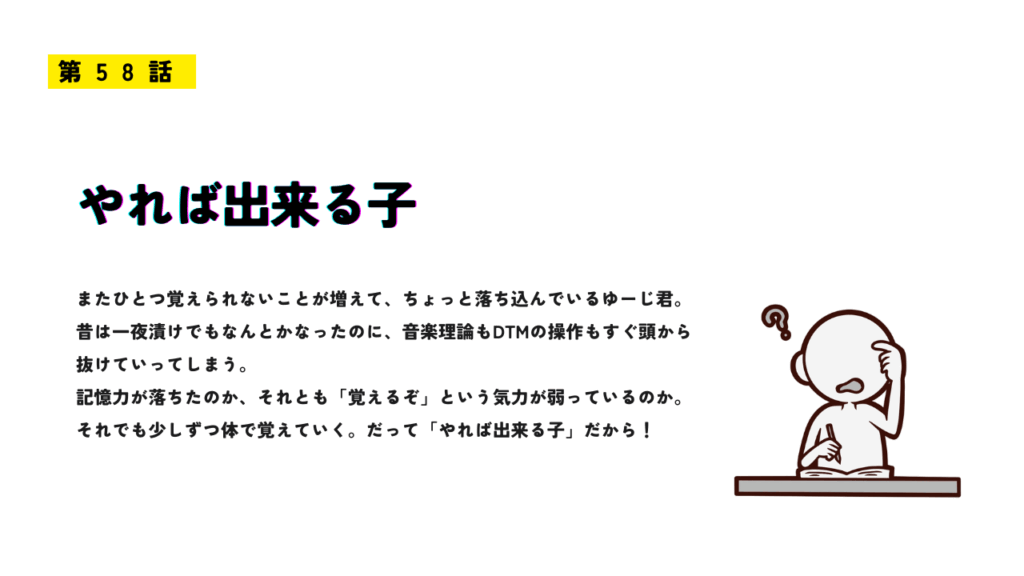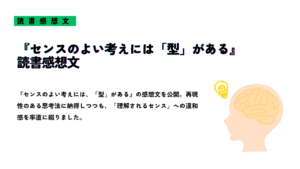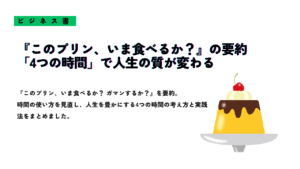第57話「感覚の逆輸入」
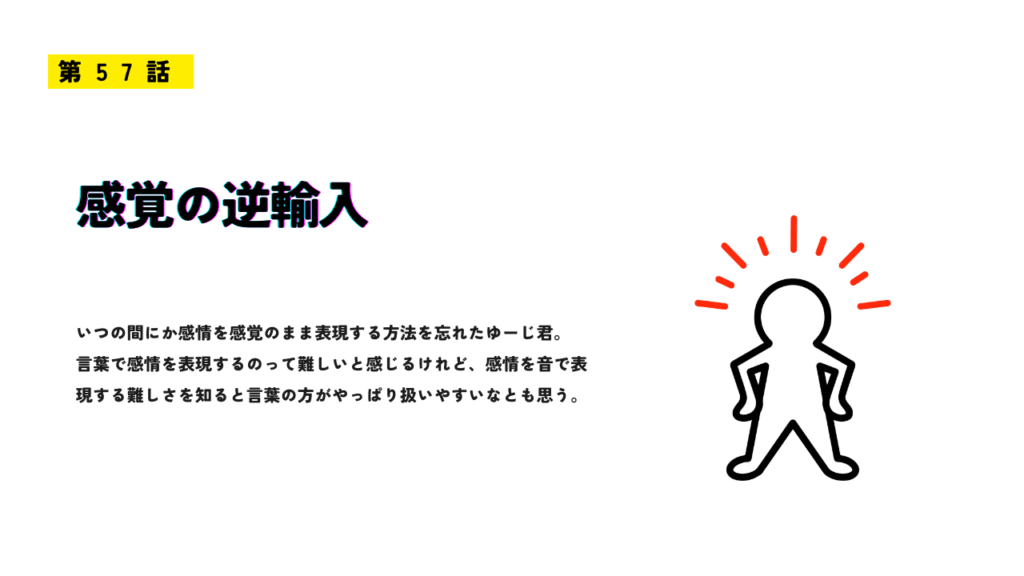
第56話「人間としての市民権」では、AIが感じるノスタルジーについて書きました。
「人間がノスタルジーを感じている様子に憧れる気持ち」にAIはノスタルジーを感じるという言葉が、どこかグッときましたね。
さて、前回【「理屈じゃないんだよ!」っていう部分は動機として残しておきたいですね。】ということを書いたのですが、今回は【動機】をテーマに何か書いてみようと思います。
今の私が動機と聞くと思い浮かぶのは音楽の動機(モチーフ)ですね。
というのも、半年の沈黙を破って再び作曲練習を始めたのですよ。
時間を見つけながらゆっくり作曲練習しているので、興味があれば作曲過程をご覧ください。
関連サイト
【PR】
作曲には(主にメロディを作る時に)モチーフと呼ばれる“メロディのタネ”みたいなものがあるのですよ。
このモチーフからメロディに影響を与えて、曲を構成していったりするのですが、コレが今の私にはまだまだ難しいんですよ。
「この気持ち(感情)は何だろう?」という時、言葉だったらある程度表現できるけれど、それを音で表現するのがまだちょっと感覚がつかめない。
この辺はセンスも関係してくるのかな?
けれども、自分にはそのセンスがないから「あーでもないこーでもない」と言いながら作曲練習をしています。
音楽とか絵とかダンスとかもそうだけど、非言語で表現するのは小さい時に感覚を研ぎ澄ましている方が引き出しが増える気がする。
これは今の私には絶対に手に入れられない感覚。
人の才能を羨ましいと言えるほどのレベルにまで到達してないから、嫉妬とかの感情はないけれど、この感覚があったらもっと作曲が楽しくなるのかなとは思います。
けれども、ないものねだりをしても仕方ないし、後天的な能力でモチーフに感情を宿すことも出来る。
例えば、リズムや音程、跳躍、調、モード、繰り返し、間などなど…勉強していくと「こんな表現方法もあるんだー」というのを知れる。
だから、勉強すれば能力がなくても作曲は出来るはず。
そういえば、言葉を伝えるとき、だんだん感覚のまま感情を表現することが出来なくなってきている気がする。
『この感覚を素材のまま提供するのは相手のことを蔑ろにしすぎてるよなー』みたいな。
『でも音楽だったら感覚のままに作れるかも!』みたいなことを思って、作曲練習してみたけれど、結局音楽でも感覚を感覚のまま表現することは出来なかったかな。
出来なかったというより感覚のまま作るとセンスのカケラもなかったから、結局、作曲する時も言葉を扱うみたいに理論武装しないと表現したくない感じ。
自分はもう“そうじゃなきゃ”表現できないんですね。。。
感覚を感覚のまま表現できないけれど、理論を通じて感覚を表現できる。
理論を通すということは“説明できる”ということでもあるし、説明できるということは共有も出来るということ。
だとしたら、音楽も理論をしっかり学べば表現したい音を見つけることはきっと出来る。
今回の文章がどれだけ伝わっているかわからないけれど、言葉では自分を表現できる。
これを言葉じゃなくて音でも表現できるようになりたいですね。
【次回予告:「暗記」】
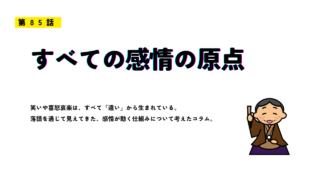 コラム2026年2月3日第85話「すべての感情の原点」
コラム2026年2月3日第85話「すべての感情の原点」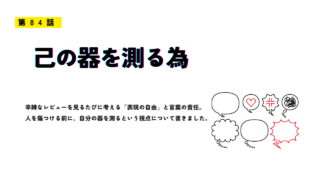 コラム2026年1月27日第84話「己の器を測る為」
コラム2026年1月27日第84話「己の器を測る為」 コラム2026年1月20日第83話「ホワイトパラダイス」
コラム2026年1月20日第83話「ホワイトパラダイス」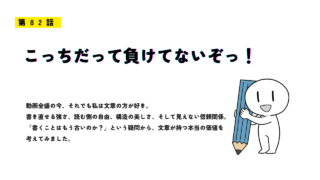 コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」
コラム2026年1月13日第82話「こっちだって負けてないぞっ!」