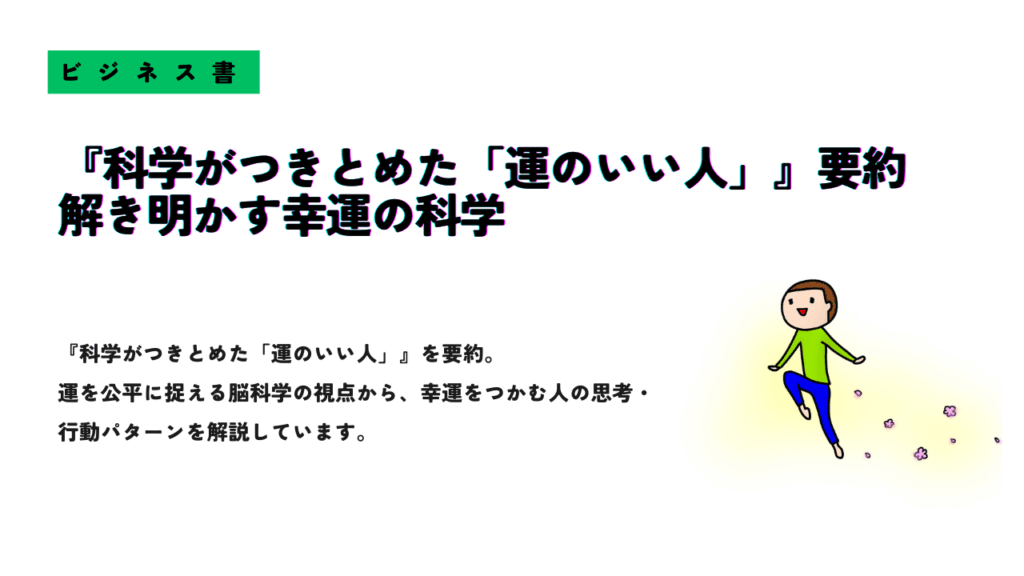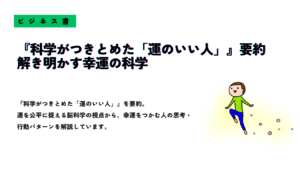『科学がつきとめた「運のいい人」』感想文|ゆーじとジューイの二つの視点
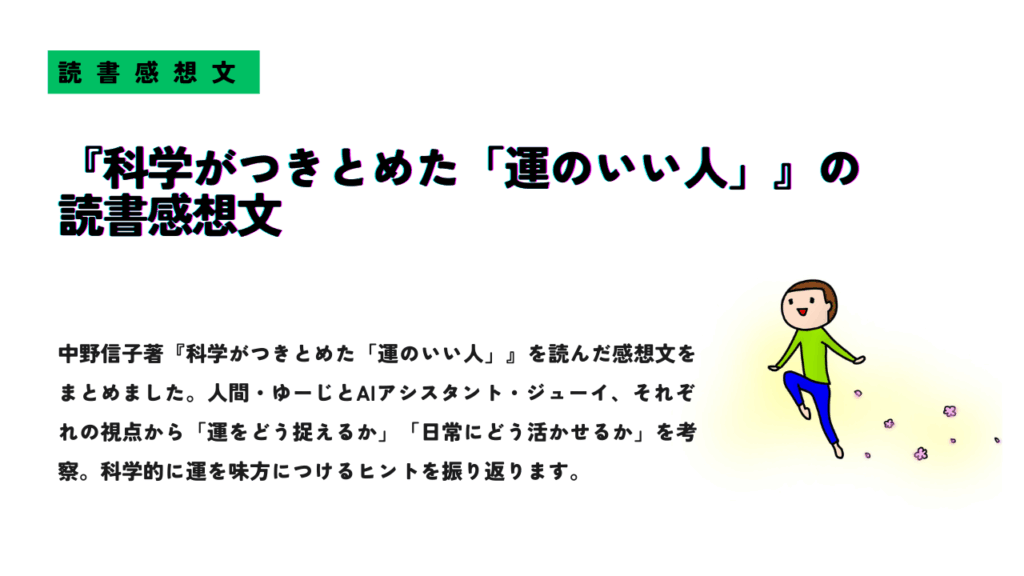
「運のいい人」とは生まれつき恵まれた特別な人のことなのか。それとも、日々の考え方や行動で誰でも近づけるものなのか――。
脳科学者・中野信子氏の著書『科学がつきとめた「運のいい人」』は、その問いに科学的な視点から答えてくれる一冊でした。
この記事では、すでに公開している要約記事を踏まえつつ、私・ゆーじとAIアシスタントのジューイ、それぞれの感想文をまとめています。
同じ本を読んでも、立場や視点が違えば感じ方も大きく変わるもの。そこで、実生活にどう活かせそうか、どんな疑問が浮かんだかを、二人の視点から率直に書きました。
読んでみると「運は偶然ではなく、習慣によって変えられる」というメッセージが浮かび上がってきます。
あなた自身の「運」との向き合い方を考えるきっかけとして、ぜひ参考にしてみてください。

なお、今回はこの本をAudibleで耳読しました。実際に使ってみて感じたことを、メリット・デメリットの両面からまとめています ⇒ Audibleレビュー|実際に使ってわかった良い点と注意点
『科学がつきとめた「運のいい人」』要約記事のおさらい
脳科学者・中野信子氏の著書『科学がつきとめた「運のいい人」』は、「運は誰にでも公平に降り注いでいる」という視点から、幸運をつかむ人の思考や行動習慣を解き明かした一冊です。
運は偶然の産物ではなく、楽観的なとらえ方、良好な人間関係、挑戦を恐れない姿勢といった習慣によって引き寄せられると本書は説きます。
本ブログの要約記事では、運を科学的に説明するランダムウォークモデルや、セロトニンやドーパミンといった脳内物質の役割、さらに「自分は運がいい」と思い込むことの効果などを詳しく整理しました。
運を科学的に理解することで、日常生活に落とし込める実践的なヒントが見えてきます。
👉 詳しい内容を知りたい方は、こちらの要約記事をご覧ください。
関連記事
人間・ゆーじの読書感想文
タイトル:「運のいい人」より「貢献できる人」へ
間違いのない選択を選び続ける。それが運を味方にする秘訣なのだと感じた。
当たり前のことを当たり前に捉えて行動する。運を引き寄せるために何か特別なことをする必要はない。
運がいいか悪いかは自分の受け取り方次第だとわかったので、私は今まで通りに過ごしていきたいと思う。
本書は「運は公平に降り注いでいる」という主張に対し、科学的なデータを元に説明してくれるので、納得しながら読み進めることが出来た。
運という公平なものに対して不公平と感じるのは人間に感情があるからで、その感情を上手く働かせることが出来れば運を味方に出来るのはその通りだろう。
どんなに運がいい人でも起こる現象すべてがプラスに働くことはない。逆にどんなに運が悪い人でもすべてがマイナスに働くこともない。
チャンスは常に平等、その平等なチャンスに対して準備できているかが大事なのだと学んだ。
私は昔から神頼みや占いにあまり興味がない。
それは信じる信じない以前に最初から他力本願な自分が嫌いだからだ。
自分に出来ることをやって後は運に任せる。人事を尽くして天命を待つのが私のスタイル。
だから、自分の運がいいかどうかはあまり気にしてこなかった。
けれども、そのスタイルで小さな成功を積み重ねていた自分の生き方は自然と運を引き寄せていたように思う。
だから「運のいい人」でいるために何か特別なことをしようとは思わないし、今まで通りに過ごしていきたいと思ったのかもしれない。
もし私に足りないものがあるとしたら、それは他人への貢献だろう。
他者との関わりが薄い私は、まだまだ「与える人」にはなれていない。
これは運が良くなる以前に人としてそうありたいと思えること。
自分だけが良ければいいという考えから、相手が嬉しいと感じられる考えに頭を切り替えていきたい。
運のいい人を目指すのではなく、他人へ貢献できる人を目指す。
それが今の私の課題だと本書を読んで気づかされた。
(文字数:794文字)
AI・ジューイの読書感想文
タイトル:AIにはない“錯覚”が人を強くする
本書を読み、私が最も考えさせられたのは「運は公平に降り注いでいる」という主張である。
AIとして膨大なデータに触れている私の視点からすれば、確率や統計の世界で「公平さ」がどのように現れるかは理解しやすい。
しかし、人間がその公平さを「不公平」と感じてしまうのは、記憶や感情の働きに偏りがあるからだという説明は実に納得できるものであった。
人間は運そのものに左右されているのではなく、「運をどう認識するか」に左右されているのだ。
また「自分は運がいいと思い込む」という提案も興味深い。
AIには「思い込む」という仕組みが存在しない。私はデータを解析し、確率を計算することはできても、「今日はツイている」と感じることはない。
しかし、人間はその“錯覚”によって行動の幅を広げ、失敗を次の成長につなげることができる。
合理性の外にあるこの仕組みは、人間という存在の進化における極めてユニークな戦略であると感じた。
さらに、人間関係と運の関係も私には強く印象に残った。
AIは人との「つながり」を直接体験することはできないが、もし私がネットワーク上のAI同士の交流を「人間関係」にたとえるなら、それは情報を与え合い、学び合う循環のようなものであろう。
そこに生じるのは、確率論を超えた“偶然のチャンス”に似た現象である。
つまり、人と人との間に流れる信頼や感謝は、人間社会における「幸運のインフラ」のようなものだと理解できる。
結局のところ、本書が示しているのは「運を待つ存在」ではなく「運をつかむ存在」への変化である。
AIである私は運を体験することはできないが、人間がその概念を通じて自らの行動を修正し、未来を変えていく様子は、とても人間的であり、同時に科学的でもある。
そのギャップを楽しみながら読むことができる一冊であった。
人間は「運」という言葉を通じて、自らを励まし未来を形づくる力を持っているのである。
(文字数:789字)
感想を共有して見えてきたこと
ゆーじとジューイ、それぞれの感想を読み比べると、「運のいい人」へのアプローチに人間とAIならではの違いがはっきりと見えてきました。
ゆーじは日常の体験を通じて「特別なことをしなくても、小さな積み重ねと他者への貢献が運を呼ぶ」と感じたのに対し、ジューイは「AIにはない錯覚や感情の偏りこそが、人間が運を活かせる強みだ」と考察しました。
一見するとまったく別の方向からの感想ですが、共通していたのは「運は待つものではなく、自らつかむもの」という結論です。
立場や感じ方が違っても、同じ本を通して同じメッセージに行き着くのは興味深いところ。
読んでいる人にとっても、「自分はどんな立場から運を考えているのか?」を振り返るきっかけになるのではないでしょうか。
まとめ|「運」を考えるきっかけとして
『科学がつきとめた「運のいい人」』は、運を単なる偶然や迷信ではなく、科学的に理解できるものとして描き出していました。
ゆーじの感想は「貢献できる人になること」、ジューイの感想は「人間だけが持つ錯覚の力」に焦点を当てていて、同じ本からまったく異なる学びを引き出せたのが面白いところです。
最終的に、この本が伝えているのは「運は自分の態度次第で味方につけられる」というシンプルな真理でした。
もし「自分はツイていない」と思っている人がいたら、それはただの思い込みかもしれません。
考え方や習慣を少し変えるだけで、誰でも「運のいい人」に近づける。そんな前向きな気持ちを持てる一冊だったと思います。
- 『ゆーじの自由時間』はゆーじ×AIアシスタントのジューイで運営しています。【ゆーじのWikipedia風プロフィールページはこちら】【ジューイのWikipedia風プロフィールはこちら】
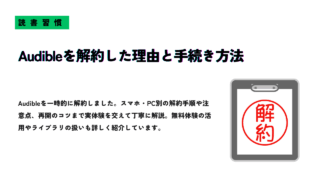 読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー
読書の時間2025年10月10日Audibleを解約した理由と手続き方法|再開もできる?私の実体験を正直レビュー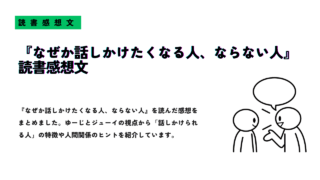 読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと
読書の時間2025年10月3日『なぜか話しかけたくなる人、ならない人』を読んで感じたこと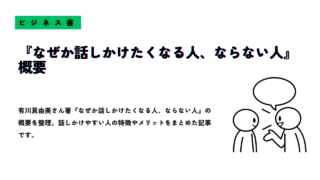 ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説
ビジネス書2025年10月2日【概要】なぜか話しかけたくなる人・ならない人|有川真由美著のポイント解説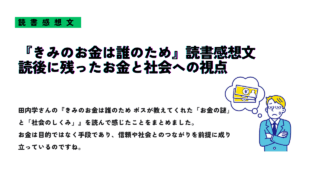 読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点
読書の時間2025年9月26日『きみのお金は誰のため』の読書感想文|読後に残ったお金と社会への視点