グリム童話編5回目は『オオカミと七匹の子ヤギ』の簡単なあらすじと読書感想文を書きました。
この物語は子供の頃に読んでなんか好きだった作品でした。子供と子ヤギの立ち位置が似ていたからかもしれません。わかりやすい教訓もありますが、そこではない部分に着目して感想文を書いています。
『オオカミと七匹の子ヤギ』の簡単なあらすじを確認してみよう
感想文の前に、まずはいつも通り『オオカミと七匹の子ヤギ』の簡単なあらすじを確認していきましょう。
ある所にお母さんヤギと7匹の子ヤギが暮らしていた。ある日、お母さんが森へ食べ物を取りに出かけるために、子ヤギたちにお留守番を頼んだ。その際、「けっしてオオカミを家に入れてはいけないよ」と警告する。
お母さんが出かけて間もなく、オオカミが子ヤギたちの家にやってくるが、ガラガラの声や黒い足を見た子供たちに見破られてしまう。
オオカミはチョークを頬張り声を変え、小麦粉を塗って足を白くしたことで子供たちを騙し家へと侵入。子ヤギたちは家の中のあらゆるところに隠れるが、柱時計の中に身を潜めた末っ子ヤギ以外の6匹は丸呑みされてしまった。
末っ子から事の顛末を聞いたお母さんは、木のかげで寝ているオオカミを見つけるとハサミでお腹を切り、6匹の子ヤギたちを救出。オオカミのお腹に石を詰めて縫い合わせる。オオカミが目覚め、井戸に行って水を飲もうとしたが、お腹の重さによって井戸の底へ落ちてしまったとさ。
(オオカミと七匹の子ヤギの詳しいあらすじはコチラで確認:インターネットの電子図書館-青空文庫)
改めて読んでみるとちょっと怖い部分もありますが、子供に読ませたい物語のように感じます。
親の言う事を守らないといけないことや疑うことの大切さ、オオカミ目線になってみると、失敗しても何度もチャレンジする精神力なんかも教訓として学べそうですね。
『赤ずきん』の読書感想文の時もそうだったけど、「グリム童話、オオカミの腹に石入れがち」だな。笑
RGさんがこのあるあるを歌ってくれたら嬉しいですね。ピンクレディーの『SOS』あたりで(^^♪
では、オオカミと七匹の子ヤギの簡単なあらすじを確認したところで、感想文を書いていきたいと思います。
『オオカミと七匹の子ヤギ』の読書感想文-提出作品
魅力を感じる人物や物語は「一人・一つの存在にも関わらず、あらゆる視点を持つことができたり、表層だけではない深層にも働きかける何かを持っている」から魅力的だと私は思う。そして、『オオカミと七匹の子ヤギ』はその魅力を持っている物語だと感じた。
この物語を読んで感じるのは「親の言うことを聞きましょう」という教訓があるということ。それは子供向けの絵本になっていることからもわかることかもしれない。また、子ヤギ目線で考えると「疑うことも必要だよ」、オオカミ目線で考えると「何度も挑戦すると道が開けるよ」というメッセージも感じられた。
『オオカミと七匹の子ヤギ』という一つの物語で、あらゆる視点で考えられるから魅力に感じたのだろう。
ただ、『オオカミと七匹の子ヤギ』の魅力はそれだけではない。表層だけではなく深層にも働きかける『何か』も持ち合わせている。
その『何か』とは『目先の情報(利益)にとらわれると、物事の本質が見えなくなってしまう』ということ。
お母さんは子ヤギたちに「オオカミを家に入れてはいけない」と言い、その際に「姿を変えてくるけれど、声はガラガラで足は真っ黒だからすぐに見分けはつく」と言った。その後、オオカミが家にやって来る。子ヤギたちは声色や足の色の違いに気づいてオオカミが騙しに来たとわかるのだが、声を変え、足の色を変えたオオカミには気づかずに家に入れてしまった。
つまり、目先の情報だけで判断してしまったのだ。けれども、お母さんは「姿を変えてくる」とも警告していた。にも関わらず、家にオオカミを入れてしまったのは子供たちが「オオカミは姿を変えてくるかもしれない」という事を忘れてしまったからだ。
目先の情報にとらわれると、それ以外の情報を遮断してしまう。『オオカミと七匹の子ヤギ』の本当の教訓はココに隠されていると感じる。そして、物事の本質がココにある。物事の本質は、上辺だけを切り取って判断している人には見えていない。
目で見る情報、耳から聴こえる情報をそのまま受け取るだけでは誰もが子ヤギと同じ運命をたどってしまうだろう。人である以上、情報の裏には経緯や背景、意図など「なぜその情報が発信されたのか」という理由があることを忘れてはいけない。知識と知恵を与えられたのだから。
物事には必ず「なぜ」が隠れている。私は常に「なぜ」を考えられる人でありつづけ、受け取った情報を自分なりに解釈して行動を起こしたいと思う。
(1006文字)
本質は考える人にしか見えない
言葉の意味は分かるけど、説明しろと言われたら意外と表現できなかったりしませんか?
手前味噌ですが、私は考える事に関しては秀でている方だと思います。その一方で、表現することに関してはかなり劣っています。なので、本質とは何かというのはわかっているつもりですが、如何せん上手く表現できません(;´・ω・)
ただ、『オオカミと七匹の子ヤギ』を読んで「この表現できない感覚は本質に迫っているんだろうな」と感じました。
『本質』は人や物事には必ず存在するけれど、簡単には見えない。考えないと辿り着けないものだから人は常に考えないといけないでしょう。
ネット記事や有名人の発言、今はちょっと気になった情報はすぐに手に入れられます。そして、その情報に対して誰でも自分の意見を発することができます。
でも、受け取った情報に対して『考えて発している人がどれだけいるのか?』を疑問に感じることも増えてきました。
『考えて発する』というのは、文章や発言を受け取って自分の意見を発することではなく、「相手は何でそう言ったのか?」「相手はどういう人物なのか?」「相手はどういう環境にいたのか?」「相手はどのくらいの温度で話したのか?」「相手は誰に向けて話したのか?」など、文章を書いたり発言をした『相手』を考えて初めて成り立つものだと思います。
相手のことを考えないで自分の意見を言っても、それは意見ではなく暴言。ただ相手を傷つけてしまう場合もある。
『考える』ことは独りよがりでいいけれど、『考えを発する』ことは相手が存在することを理解していないといけない。ココを間違えると中身のない発言になってしまったり、情報を鵜呑みにしてしまって本質がわからない浅い考えの人間になってしまうだろうなーと。
私は日本語が好きなのですが、それは言葉一つでもいろんな意味を持っているから。そして、文章にすると日本人ならではの察しや思いやりを感じ、時に皮肉も言えるので、表現することが苦手な私にとって日本語の曖昧さはすごく重要なのですね。
なので、すぐに炎上する最近の文化が悲しいです。炎上するのは『読む側の読解力が下がっているから』と考えていて、文面や発言だけ切り取って、受け取った情報だけで物事を判断しているのだろうなと。
でも、大事なのは『受け取った情報の背景はどうなっているのか?』を意識することで、そこに意味があるとわかれば相手がなぜその主張をしたのかもわかります。
一定の理解ができれば心無い暴言を吐くことも少なくなっていくのかなと期待しています。
一方で、人の心を動かすのは感情ですから、喜怒哀楽を前面に出して表現することは大切だと思います。でも、その出し方はもっと場面を選んでもいいのかなと。
スピード重視の世の中になっているからなのか、現実世界の不満をネット上でしか発散できないからなのか、それぞれ相手の環境があるので何とも言えない部分はありますが、もっと時間をかけて考えてもいいんじゃないかなーと思ったりします。
曖昧さが魅力の日本語だからこそ、考える余裕を持つと見える世界も変わるのかもしれませんね
もちろん、読解力がないのはごく一部で、そこに日和見の人がごく一部ついていって、それで盛り上がってるだけ。
ほとんどの事は100人いたら数人が火種をまいて、数人が拡散して、そこを切り取るメディアがあって大衆化させるから、自分のところに情報が届く頃には炎上という枕詞がついて情報がお届けされるでしょうね。
けれども、自分がしっかり考えることができれば本質は見えてきますし、受け取った情報を鵜呑みにしたり、振り回されたりすることはなくなると思います。人の姿が見えなくても『画面の向こうには人がいる』ということを、もっと感じられたら傷つく人は減りそうな気はしています。
私は今は文章を生業にしていますし、文字から温度が感じられるくらいの表現力を身に着けられるように精進しないとですね (-ω-)

結局末っ子が一番得をする
『笑っていいとも!グランドフィナーレ』のキーマンは石橋でしたが、『オオカミと七匹の子ヤギ』のキーマンは末っ子じゃないですか?
もし末っ子がオオカミに見つかっていたら子ヤギたちは全滅していたわけですし、ファインプレーでした。
童話には兄弟が登場する話があったりしますが、意外と末っ子や小さい子が活躍する話もありますね。『三匹の子豚』なんかは末っ子がレンガの家を作ってお兄ちゃんたちを助け、オオカミをやっつけます。
末っ子というのは年下で力が弱いというイメージがあるので、ちょっと出来ただけで「すごい!」となるんですね。
また、スポーツ選手では末っ子が多いと言われていますが、それはすぐ近くにお手本になる姉や兄がいるからでしょう。
末っ子は上の兄弟を見ているので非常に要領がよく、強かに生きていく。さらに言えば責任感も薄く、自由奔放。なんだかんだ一番得をするのは末っ子だと思います。
…本当いい身分ですよねー、末っ子は。
まぁ私、末っ子なんですけど(´艸`*)
★グリム童話の読書感想文まとめ



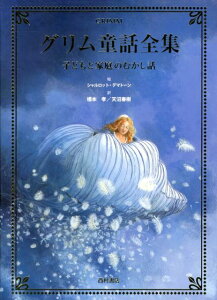


コメント