11回目に入った読書感想文ですが、今回からはグリム童話篇として10回に渡って毎週感想文を書いていきます。
グリム童話篇1回目は『ヘンゼルとグレーテル』。
『目印のパン』『お菓子の家』など断片的には知っていますが、「魔女っていい人だったっけ?」「始まりと結末を覚えてないなー」という状態だったので新鮮な気持ちで読むことができました。

今回からは今までの文字数制限の縛りを解除して自由に書いていきますね。

ヘンゼルとグレーテルの読書感想文【ヨーロッパ版『姥捨て山』が伝える2つの違い】
ヘンゼルとグレーテルを読むとヨーロッパと日本の違いを感じることが出来る。私が感じたのは2つ。1つは『文化』の違いだ。
ヘンゼルとグレーテルの物語を一言でまとめるなら「子どもの成長の物語」と言えるだろう。危機的状況に追い込まれた時にヘンゼルは月明かりに光る石をヒントに森に置いてかれたピンチを乗り越えた。
また、グレーテルは魔女によって釜土の中に入れられそうになったことを察し、その考えを逆用することで魔女を出し抜いた。
このように兄妹がそれぞれ機転を利かすことでピンチを乗り越えることで、一回り成長して家に戻ってくることからも「子どもの成長」を物語としているのが分かる。
一方で、日本の昔話は桃太郎など子どもが主役の物語はあるが、その成長過程を描写しているものはほとんどなく、教訓を伝える物語が多い。このことから、ヨーロッパの文化は『体験』を重視することがわかり、日本は『教え』を重んじる文化だと分かるだろう。
また、もう1つの違いは『地形』について。
ヘンゼルとグレーテルは森が舞台になっている。森の中にはお菓子の家があったり、魔女が住んでいたり、異界の象徴として森が大きな役割の一つを担っていることが読み解ける。グリム童話が誕生したドイツは、広大な平地が広がっていて多くの森に恵まれている国であるのは周知の事実であろう。それはドイツが環境先進国であることからも理解できるはずだ。
一方、日本は国土の多くが山岳地帯である。日本には数多くの山脈や名峰があり、世界遺産としても有名な地域もある。ココから推測すると、ヨーロッパにとっての『森』と言うのは日本にとっての『山』であるということが言えるのではないだろうか。
そこに気づくとヘンゼルとグレーテルが日本のある物語と類似していることに気づく。それは『姥捨て山』だ。『姥捨て山』は親が捨てられる道すがらに小枝を折り、それは息子が帰り道で迷わないようにするためという優しさに心打たれる物語で、人を想う大切さの『教え』がある。
ヘンゼルとグレーテルは言うなれば『子捨て森』だ。捨てられた子どもがどうやって危機を乗り越えるか、その『体験』に物語の面白さを込めている。
以上のことから、ヘンゼルとグレーテルはヨーロッパと日本の『文化』や『地形』の違いを示す歴史的な価値がある物語の一つということが言えるだろう。
(965文字)
読書感想文の考察と解説

新しくグリム童話編に入ったということで前回までの『日本昔話編』とはちょっと違った視点で今回は感想文を書いてみました。
まず、ヘンゼルとグレーテルを読んで感じたのは『既視感』でした。「どこかで似たような話を聞いたことがある…」と思ったのですが、何度か読み返すうちに「“姥捨て山”に似てるのかな?」と気づきました。
そこから、グリム童話という日本昔話とは違った視点で書かれているのが面白いと思って、ヨーロッパと日本の文化の違いを意識して感想文を書いたのですね。
日本昔話は『教訓』が重視されていましたが、ヘンゼルとグレーテルは『体験』が重視されていて、そこに日本とヨーロッパの考え方の違いが表れていてすごく面白かったです。
『教訓』を重視する日本昔話は、ルールを守るという日本人の真面目さが反映されている気がしますし、『体験』を重視するグリム童話はヨーロッパ人(外国人)の積極性が映し出されている気がしました。
童話からそれぞれの国の文化の違いを感じられたのは、物語そのものの面白さ以外の面白さを感じられましたね。
また、もう一つ面白かったのが森を舞台にしているところ。
日本昔話はほとんどが海か山が舞台でしたが、ヘンゼルとグレーテルは森や湖の描写がありました。
ここで改めて「日本って島国で山に囲まれているんだなー」と気づけて、当たり前を再確認できましたね。
民俗学などの文献を軽く調べると、日本では山に鬼や妖怪がいるようにヨーロッパでは森に魔女や妖怪がいる話が多いみたいです。
文化の違いは地形の違いも少なからず関わっているのでしょうね。
地形の違いが物語の違いを生むというのはヘンゼルとグレーテルを読まないと気づけないことだと思うので、ヨーロッパと日本の歴史や違いを学ぶ上でもヘンゼルとグレーテルは価値のある物語だと感じました^^
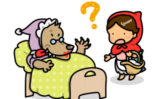
ヘンゼルとグレーテルの簡単なあらすじ
ヘンゼルとグレーテルの簡単なあらすじを書いておきます。
「継母が子どもを捨てると言ったときお父さんはどうして止められなかったのか?」「お菓子の家から自宅までなぜすんなり帰れたのか?」など疑問に感じる部分はたくさんありますが、この粗さが昔話の特徴でもありますから気にしてはいけませんね^^
簡単にあらすじを確認したところで、この物語の教訓と呼べる部分を確かめてみましょう。
ヘンゼルとグレーテルが伝える教訓は『困難は協力して乗り越える』こと

ヘンゼルとグレーテルの教訓は、切り取り方でいろんな解釈ができます。
例えば、『諦めないで行動することで道が開ける』とか、『誘惑に負けない』とか、他にもどの部分に着目するかで教訓と言える部分は変わってくるでしょう。
ですが、私が実際にこの物語を読んで感じた一番の教訓としては『困難は協力して乗り越える』ということです。
もし、ヘンゼルとグレーテルのどちらかだけがこの体験をしていたら、きっと生き残ることは出来なかったでしょう。それは、それぞれに別の役割があったから。
もしヘンゼルが機転を利かせなければ一度目で家に帰ることは出来なかったし、グレーテルに勇気がなければお菓子の家から脱出することは出来なかったはず。
ヘンゼルは知恵の象徴、グレーテルは勇気の象徴と言ったところでしょうか。
「2人が協力したからこそ、困難な状況を乗り越えることができたのではないだろうか?」そんな風に私は考えて、これこそが一番伝えたかった教訓になるのかなと感じました。
原作は怖すぎた?真実がベースのリアルすぎる物語

昔話は子どもでも読めるように表現や描写を変えていると言われていますが、ヘンゼルとグレーテルもそういった変更がされているようです。
原作の物語はかなり怖く子供の教育上良くないということで、どんどん改編されていき、子供でも読めるような物語になってきました。
なぜヘンゼルとグレーテルの物語が怖すぎると言われているのかですが、それは『もともと現実に起きていたことが話のベースになっている』から。
ヘンゼルとグレーテルは子どもを捨てるところから物語が始まりますが、これは実際に中世ヨーロッパで起きた大飢饉(1315年から1317年の大飢饉)のことだとされています。
親が口減らしのために子どもを犠牲にした歴史があり、それを伝えるために作られたとされています。
物語の面白さに目が行きますが「なぜこの物語が作られたのか?」を知らないで満足してしまうのは、負の歴史を学ばないことになりかねないので、無知の怖さがありますね。
ヘンゼルとグレーテルは実際に起きた出来事を伝えているという側面がある。真実がベースになっているから余計に怖いと感じるのですね。
魔女の正体は母親だった?
怖いついでに、もう一つ驚く説もあります。それは『魔女の正体は母親だった』ということ。
私が読んだものは継母が子どもを捨てたと書かれていましたが、原作では継母ではなく実母だったそうです。
ですが、「実母だと話が怖すぎる」「教育的に良くない」ということで、継母に変えられたと言われていました。
ただ、これも親が口減らしのために子供を犠牲にした歴史を知ると、確認は出来ていませんが「おそらくそうだったんだろうな」と推測はできますね。
私が読んだヘンゼルとグレーテルは『家に帰ると意地悪な継母はすでに死んでしまっていた』と書かれているだけで、何で死んでいたのかわかりませんが、もしかしたらあの魔女は継母だったのかもしれません。
もし、そうだったらグレーテルがやっつけた魔女は自分の親だったということになりますから、また別の物語が始まりそうですね。笑
ヘンゼルとグレーテルのその後はどうなった?
「また別の物語が始まりそう」なんて思ってたら、実はヘンゼルとグレーテルのその後を描いた映画が2013年にアメリカで制作されていたみたいですね。
あの出来事から15年後、2人は魔女ハンターとして活躍していた。ある日、子どもの誘拐が頻発する村から事件の解決を依頼されるが…。
といった感じで、ジャンルで言ったらアクションホラーになっています。
グロいシーンもあって、私はちょっと苦手な部分もあったのですが、まぁ面白いと思いますよ。Amazonプライムで視聴できるので興味のある方はぜひ^^
★グリム童話の読書感想文まとめ




コメント