映画『スタンドバイミー』が金曜ロードショーで放送決定!(放送日は2021年5月28日でした)
名作映画と呼ばれる『スタンドバイミー』。でも実は私いままで一度も観た事がなかったのですよ。
なので、放送を楽しみにしていたのですが…我慢できなくて先ほどAmazonプライムビデオで視聴しちゃいました(´▽`)テヘッ
地上波放送よりも一足先に、『スタンドバイミー』の感想文やなぜ名作と呼ばれているのか?などを自分なりに考察してみましたが、確かにこの映画は『不朽の名作』だと感じますね(´▽`*)
スタンドバイミーのあらすじ
1959年オレゴンの小さな町。文学少年ゴーディをはじめとする12才の仲良し4人組は、行方不明になった少年が列車に轢かれて野ざらしになっているという情報を手にする。死体を発見すれば一躍ヒーローになれる!4人は不安と興奮を胸に未知への旅に出る。たった2日間のこの冒険が、少年たちの心に忘れえぬ思い出を残した……。
あらすじを簡単にまとめるなら、少年たちの成長の物語かな。
成長というのは友情や冒険など、いろんな要素をひとまとめにしたイメージですかね。
簡単にあらすじを確認したところで、感想文をご覧いただければと思います。
『スタンドバイミー』の感想文
観終わった時、私は自分が大人になっていることに気づく。
そして、すごく幸せな気分と脱力感でしばらく物思いにふけた。
切り取る場面によって物語の印象は変わるけれど、最後に残るのは彼らを通じて思い出す自分が少年だった頃の懐かしい気持ち。
この気持ちを上手く表現できないけれど、ずっとそばにいて欲しい形のない何かであることは間違いない。
『スタンドバイミー』は人間関係や社会構造、時代背景などあらゆる点で負の側面が凝縮されている。
その中で少年たちが自分の感情と向き合いながら冒険する姿は、たくましくもあり、希望の存在のようにも感じた。
死体を探しに行くというただの好奇心だけで楽しめる愚かさも、行き当たりばったりで行く先を決める無謀さも、彼らが本気で挑んでいると気づくだけで優しい気持ちになれてしまう。
それは彼らがまだ少年であること、そして友達と一緒だったから余計にそう感じてしまうのかもしれないし、自分がもう大人になってしまって、ある程度答えを知ってしまったからかもしれない。
経験と引き換えに新鮮さを失うのは、こんなにも現実世界へと引き戻されるのかと知ると何とも言えない気持ちにもなってしまう。
けれども、これからの自分の人生が暗くなる一方だとは思わない。
それは私にも少年時代があったからだ。
彼らのような大冒険ではなかったかもしれないが、少年時代をぎゅっとすれば毎日新しい発見があって、失敗があった。
頭では覚えてなくても、その場所やにおいに触れれば思い出す記憶もあるはず。
どんなくだらないことも、私にとっては大切な思い出。
私がした経験は後ろから未来を照らしてくれると信じている。
だから、私の人生はまだまだ楽しくなるはずだ。
少年時代は良かったという羨望の気持ちよりも、少年時代に自分が少年であったことが愛おしい気持ちで今は満たされている。
あの頃、共に過ごした友達たちとはもう10年以上会っていない。
どこで何をしているかもわからないし、きっとこの先、会うことも会いたいとも思わないだろう。
でも、みんな幸せで楽しく生きてたら嬉しいな。
(文字数:856字)
抽象的にとらえるか具体的にとらえるかで解釈は変わるかもしれない
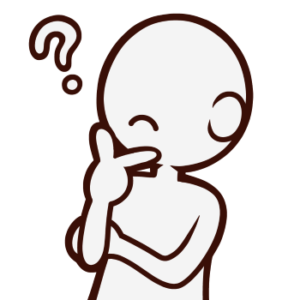 この映画は抽象的な視点でとらえるか、具体的な視点でとらえるかで解釈が変わるような気がします。
この映画は抽象的な視点でとらえるか、具体的な視点でとらえるかで解釈が変わるような気がします。
私は抽象的にとらえていて、彼らのした行動を通じて自分の少年時代を思い出しました。
なので、どちらかというと懐かしさやノスタルジーな気持ちでいっぱいになりましたね。
また、具体的にとらえることもできるでしょう。例えば登場人物たちと同じように少年時代に複雑な家庭環境で育った方は具体的にこの映画をとらえたかもしれない。
夜の森や死体を見つけたシーンでゴーディとクリスが語り合い、想いを言葉にする場面などで、自分を重ねて自分の少年時代を思い出した人もきっといると思う。
ただ、共通しているのは【抽象的にとらえても、具体的にとらえても、少年時代を思い出す人は多い】ということ。
そして、そこに『スタンドバイミー』という映画が名作だと言われる理由があると私は考えています。
名作と呼ばれる理由はある種の『通過儀礼』だから
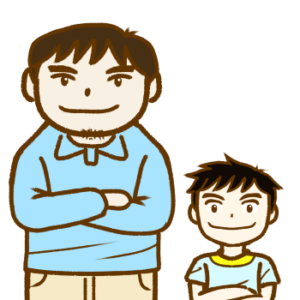 『スタンドバイミー』が名作と呼ばれる理由は、ある種の『通過儀礼』だからと言えるかもしれません。
『スタンドバイミー』が名作と呼ばれる理由は、ある種の『通過儀礼』だからと言えるかもしれません。
通過儀礼とは、砕け言い方をすれば『人間が成長する過程で起きる節目のこと』かな。
『ある種の通過儀礼』と表現したのは、『みんなに共通した儀式ではないけれど、みんな必ず似たような経験を通ってきたはず』だから。
例えば、私だったら小学生の頃によく遊んでいた子が私立の中学校を受験した時に、『あっ、一緒の中学校には行けないんだ…』と知って、その時に『ふーん、そうなんだぁ…』という気持ちになりました。
「家近いし中学生になっても遊ぶでしょ!」なんて頭では思っていたけれど、結局、一度も遊ぶことはありませんでした。
こんな感じで、誰しもが子供から大人になっていく出来事、ずっと子供ではいられない瞬間を経験しているはず。
みんな経験していることだから映画の内容に共感しやすいし、それぞれに少年時代があるから思い思いの感情が芽生えてくる。
共通認識はあるけれど、人それぞれの感動(答え)がある。しかもそれが、少年時代という誰しもが通る道(通過儀礼)で世代も性別も関係ない。
そんなところ名作と言われる理由なのかなと思います。

簡単に言えば『スタンドバイミー』が名作と呼ばれる理由は「懐かしい気持ちが蘇ってくるから」ってことですね。
「女性には分からない」という評価はセンスのない意見
『スタンドバイミー』は女性の登場人物がほとんど出てきません。男臭い映画でひょっとしたら『刃牙』より女性が出てこない作品かもしれません。笑
なので「女性には分からないだろう」みたいな評価があるかもしれないですが、それは非常にセンスのない意見でしょう。
少年時代という設定になっていますが、この少年には『少女』の意味も含まれていると思います。
小学生の頃は男女関係なく一緒にドッジボールとかしてましたよね?そこに性別の差なんてなかったはず。
思春期までは女の子も男の子とある程度同じように成長していきますし、どちらの性別もどこかのタイミングで子供から大人になる出来事があります。そこは共通認識できるところでしょう。
だから女性にはわからないということはないし、『スタンドバイミー』は性別関係なしで面白いと感じられる作品なのですね。

まぁ「またバカやっちゃって!男ってホントに子供ね。全然理解できない♡」みたいな女性側の意見はあるかもしれませんが…(^^;)
そして、これは憶測ですが、女性がほぼ出てこないのは、女性は大人の要素が出やすいからかなと。
男の子より女の子の方が成長が早いですし、精神年齢も高いように思います。特に子供の頃は。
だから子供から大人になることを表現するのには少年の方がしっくりくるし、別に登場人物を少年にしても女性は理解できるはず…。
逆に、もし『女性版スタンドバイミー』があったとして、そこで繰り広げられる葛藤は男性には理解できない(経験してない)感覚かもしれない。
『スタンドバイミー』の登場人物の男女比が逆転した物語を想像してみると…少なくとも伝えたい事は変わりそうですね。
まぁ、理解できないから人って優しくなれるんだけどね(´_ゝ`)フッ

……うん、なんかごめん(;´Д`)チョウシノッタ…
「あの12歳の時のような友達はもうできない」は名言
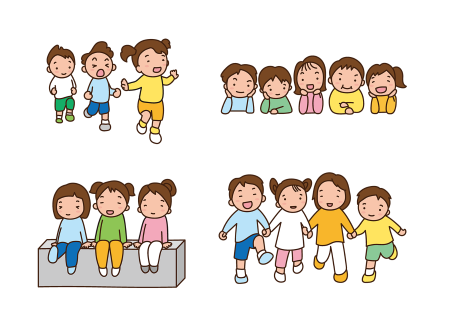 「あの12歳の時のような友達はもうできない」は名言。
「あの12歳の時のような友達はもうできない」は名言。
これは説明不要でしょう。それぞれが感じていると思うから。
いくつになっても友達はできる。でも「あの12歳の時のような友達はもうできない」ですね。
何が楽しくて一緒にいたのか。何がそんなに自分を動かしていたのか。
説明なんてできないし、そんな次元の話ではない。
子供の頃は持っていなかったのに、大人になって身に着いたものが邪魔する以上、「あの12歳の時のような友達はもうできない」でしょう。
このセリフは『スタンドバイミー』を象徴する言葉ですね^^
『スタンドバイミー』の曲を聴いてみよう!
『スタンドバイミー』と言えばやっぱりあの曲を思い出しますよね(*´з`)ボボボンッボンッ♪
僭越ながら私からひと節…「ウグナッ!ソポ~!」(ノ゜∇゜)ノ♪
…果たして「ウグナソポ」を知っている人がどれだけいるのだろうか?笑
私もうろ覚えですが、『ロンドンハーツ』だったかなー?ロンブーが出てた番組ってのは覚えているのですが、番組名までは覚えてないなー。おそらく20年以上前のテレビの話ですからね。(ご存知の方がいたら嬉しいです!(´艸`* 笑)
お耳なおしにちゃんとした曲を聴いてみましょう。
素敵な曲ですね^^
簡単に日本語で要約すると、
「暗闇で月明かりしか見えなくなっても君がいれば何も怖くない」
「空や山が崩れて海に沈んでも君がいれば泣かない」
って感じ?
まぁ「君がいれば何があっても大丈夫」ってことですね。
ラブソングとして捉えることも出来るし、友情ソングとしても受け取れる。君を過去の自分と考えて、想い出の歌と考えるのもいいかもしれません。
映画同様、いろんな解釈が出来る素敵な歌ですね^^
『スタンドバイミー』で気になるあの意味を考察!
 『スタンドバイミー』は具体的な表現よりも抽象的な表現の方が多いと思うので、物語をそのまま捉えるとつまらないと感じる場合もあるかもしれません。
『スタンドバイミー』は具体的な表現よりも抽象的な表現の方が多いと思うので、物語をそのまま捉えるとつまらないと感じる場合もあるかもしれません。
メタファー(あからさまな比喩表現を使わない喩え)の多い作品なので、分かりにくい部分もありますよね。
簡単に言えば、『子供と大人』や『子供と大人の境目』を表現しているでいいと思いますが、私も意味が分からなかったシーンがいくつもありましたし、回収できていない伏線みたいなのもあるでしょう。
ですが、せっかくなのでいくつか興味深い部分をピックアップしてみます。
意味が分かった方が映画をより楽しめると思いますし、私なりに『スタンドバイミー』を観て感じた「あれってこういう意味なんじゃないかなー」とか「そういう意味だったのかー」というのを書いていきますね。
なぜ汽車は線路を歩く少年たちの後ろからやってきたのか?その意味とは?
 少年たちは死体を探しに行く際、線路の上を歩いて目的地に向かいました。
少年たちは死体を探しに行く際、線路の上を歩いて目的地に向かいました。
この線路は『大人へと通ずる道』を表していると思います。
そして、線路を歩くシーンで特に印象的なのは『橋を渡る場面』。
橋を渡っている途中で汽車が来て、観ている方も「わぁ~危ない~(゜.゜)」なんてなりましたね。
あのシーンはおそらく『子供にはもう戻れない』ことを暗示しているのでしょう。
少年たちの後ろから汽車が来たのも、子供の世界から大人の世界へと無理矢理進んでいくこと、大人になったらもう子供には戻れないことを意味していると考えられますね。
そして、この『橋』が子供と大人の境界線だと考えると面白いことがわかりますよね。それは『クリスとテディはすんなり渡っていた』のに対し『ゴーディとバーンはなかなか渡れなかった』ということ。
大人になることをすんなり受け入れられる子もいれば、なかなか受け入れられない子もいるということ。
進んで大人になるのもいいし、なかなか受け入れられずに大人になるのもいいし、何となく大人になってもいいと思う。
それでも時間は待ってくれない。大人になることは避けられないのですね。
子供からしたら大人になることが不安だったりするのかなー…まぁでも、大人になっても『トイザらス』はやっぱり楽しいぞ!ヾ(≧▽≦)ノボクラハトイザラスキッズ!!
ちなみに、汽車(列車)にはポジティブもネガティブもいろいろ意味が込められると思います。列車で思い浮かぶ名曲と言えば、THE BLUE HEARTSの『Train-Train』ですよね。
この曲から感じられる『列車が持つイメージ』を3つほど私なりに書いているので、良ければご覧ください^^
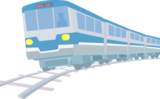
死体を見つけたシーンを考察!
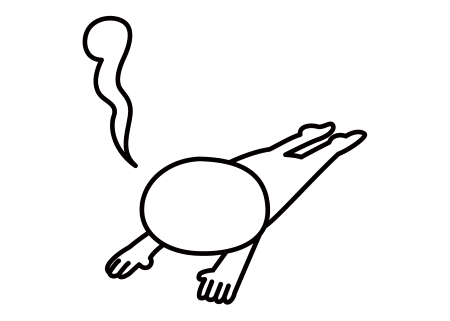 『スタンドバイミー』の目的は死体を見つけるというもの。
『スタンドバイミー』の目的は死体を見つけるというもの。
実際に物語の終盤で死体を見つけましたが、その時の少年たちの表情が私にはすごく印象的でした。
それは、少年から大人になる瞬間を見て、この映画のテーマを最も具体的に表しているシーンだと感じたからかな。
『死体』は『現実を表している』のかなと思いました。
今まではバカやって楽しく生きてきた、夢の中で生きてきたような時間だったけれど、本当に死体を見つけて現実を目の当たりにした。
この旅で初めて本当の意味で大人になる瞬間(具体的な何か)を体験したのがこの死体を見つけたシーンだったのかなと思います。
こんな感じで、比喩表現がこの映画には散りばめられていると分かると一瞬にしてこの世界観に引き込まれますよね^^
その他タバコや帽子を奪われるシーンなどの解釈をしてみよう
特に印象的なのは汽車のシーンと死体を見つけたシーンだと思いますが、それ以外にもさまざまなシーンで『子供』や『大人』を感じるシーンがありましたので、簡単に見ていきましょう。
タバコは大人への憧れ
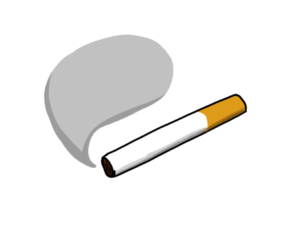 冒頭、子供たちがタバコを吸うシーンから始まりましたが、タバコは『大人への憧れ』の意味。これは何となく理解できますね。
冒頭、子供たちがタバコを吸うシーンから始まりましたが、タバコは『大人への憧れ』の意味。これは何となく理解できますね。
何の銘柄吸ってたんでしょうか…『わかば』かな?笑(-。-)y-゜゜゜
ちなみに、私はタバコを吸ったことありません。鼻炎がひどいので吸えないのです( ̄ii ̄)ズルズル
帽子を奪われるシーンは子供と大人の絶対的な力の差
ゴーディとクリスが街でエースに帽子を奪われるシーンがありましたが、あれは子供と大人の力の差を表していると思います。
同時に誰しもが感じたことのある感情「不良の兄ちゃん怖ぇよ(´;ω;`)」ってやつだね。
これはみんな経験があるんじゃないかな?
絶対的に子供は大人には勝てないもの、『抗えない存在』があることを暗示しているのでしょう。
でも、いつも誰かとつるんでいるところから察するに、意外と小心者なのかもしれませんね。
銃は男性器のメタファー
 銃が男性器のメタファーというのは割と知られていることかもしれませんね。ロック系の歌詞でそういう意味として使っていることもありますし。
銃が男性器のメタファーというのは割と知られていることかもしれませんね。ロック系の歌詞でそういう意味として使っていることもありますし。
これは知らなかったのですが、序盤で銃を発砲して「誰がかんしゃく玉でいたすらを」と女性が出てくるシーンがありましたが、かんしゃく玉は『童貞』を意味しているそうですね。
かんしゃく玉は英語で『cherry bomb』と表現することがあるそうで、『チェリー=童貞』だとのこと。
ちなみに、銃がいつも男性器を表しているわけではないと思いますよ。
例えば、死体を見つけたシーンでエースと対峙した際にゴーディが発砲したのは『男として勇気を出した』と私は捉えました。
「(ナメるほどデカいのか?)ぼくのはデカいさ」というセリフは、『男としては俺の方が上だよ』というニュアンスがあったのかなと感じます。
鹿と出会ったことを誰にも話さなかったのはなぜ?
森で雑魚寝をした翌朝、ゴーディは鹿と出会いましたが「その事は誰にも話していない」と言っていました。
この一連のシーンに関して私は全く意味がわかりませんでした。
そこで鹿が何の象徴なのかを調べてみたところ、(いろいろ意味があったのですが)その中に『死と再生を象徴する動物』というものがありました。
鹿の角は生え変わりますが、それが『死と再生』を意味するそうです。
おそらくゴーディはお兄さんの死を彼なりに受け入れようとしたのだと思います。
角の生えていない鹿について誰にも話していないのは、たとえ友達でも共有できない感情だと思ったからなのかな。
パンツの中にヒルがいたシーンは性の目覚め
線路から外れて森の中を突っ切ったとき、沼から這い上がるとヒルに噛みつかれるシーン。
不幸にもゴーディはパンツの中にもヒルがいて、血が出てました。
私は思わず顔をしかめて「ひぃぃぃ(/o\)」と目を覆いたくなってしまいましたが、あれも単純な面白シーンではなさそうです。
あのシーンは性の目覚めを表していると考えられるかもしれません。
少年たちの中でも少し中性的なゴーディのパンツの中にだけヒルがいましたが、ゴーディはあのシーンの後、「絶対に死体を見つけるんだ!」と人が変わったようになります。言い換えるなら「男らしくなった」と表現すればいいですかね。(男らしいって表現は今は適切じゃないのかなぁ…)
少年と少女はある程度の年齢までは同じように『子供』としてくくれますが、大人になっていけば性差は生まれます。
そういう意味でヒルに噛まれたシーンは『性の目覚め』を暗示しているのかなと考えられます。
血が出るというのは女の子特有の成長、初潮(生理)を表現しているとも考えられますし、男女で受け取り方が違ってくるシーンかもしれませんね。
こんな感じで『スタンドバイミー』にはいろんな仕掛けがあります。
もちろん、場所や物、動物だけでなくそれぞれの登場人物から見えてくるものもあります。例えば、家庭環境の悪かったクリスが銃(暴力)ではなく、弁護士(知性)を身に着けたことなど。
私の解釈が間違っている部分もあると思いますし、細かい所に目を向ければ数えきれないくらいの仕掛けや意図があるはずです。それこそ1回2回観ただけじゃわからないでしょう。

…なるほど、確かに何度も観たくなる作品ですね^^

まとめ:『スタンドバイミー』は紛れもない名作
本当はまだまだ書きたいことがたくさんありました。
例えば、
「スラング多いな!字幕ってこの表現OKなの?地上波放送だとどう表現されるんだろう?(゜-゜)」とか。
「“ロリポップ”聴くとバナナマン思い出すよね!ヽ(^。^)ノ」とか。
「パイ食い競争ってイッテQで宮川大輔が挑戦したヤツか!(゚∀゚)」とか。
本当にいろいろ書きたかったのですが、書ききれないのでこの辺でやめておきます。
とりあえず、『スタンドバイミー』は紛れもない名作とだけはわかりました。また観よう^^
名作と呼ばれる映画はやっぱり面白いんだなぁ。もっといろいろ観てみようかなー(゜.゜)
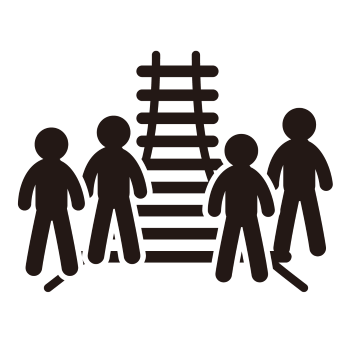

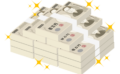
コメント
ウグナ、覚えています。
素人さんが歌っていたと記憶してます。けど、ロンブーだったかは覚えてない^^;
>コメントありがとうございます!
まさか覚えてらっしゃった方がいるなんて!(≧◇≦)<ウレシー!!! 私も記憶が曖昧ですが「何か面白かった」という感覚だけ残っています(^_^;)