太宰治の『人間失格』の読書感想文を書きました。
読んだ事があるなしは置いといて、知らない人はいない作品でしょう。
太宰治の捨て身の問題作とも言われたりしますが、今の自分が『人間失格』を読んでみてどう感じるか?それを確かめたいと思います。
まずは読書感想文からご覧ください。
『人間失格』の読書感想文【800字】
『世間というのは、君じゃないか』作品を読み終えてもこの言葉が頭から離れなかった。
葉蔵は『世間とは個人じゃないか』と思うようになり、そう思うことによって自分の意志で動けるようになった。
この言葉に救われた人はきっと多かっただろう。
けれども、今、そしてこれからの日本においてこの言葉をそのままの意味で受け取ってしまう人がいないか、私は不安に思う。
多くの人は世間に怯えている。それは世間という言葉は知っていても、そこに実態がないからだ。
空気を読む、暗黙の了解などの言葉があるように、言葉の意味はわかっていてもモヤモヤした気持ちが晴れず、この気持ちを処理できない事から恐れや居心地の悪さを感じてしまうのだろう。
しかし、「世間とは個人」と認識することでそこには実態が生じ、明確な答えに触れることができる。
答えを見つけることで目標が生まれ、それこそ葉蔵のように意志を持って人は行動を起こせるはずだ。
ところが、今の日本においてこの言葉を文字通りに受け取るのは危険な気がする。
それは今は世間における個人の尊厳が強すぎるからだ。
今は国民一人一人の言葉の力が強まっている。そして、関心を持った物事に対して言い争いが生まれる。
けれども『人間は決して人間に服従しない、奴隷でさえ奴隷らしい卑屈なしっぺ返しをするものだ』と書かれているように、言い争いに終わりはない。
争いが終わるのは個人がそれに飽きた時か、また別の関心事を見つけた時だけだろう。
この恐ろしさは想像に難くないはずだ。
「世間とは個人」、だからと言って世間と個人を切り離して考えてはいけない。
私たちは「世間とは個人」の意味をいま一度見直すべきだ。
だが、それは決して難しいことではない。個人は世間があって存在していることを認識すればいい。
つまり「自分が存在しているのは他人がいるからだ」と思うだけでいいのだ。
それだけで「世間とは個人」の意味を履き違えることはないだろう。
(文字数 800字)
『人間失格』読書感想文の解説
「最近『個人』が強いなー」って思うんですよ。
それが良いのか悪いのかは分からないのですが、個性の意味を履き違えている人が増えたというか…可視化されるようになってきたのかな?と感じています。
こういう事を書くと、「テメェもな」とブーメランが返ってくるので嫌なのですが、幸い私は弱い『個人』なので、人に見つかることはないでしょう。笑
さて、『人間失格』を読んだ時に『世間というのは、君じゃないか』という言葉が凄く引っかかったのも、いまの世の中の『個人(個性)』の強さに私が戸惑いを感じているからかもしれません。
「個人は世間があって存在している」としたのは、そんな自分の戸惑いを正当化するために書いている部分もあります。
個人とか個性とか、近年すごく重視されているけれど、それが私は好きくないんです。
なんでそう思うのか?それは曖昧さが失われているからなのですね。
曖昧さがなくなって生きにくい
 学校や会社、組織などで「人間関係が嫌」って人は多い…よね?
学校や会社、組織などで「人間関係が嫌」って人は多い…よね?
それは『空気を読まない』といけなかったり、間違っているのに違うと言えない関係や環境があるからと思います。
本当は答えや考えがあるのに、不安定な気持ちや環境の中で生きてるから嫌なのかなと。
でも私はそうじゃないんです。
あまり『空気は読まない』し、嫌な人間とは離れるし、ドライな人間です。
そのせいか【曖昧さや正解がわからないものが好きで、その状態を考えたい、楽しみたいと思う性格をしている】のですね。
『曖昧』って余白があって遊び心があるじゃないの?
UFOがいるかいないかはっきりさせるより、いるかいないかを考えるのが楽しいじゃない?
だから、曖昧さが失われつつある現代がすごく嫌で、その気持ちを読書感想文で書いたつもりです。
★小説の読書感想文

世間とは何か?世間とは曖昧なものである
私の書いた『人間失格』の読書感想文には欠点があります。それは「世間」が何なのかを示していないこと。
おそらく、多くの方が納得できない終わり方をしているでしょう。
ただ、世間について触れるのはめんど…自分でもよくわかっていないので、何となく800字程度でおさめて、スッキリした感じを演出してみました。
さて、「世間とは何か?」という事に関しては阿部謹也さんという歴史学者が著書を書いていて、その事について触れているサイトがあったのでそちらから引用します。
これによると
『世間とは曖昧なもので、その曖昧な世間との間で形成される日本の個人は曖昧なものである』 参考サイト:「世間」とは何か?-阿部謹也
とされているわけです。
西欧は個人の尊厳が認められている社会だけど、日本は個人の尊厳が認められていなくて、その代わり世間と言う枠組みで活きていると。
一見すると「個人の尊厳を認めろー!」となりそうだけど、日本人って世間に依存してたり、守られてたりするわけじゃない?
みんな何となくのルールや共通認識を持っていて、それがあるから助かっているところってない?
西欧やアメリカみたいに何かある度に「訴訟だ!裁判だ!」ってなったら、そっちの方が面倒じゃん?

世間と言うのは曖昧なもの、だから曖昧な部分を考慮したり、許容したりした方が日本人は生きやすいと私は思うわけですね。
日本人はもともと曖昧な民族である
「日本人はもともと曖昧な民族だ」という認識を持ってくれたら、私は生きやすいです。
以前、新渡戸稲造の『武士道』を読んだのですが、日本人は独特な民族なんですね。
日本の武士道(道徳)はそもそも成文法(体系化)されていない、つまり、もともとが『何となく』なんですよ。だから、無理に白黒はっきりさせなくていい。
ピース・又吉直樹さんの『火花』を読んだ時も、「又吉さんが白と黒の間に色が合っていいし、グレーの中にも色の濃さがあっていいと言ってくれた気がした」みたいなことを書いたのですが、こんな風に答えにグラデーションがあっていいんじゃないのって。
そんな風に私は思うし、海外に留学した経験からも「日本人の『察しや思いやり』って素晴らしいと感じた」と書きました。
『察しや思いやり』のような曖昧なものが日本人のベースになっているし、私はその『武士道精神』みたいな曖昧なものを育ってきた環境で受け継いできたので、ベースは曖昧なものなんだと思います。
だから、個人が強くなるのは嫌だし、曖昧さを許容できない世間になるのは生きにくく感じてしまいます。

ちなみに、『武士道』では『日本人は民族レベルで個性のあふれる人々』的なことが書かれているのよ。要は存在自体が個性的な訳です。
だから、個人や個性なんて無理に主張することないし、自分が曖昧なものと分かっていれば、逆にはっきりした答えもその時々で出せるはず。
…まぁでも、今の流れは止まらないんだろうなー。。。
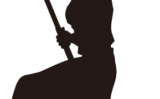
中学生や高校生が『人間失格』の読書感想文を書く時のポイント
『人間失格』は私が中学か高校の時に読んだことがあるのですが、その時には感じられなかった部分に着目して読書感想文を書いてみました。
『世間』を意識するようになるのは大人になってからだと思うので、中学生や高校生の頃の自分が『人間失格』の読書感想文を書くなら、「葉蔵は人間失格なのか?いやそうじゃない」みたいな感じで書くかな?
そこから「じゃあ自分はどうだろう?どうするべきだろう?」みたいな展開ですか。
タイトルになっている『人間失格』の部分に注目したほうがウケはいいですよね。わかりやすいし。
そういう事を頭でわかっていながらそれを書かない。こういうヤツが組織で動けないのよ。笑
ちなみに、子どもの頃に『人間失格』を読んだことがあるだけで、当時は全部読んでなかったと思います(^^;)
今回ちゃんと読んだのは初めてだと思うので、最後まで本が読めるようになったと感じられただけでも成長したのかなーと思います^^
『人間失格』のあらすじ
『人間失格』のあらすじに関してはいつも通りWikipediaを確認していただければと思います。
私なりに簡単なあらすじを書くとすれば、、、
幼少期から他人の気持ちがわからない、自分の心情も理解されない主人公の葛藤と、その苦しみから逃れるためにもがく人物のお話。
酒や女、薬に溺れて脳病院に入れられる。
自分では思っていなかったけれど、狂人の烙印を押されてしまい、ここから出ても狂人や廃人としてこの先の人生を生きていくことになって絶望。
自分のことを「人間失格」と評するわけですね。
こんな感じですか?違うかも。笑。自分でちゃんと読んだほうが良いですね。
『人間失格』はただ暗いだけの小説なのか?
『人間失格』ってただただ暗くて、読み終わった後にどよーんとした気分になるだけの小説っていうイメージがあったけど、でも実際はそんなそんなだったかも。
確かに読み終わった後、しばらくはその場から動きたくなくなるくらい気持ちが沈むのですが(笑)、希望も何もないわけではないと感じるわけではなかった。
例えば、葉蔵の周りの人、特に女性には魅力的な人物に映っていたはずだし、自分の負の部分に目を向けられる葉蔵を別に弱い人間だとは思いませんでした。
酒も女も薬も、それ自体は悪いわけではない。時に救いになるものだし、依存しなければ人生を豊かにしてくれるはず。(でも違法薬物は絶対ダメよ!(。-`ω-)
快楽に溺れる怖さみたいなのは改めて学ばされた気がしますし、女性って本能的に『悪い男』や『ダメな男』に魅力を感じてしまうんだろうなーと思いました。
んで『女は悪い男に惚れるのか…』『いやいや悪い男ってそういうんじゃないから!』とか、『テクニックを磨く男』『見抜けない女』とか、、、そんな感じでわちゃわちゃしてエンタメになるんだろうね。笑
チャップリンの名言で『人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ』という言葉がありますが、『人間失格』は自分に一番近い人間(自分)が自分の心を直視していたから悲劇の要素が強かったのかもしれませんね。
『人間失格』を読んで感じた希望
『人間失格』は読む人によっては「救われた」と感じたり、「まるで自分の姿を見ているようだ」と感じたりしますよね。
だから、自分が持ってるマイナスの部分(コンプレックス)って、自分以外の人の救いになったりするんだろうね。
太宰は『人間失格』を執筆した数ヶ月後に入水心中しましたが、もし「あなたのおかげで救われた」と言う人が後にたくさん出てくると知ってたら、考えが変わってたりするのかなー。
ただ、それすら許さないくらいの覚悟や言葉の強さを感じる部分もあるかな。
『人間失格』は確かに問題作かもしれないけれど、問題を提示してくれたおかげで答え探しをする側の人間は生かされている、そんな気がしました。
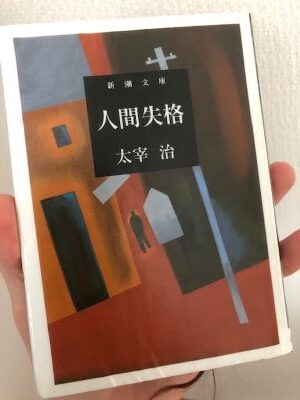

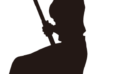

コメント